
厚い縦割りの壁を乗り越え、九州から意識変革の風 がんのチーム医療を未来へ託す
2010年2月
九州がんセンター乳腺科部長の 大野真司さん おおの しんじ 九州がんセンター乳腺科部長。1958年、福岡県生まれ。九州大学医学部卒。九州大学病院を経て、2000年から九州がんセンターに勤務。乳がんのチーム医療の専門家。著書に『明日から役立つ乳がんチーム医療ガイド』(金原出版)。多職種の医療者が乳がんの啓発活動を行う団体、NPO法人ハッピーマンマ代表理事2009年8月、九州福岡市で行われたセミナー...

2010年2月
九州がんセンター乳腺科部長の 大野真司さん おおの しんじ 九州がんセンター乳腺科部長。1958年、福岡県生まれ。九州大学医学部卒。九州大学病院を経て、2000年から九州がんセンターに勤務。乳がんのチーム医療の専門家。著書に『明日から役立つ乳がんチーム医療ガイド』(金原出版)。多職種の医療者が乳がんの啓発活動を行う団体、NPO法人ハッピーマンマ代表理事2009年8月、九州福岡市で行われたセミナー...
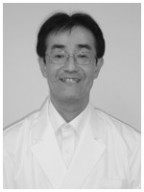
2010年2月
埼玉医科大学国際医療センター 臨床腫瘍科・腫瘍内科の 藤田健一さん バイオマーカーは、抗がん剤の効果と副作用をあらかじめ予測する手段として、今治療現場での応用が進んでいる。 しかし、埼玉医科大学国際医療センター臨床腫瘍科・腫瘍内科で薬学を専門とする藤田健一さんによると、バイオマーカーの利用価値はそれにとどまらないという。藤田さんに、バイオマーカーの現状と展望について聞いた。 効果と副作用の個...

2010年2月
NTT東日本関東病院 消化器内科・内視鏡部部長の 松橋信行さん 胃からも、大腸からも到達しにくい小腸。その内部を、痛みを伴わずして知る術がある。カプセル内視鏡だ。その使用によって多くの患者さんの病変を見つけることができるようになった。真っ暗な小腸を照らし出す、画期的な検査だ。 オレンジ色のものはカプセル内視鏡のキャップ。データレコーダなどの取り付けが終わったあと、カプセル内視鏡を飲み込む...
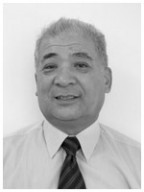
2010年2月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 67歳の男性Pさん。大腸がん検診(便潜血反応検査)で陽性となり、精密...
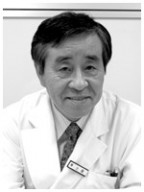
2010年1月
日本医科大学付属病院 病理部教授の 土屋眞一さん これまで、患者の前に姿を見せることがなかった病理医。しかし、病理医の診断によって治療方針が決まるなど、病理医は非常に重要な役割を果たしている。そこに着目した患者側の要請もあって、いよいよ病理医が表舞台に出てきた。患者の素朴な疑問に答えようと、患者の前で説明をしだしたのだ。 「これがあなたのがんです」 「へえー 初めて見ました」 じっくり1時間...
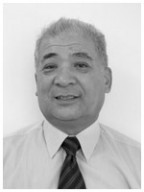
2010年1月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 62歳の男性Qさん。半年ほど前から、便に血が混じるようになる。長年患...
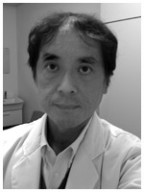
2010年1月
三重大学大学院医学系研究科 消化管・小児外科 准教授・病院教授の 三木誓雄さん がん患者の体内では絶えず炎症が起こっている。実はこの炎症ががん細胞の増殖と関係しており、この炎症を抑えることで今注目を集めているのが栄養成分EPA(エイコサペンタエン酸)だ。現在、このEPAを中心とした栄養療法で、がんと免疫栄養療法に関する研究を進めている三重大学では、栄養療法の可能性の高まりを感じさせる研究デー...

2009年12月
九州大学大学院医学研究院 先端医療医学教授の 橋爪誠さん 内視鏡以上に体への負担が少なく、安全性が高いと注目されている内視鏡ロボット手術。アメリカでは、すでに前立腺がん手術の大半がロボット手術(ダヴィンチ)で行われています。このロボット手術をいち早く臨床に取り入れているのが、九州大学大学院医学研究院先端医療医学教授の橋爪誠さんです。ロボット手術の現状とその利点について聞きました。 内視鏡の限界...

2009年12月
独立行政法人国立病院機構(NHO) 東京医療センター栄養管理室長の 石長孝二郎さん がん治療中の患者さんは副作用のために食事が摂れない人が多い。患者さんにとって「食べる」こととは、生命の維持としてばかりか、生活上の喜びであり、がんと闘う精神的な励みにもなる。ところがこの問題はこれまで放置されたままであった。 患者さんの「食べられない」苦しみに目を向け、生み出されたのが「副作用対策食」だ。そ...

2009年12月
選べて食べられてほっとして、患者さんの表情が変わる! 栄養管理室長の河内啓子(左)さんと調理師長の立田秀義(右)さん。ここでは管理栄養士、栄養士、調理師の全員が副作用対策食のアイデアを出して、試作し、メニュー作りが行われている 四国がんセンターの病院食で驚くのは、いろいろなセットがいくつもつくられ、患者さんの要望に迅速に応えられようになっていることだ。抗がん剤による食欲不振や吐き気で食べら...