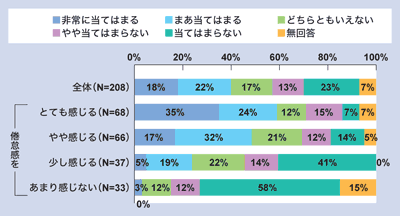「がんの倦怠感」調査結果
がん患者さんの多くは倦怠感を感じている。しかし、それを医師には伝えていない
 聖路加国際病院
聖路加国際病院ブレストセンター長・
乳腺外科部長の
中村清吾さん

十和田市立中央病院院長の
蘆野吉和さん
8割ものがん患者さんが倦怠感を感じていることが、がんサポートとNPO法人キャンサーリボンズが患者さんを対象に行ったアンケート調査の結果、わかりました。
しかし、そのことを患者さんは医療者に伝えていません。そこで、この問題についてがん医療に取り組む医療従事者たちやNPO団体は何ができるのか――。
がん医療の最前線で活躍中の6人に、それぞれの立場から話を伺いました。
アンケート調査について
 神奈川県立がんセンター
神奈川県立がんセンター呼吸器科医長の
坪井正博さん
 大阪府立大学看護学部
大阪府立大学看護学部療養支援看護学講師の
田中登美さん
 藤田保健衛生大学医学部外科・
藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学講座教授の
東口高志さん(*)
 NPO法人キャンサーリボンズ
NPO法人キャンサーリボンズ副理事長の
岡山慶子さん
*東口高志さんの「高」は正しくは「はしごだか」です
背負う役割が多い若い人に倦怠感
アンケート調査結果によると「倦怠感を感じているか」との質問に、8割以上が「感じている」と回答。特徴的だったのは、30代が倦怠感を強く感じていたことでした。
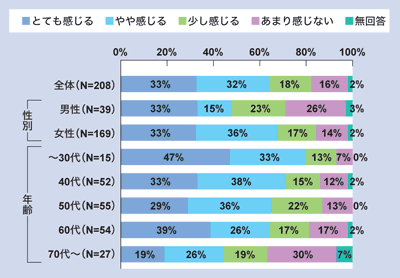
蘆野 若い方は日常生活の活動度が高く、病気前と同じレベルで動けないと、うつ状態になりやすいと思います。また、患者さんは、倦怠感を話すことで楽になります。医療者にわかってもらったことで、倦怠感を軽快させる方向にもっていくことができます。その人が生活の中で何にいちばん倦怠感を感じているのかを聞き出し、そこをどう改善するかを医療者が考えることが必要です。
田中 患者さんの今までの生活体験が、感じ方に影響していると思います。30代、40代は人生経験が少ないため、コーピング(ストレスに対処する技術)パターンも少ない。しかし、70代、80代はいろいろな人生経験をつんでいるので(ストレス対処の)引き出しがたくさんあります。さまざまな危機も乗り越えてきているので、同じ病気でも苦しみの度合いが違うようです。30代の患者さんの訴えには集中力がない、やる気が出ない、疲れるなどが多く、いわゆる適応障害が関係している印象です。
中村 仕事に加えて、子育てや家事などといった背負う役割が数多い30代、40代などの若い女性は今までできたことができなくなることに対するギャップが大きく、落差が激しい。それが、倦怠感という症状となって出てくるのでしょう。
東口 患者さんの背景に何があるか、を知る必要があります。「だるい」と訴える終末期の患者さんの血液中の乳酸値を測定すると、非常に高い値を示すことがあります。医学的に乳酸値が高いと、強い倦怠感を訴えます。一方、数値が低いのに、「しんどい」という人もいます。しかし肉体的なだるさをとることで、精神的なつらさが減る人もいます。いろいろな要素が絡み合って、「だるい」という表現になっています。
倦怠感と仕事は双方向の関係にある
「具体的にするのがつらいこと」の調査結果を見ると、「仕事が以前ほどできない」ことを4割もの人が感じており、倦怠感と仕事が密接な関係にあることがわかりました。
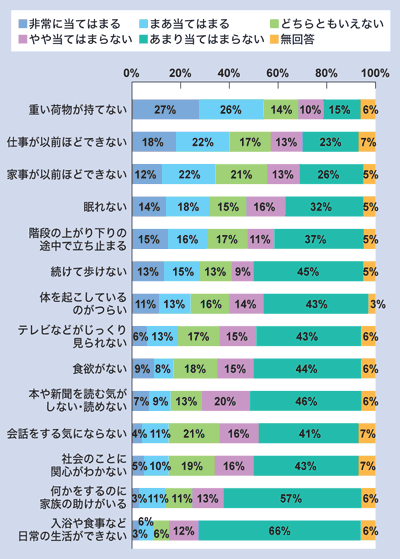
中村 乳がんの手術で3~4日入院し、通院治療を受けている人は、一見前と変わりなく見えます。まわりにも「社会復帰できるね」とか、「前と同じように働ける」と思われがちですが、本人はまだ非常につらく、そこに大きなギャップを感じていることが少なくないようです。
東口 倦怠感で仕事ができないということもあるでしょうが、仕事ができないから感じるのではないでしょうか。この2つは、双方向と考えるべきでしょう。
坪井 私の診察の中でも、多かれ少なかれ、ほとんどの患者さんが倦怠感を感じていらっしゃるようです。とくに抗がん剤、放射線などの治療を受けると、体はだるくなります。だからといって、安静にしていればいいということではありません。仕事に限らず、日常生活に戻ることも、1つの治療です。体力がないと治療のダメージ(副作用)を受けやすいので、当たり前のことですが、「食べる(栄養を摂る)、寝る、体を動かす」の3原則が生活の基本です。病状を理解して、ご自分のできること、やりたいことをやってほしいと思います。