
がんによる腸閉塞に対し、大腸ステント治療で人工肛門を回避
2015年7月
「内視鏡治療の経験が豊富にあり、大腸ステントをきちんと勉強している医師が行えば、決して危険な治療ではありません」と語る斉田芳久さん がんのために大腸が閉塞した場合、かつては緊急手術が行われ、人工肛門を造設するのが一般的だった。しかし、2012年に大腸ステント治療が保険で認められ、現在では、閉塞部にステントを留置する治療が可能になっている。治療に要する時間は、通常15分程度。ステントが入ると速やかに...

2015年7月
「内視鏡治療の経験が豊富にあり、大腸ステントをきちんと勉強している医師が行えば、決して危険な治療ではありません」と語る斉田芳久さん がんのために大腸が閉塞した場合、かつては緊急手術が行われ、人工肛門を造設するのが一般的だった。しかし、2012年に大腸ステント治療が保険で認められ、現在では、閉塞部にステントを留置する治療が可能になっている。治療に要する時間は、通常15分程度。ステントが入ると速やかに...

2015年7月
「術後のトラブルは、まず専門医や専門の看護師に相談することが解決への早道です」と話す舛田佳子さん 大腸がんの手術をされた患者さんは、術後の身体の変化やトラブルが気になるだろう。術後に起こりやすい症状とは?食事はどのように進めていけばいいのか?排便障害や排尿障害は起こるのか?患者さんが悩みがちな術後の生活について、専門家に聞いた。 術後に起こりやすい腸閉塞に注意 大腸がんの手術後には、どのような合併...

2015年7月
「なかなか分子標的薬が登場しなかった胃がん領域において新薬が承認されたことは1つの進歩と言えるでしょう」と語る朴成和さん 手術による切除が困難と判断された進行・再発胃がんの化学療法に、ファーストラインではエルプラット(2015年3月承認)、セカンドラインでは分子標的薬のサイラムザ(同)が加わった。かつて胃がんは抗がん薬が効きにくいがんと言われたが、着実に治療の選択肢が広がりつつある。 入院せずに外...

2015年7月
「腹膜播種の診断と治療の両方を行えるのが最大のメリットです。5年以内の実用化を目指したい」と語る辻本広紀さん これまで胃がんの腹膜播種では抗がん薬が効かなくなると、それ以上打つ手がなかったが、昨年(2014年)11月、光増感剤内包ナノ粒子を用いた光線力学療法(PDT)により、ヒト胃がん細胞を移植したマウスの腹膜播種モデルで体重減少の抑制と生存期間の延長効果が得られたとの報告があり、将来的には食道が...

2015年7月
胃がんの怖さに腹膜播種がある。決して珍しい症状ではなく、胃がんでの死亡者のうち、半数近くが腹膜播種に苦しむとされている。これまでは化学療法を受けても予後が悪いとされてきたが、近年は新しい併用療法の研究が進んでいる。その中でも、とくに注目されているのが、パクリタキセルなどを用いた腹腔内投与併用療法。この併用療法に2006年から取り組んでいるのが東京大学医学部附属病院腫瘍外科。本誌では、これまでにも数...
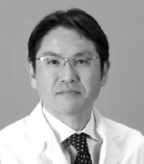
2015年7月
「社会復帰を目指した治療を行うことが大切だと考えています」と話す大幸宏幸さん 食道がんは早い段階からリンパ節転移を起こしやすい。そのため手術では食道の切除に加え、頸部、胸部、腹部に及ぶリンパ節を取り除く必要があり、体への負担が大きい。そこで、患者さんの社会復帰までを見据え、開胸・開腹よりも傷や痛みの少ない「胸腔鏡・腹腔鏡下手術」が注目されている。 切除と再建が必要な 食道がんの手術 食道がんは食道...

2015年6月
「肝がんの再発予防として樹状細胞ワクチン療法を行っています」と話す小寺由人さん 肝がんには大きく分けて、肝細胞がんと肝内胆管がんがあるが、両者ともに再発しやすく、たちの悪いがんと言えるだろう。この肝がんの再発予防を目的として、自己のがん組織を利用した樹状細胞ワクチン療法が効果を示しているという。 手術後に再発しやすい肝がんを対象に先進医療として実施 第4世代の免疫療法である免疫ワクチン療法は、昨今...
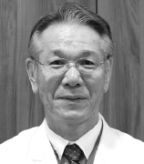
2015年6月
日本赤十字社医療センター副院長の鈴木憲史さん種類も治療法も多岐にわたる血液のがん。新しい治療薬の登場で、一昔前に比べて生存率も飛躍的に高まってきている。同時に解決を必要とする課題もまだ多く残されている。血液がんの基礎的な知識のまとめと、最近の話題を拾った。 血液がんの特徴 血液がんには多くの種類があります。性質も様々ですが、一番特徴的な白血病で見ると、皮膚や臓器にできるがん(固形がん)とは異なった...
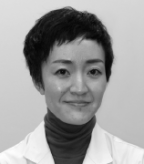
2015年6月
「今回の調査は患者さんの声という意味でとても貴重なものだと思います」と語る黒澤彩子さん新薬や移植などの治療法の改善により、白血病などの血液疾患を完治させるケースも増えており、最近ではいかに治療を終えた後のQOL(生活の質)を維持することができるかが問われるようになってきた。そうした中、国立がん研究センター中央病院造血幹細胞移植科では、急性白血病患者さんを対象に治療後のQOL調査を実施。回答内容を吟...
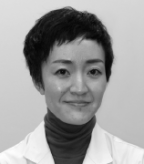
2015年6月
「今回の調査は患者さんの声という意味でとても貴重なものだと思います」と語る黒澤彩子さん新薬や移植などの治療法の改善により、白血病などの血液疾患を完治させるケースも増えており、最近ではいかに治療を終えた後のQOL(生活の質)を維持することができるかが問われるようになってきた。そうした中、国立がん研究センター中央病院造血幹細胞移植科では、急性白血病患者さんを対象に治療後のQOL調査を実施。回答内容を吟...