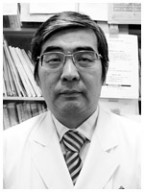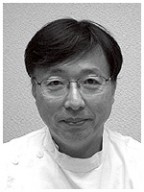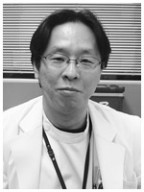2012年9月
「GC療法の登場によって 副作用は少なくなった」と話す 深沢賢さん 転移性膀胱がんの標準治療は従来から抗がん剤の併用療法で、以前は副作用が強い治療が行われてきたが、ジェムザールの登場により副作用は大幅に軽減され、患者さんのQOL(生活の質)向上にもつながっています。 全体の1割に満たない転移性膀胱がん膀胱は骨盤内にある臓器で、腎臓から送られてくる尿を一時的に溜める役割を担っています。ここにで...

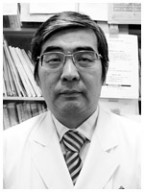
2012年9月
膀胱温存療法を 広めていきたいと話す 木原和徳さん 現在、浸潤性膀胱がんの標準治療は膀胱全摘術である。しかし膀胱全摘術は、QOL(生活の質)の面でさまざまな問題が残る治療法でもある。それを解決したのが、膀胱温存療法だ。再発も少なく、根治性も高い治療法だと期待されている。 膀胱を全摘するとその後が大変 [図1 経尿道的膀胱腫瘍切除術] 膀胱がんの標準治療は、表在がん(筋層非浸潤がん)と浸潤が...


2012年8月
「病理の専門医がいる病院なら一定の治療の質が望めます」と話す 増田しのぶさん 病理診断の結果により、その後の治療方針も決まるため、がんの治療において病理診断の役割はきわめて大きいといえます。病理診断を通じて、自分の乳がんの状態やタイプを知ることは、良い治療を受ける上でも大切なポイントとなります。細胞の顔つきで良悪を判断するのが難しい乳がん現在、乳がんは女性が最も多くかかるがんで、その罹患率は年々増...


2012年8月
再発しても治癒を目指せる 時代が来るかもしれないと話す 河野範男さん 再発乳がんの薬物療法は、近年飛躍的に進歩している。新薬が次々と承認され、治療の選択肢も増えてきた。 また、現在臨床試験が進行中のものなど、将来有望な薬剤が控えていることも見逃せない。 新薬で治癒も視野に [図1 治療の目標と考え方] ここ1、2年の間に日本でも、再発乳がんに使える新規ホルモン剤や抗がん剤などが相次いで承認され、...

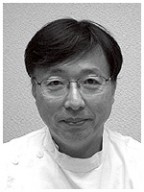
2012年8月
トリプルネガティブにも 個別化治療が期待されると話す 杉江知治さん 薬物治療の方法が限られ、予後が思わしくないとされるトリプルネティブ乳がんだが、最近は、抗がん剤によく反応するタイプが明らかになり、年齢による効果的な薬剤の使い分けも見えてきた。 術前、再発・転移時の治療として、どの薬剤をどう使ったらいいか、効果的な選択は? 期待される新規治療は? 最新情報を紹介する。 実は著効例も多いトリプルネガ...


2012年8月
術前化学療法の 有効性について詳しい 海瀬博史さん 乳房温存手術が難しい比較的大きながんをもつ患者さんに行われる術前化学療法。術前化学療法は、術後化学療法と比べて、「乳房温存率の向上」と「わずか半年の化学療法で10年後をある程度予想できる」という大きなメリットが確認された。 また、ハーセプチンの登場後、新しい治療薬の開発が進み、医療現場での実用化はそう遠くはないと見られている。術前でも術後でも生存...


2012年7月
腫瘍内科医の第一人者である 渡辺亨さん 昨年9月、進行・再発乳がん治療に加わったアバスチン+パクリタキセル療法。 乳がんの進行を長く抑えることが明らかになった一方、今後重要になってくるのが副作用への対策だ。 治療を長く継続するためにもいかに副作用を抑えるか──チーム医療を実践している浜松オンコロジーセンターに話を伺った。 外来での投与が可能昨年から、乳がんの治療に ...


2012年6月
副作用の少ない TS-1に期待をよせる 佐藤温さん 以前は、腎機能が低下しているなどの身体的な衰えが見られる高齢者には化学療法は難しかった。しかし、TS-1の登場で高齢者にも化学療法が行われるようになっている。また、新たな治療薬にも期待が集まっているという。 高齢者の抗がん剤治療を難しくしている理由現在、胃がんの患者数はやや減少傾向にあるが、高齢者人口の増加に伴い、高齢者の胃がんは増えていくと...

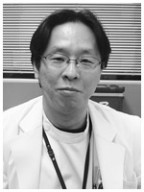
2012年6月
胃がんにおいても今後は 個別化治療が進むと話す 土井俊彦さん 昨年3月にハーセプチンが承認されたことで、胃がんも個別化治療の時代に入りました。分子標的薬の登場で、臨床現場にも大きな変化が見られています。 進行・再発がん治療はHER2検査が大前提昨今、さまざまながんの治療において、薬物療法はめざましい進歩を遂げています。 胃がんにおいても、2011年3月にハーセプチン(*)という薬が、適応拡大と...


2012年6月
胃や食道など消化器の 低侵襲手術を実践する 北川雄光さん 胃がんの低侵襲手術では、腹腔鏡下手術の臨床研究が進んでいる。例えば、1期の胃がんでは、開腹手術との比較が行われている。腹腔鏡下手術のメリット・デメリットは? 術中のセンチネルリンパ節生検は温存手術にどう生かせるのか?進行中の試験から見通せる現状をいち早く紹介する。 腹腔鏡下手術のさらなる進歩 [図1 胃の機能温存手術の種類] [...