医療ジャーナリスト・祢津加奈子の例 セカンドオピニオンが決めた悔いのない選択
冗談のつもりが真実だったとは

一昨年東京国際フォーラムで開かれた日本癌治療学会の会場
かくいう私も、がん患者の家族である。6年ほど前、連れ合いが末期の肺がんと診断された。
奇しくも私が京都で行われた日本癌治療学会の取材から帰った夜のことだ。連れ合いが「駅の階段を登るのも苦しくて、会社を休んじゃった。お腹に水が溜まっているような気がする」と訴えた。3日前に取材に出る時まで、連れ合いはいつもどおりに過ごしていた。私は「お腹に水って、がんなら末期よ」と笑った。冗談のつもりだった。それが、まさか真実を衝いていようとは……。
溜まっていたのは、腹水ではなく胸水だった。
「胸水からがん細胞が発見されました。原発巣は不明」
若い大学病院の医師は、顔を引きつらせながらそれだけを伝えた。原発巣がどこであれ、がんの末期であることは明らかだった。
がんは、早期に発見できれば治る可能性は高い。だが、早期発見じたいが難しいがんもある。肺がんの場合、今も6~7割は手術できない進行がんの状態で見つかっている。肺がん検診が生存率を向上させるかどうか、科学的な有効性は十分に証明されていない。連れ合いの場合、せきやタン、血痰など呼吸器系の異常を思わせる兆候も全く無かった。
生涯の大事であるからこそ、私は自分の口からまず真実を伝えたかった。
「僕ががんになったら、必ず言うんだよ。僕は平気だから」
常々そう語っていた連れ合いの言葉を頼りに、それから4日後、がんであることを告げた。その時は「そうか」と笑ってみせた連れ合いも、主治医から、ステージは4期、手術できない段階であると告げられた時には、さすがに「厳しいな」と漏らしていた。
治る方法があるのならば、どんなに厳しい治療でも耐えてみせる自信が彼にはあったようだ。
セカンドオピニオンが私の拠り所
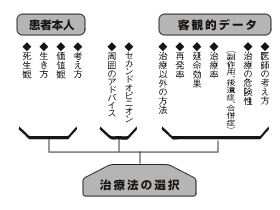
治療をどうするか。仕事がら、がん治療については多少の知識は持っているつもりだった。が、末期がんという現実の前には、それも全く役立たなかった。しかし、何とか気力をふり絞り、手元にあった専門医向けの雑誌を読み始めた。
医師からは、抗がん剤治療を勧められた。がんが進行すると、全身への効果を期待して抗がん剤が使われるのがふつうだ。
しかし、肺がんは抗がん剤で治るがんではない。
いくら抗がん剤の奏効率がよくても、それはがんが縮小する割合で、治るという意味ではないのである。肺がんは、抗がん剤が中程度に効くがんとされているが、期待できるのは延命効果、つまりどれだけ命を永らえさせることができるかである。

セカンドオピニオンを拠り所にする人が多くなった
しかも、連れ合いのがんは肺がんでも腺がんというタイプで、抗がん剤の反応はよくない。それでも専門誌を見直したのは、新しい治療法なり、参加できる臨床試験がないか、というすがるような思いからだった。少なくとも後悔しないだけの情報を自分で集めておきたかった。
しかし、手掛かりになるような記事はなかった。「抗がん剤による延命期間は1カ月ほどで、それも治療により苦しんでいる期間が延命期間になっているだけではないかという意見もあります」という専門医の絶望的な見解を確認しただけだった。
当時の私にはまだインターネットも身近な存在ではなく、一般向けのがんの専門誌もなければ、末期がんの治療まで踏み込んだ書籍もあまりなかった時代である。
私が考えたのは、抗がん剤治療の専門家にセカンドオピニオン、つまり主治医以外の医師の意見を求めることだった。実は、これが今でも私の拠り所なのである。
延命よりは、共に過ごす道を選んだ

抗がん剤治療。しかし、日本の病院にはその真の専門家が少ない
日本ではどの病院でも抗がん剤治療ぐらいは行っている。しかし、実際には抗がん剤に関する本当の専門家(腫瘍内科医)は少ない。その少ないが、熱心な化学療法の専門家に意見を求めることが一番確実で、早道ではないかと思ったのである。
早速取材で知り合った医師を訪ねると、抗がん剤治療の進歩を話してくださったあと、最後にこう語った。
「私のところにも、シスプラチン(抗がん剤)で1年間通院治療を受けた人もいますから」
だから、頑張って治療しましょう、という意味だったと思う。
しかし、その言葉を聞いて私は別の決断をしていた。抗がん剤の専門家である医師が、1年の通院治療例をわざわざ引き合いに出すということは、それが化学療法における最大効果であり、稀な例だろうと私は理解したのである。

相談者の考えとは裏腹に、別の決断をする
ことになった問題のシスプラチン
彼の命を救う手段は今の医療にはない。そう私は判断した。
だから連れ合いに抗がん剤治療を受けさせる気持ちにはなれなかった。わずかでも治る可能性があるとか、年単位の延命効果が期待できるというのならば、迷わず抗がん剤治療を受けていただろう。
しかし、数カ月の延命程度、それも効果があるかどうかもわからないとなれば、その治療のために、残り少ない時間の何分の1かをつぶしてしまうことを私は恐れたのである。
私たちは、残された時間を、できるだけ共に過ごす道を選んだ。しかし、それでも諦めたわけではなかった。なお奇跡を信じ、連れ合いの生命力にかけたのである。
私たちの選択に心残りはない
連れ合いが逝ったのは、診断から5カ月後だった。その間、二人で週末ごとに通って作った山のログハウスにも行き、一度だけだが連れ合いを家に連れて帰り、可愛がっていた犬の散歩もした。
腺がんなど肺の非小細胞がんを対象とした初の分子標的治療薬、イレッサの臨床試験が始まったのは、連れ合いの死から3年後のことだった。もう少し早ければという気持ちもないわけではない。しかし、それが強い心残りになっていないのは、やはりセカンドオピニオンのおかげである。
あの時の言葉があったからこそ、あの時点でできるかぎりのことはした、知らないがゆえに逃した治療はなかったと自信をもって言うことができるのである。その上で最後まで連れ合いと相談し、私たちらしい最後の時を過ごすことができた。私にとっては、それがせめてもの納得のしかただったのである。
私たちの場合、選択肢は限られていたとはいえ、数カ月でも延命効果を期待して抗がん剤治療を受けることもできた。ホスピスや往診を受けるという選択肢もある。がんの種類によっても選択肢は違ってくる。他の人たちは何を考え、どういう選択をしているのだろうか。



