にのさかクリニック 人と人とがつながっていく。それこそが在宅ホスピス
欧米に比べて少ない在宅死。もっと在宅で過ごすことの力に注目を!

最後の最後まで、自分らしくありたい。
こう願って、この「自分らしく、我が家で」というシリーズを進めているが、今回は福岡市郊外にある「にのさかクリニック」とそれを取り巻く人々の人間模様を描き出す。
そこには、人と人とのつながりがあり、それが在宅ホスピスの源動力になっているように見えた。
聞きたいけど、何を聞きたいかわからない
明るい部屋の中央におかれたベッドで寝ている女性患者に、在宅医のニノ坂保喜さんはこう尋ねた。
「なにか聞きたいことはないですか」
女性は天井を見上げたまま、つぶやくように言った。
「……聞きたいけど……何を聞きたいかわからない」
聞きたい気持ちと、本当のことを知る怖れで心が揺れているのだろう。スキルス胃がんが骨転移し、トイレに行くのもやっとの状態。残された時間は長くはない。夫は妻のために、本当のことは告げないつもりだった。厳しい状況であっても、冗談を言って場を明るくしようとする家族の温もりは伝わってくる。
医者にとっても厳しいケースに違いない。ニノ坂さんは告知を無理強いはしないが、嘘はつかないことを前提にしている。患者との間に嘘があると、信頼関係が築きにくいからだ。
「……むずかしいですね」
と、ニノ坂さんは次の患者宅に向かう車のなかでぽつりと言った。
こんな過度の緊張を強いられる訪問診療ばかりではない。次に行ったのは、90歳の軽い認知症のおばあちゃん宅。たまたま一昨日、30年ぶりに知人の男性が訪ねてきてくれたのだと言う。
「うれしくて、うれしくて、ゆうべはふとんの中で眠れんかったとですよ」
まるで昔の恋人が空から降ってきたかのように90歳のおばあちゃんが目を細めて語る「ロマンス」に救われる気がした。
病院死が突出する異常な状態の日本
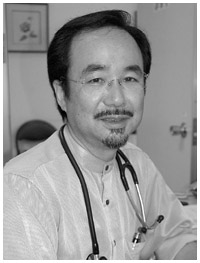
「にのさかクリニック」が開業したのは1998年3月。そのころの在宅患者は、
「ぎりぎりの状態になって病院から逃げ帰る人が多かった」
と、ニノ坂さんは言う。近年は身内のがん患者を見た経験などから、自らの意思を表明して自宅に帰る人が増えているという。もうひとつ大きな違いは、訪問看護ステーションなどの充実だ。
「福岡県には訪問看護ステーションが240くらいあり、そのうち夜間対応の可能なところが100程度あります。10年前には緩和ケアの技術や考え方をもっているところはごくわずかでしたが、今は患者側が選べるくらい多くなって、良くなければ変えることもできるんです」
こうした面での進歩がある一方で、「もう治療がないので出て行ってくれ」と、信じられないような言葉を使う医師もいまだにいるのだという。
「患者さんは、治らないとわかった後こそ大変な思いをして苦しむ。それをどうサポートするかが医療の大きな役目のひとつなんですが、事実上放り出されていることが多いのが現状です」
痛みの緩和に取り組む家庭医の存在が足りない。国内のがん死亡者数は年間約30万人。そのうち在宅で亡くなる人の数が諸外国に比べて圧倒的に少ないことをニノ坂さんは指摘する。
「イギリスやアメリカではがん患者でも25パーセント、全死亡者になると40~50パーセントが自宅で亡くなっています。日本には在宅死のはっきりした数字が無いんですが、緩和ケア病棟で亡くなられた方が3パーセント程度なので、おそらく95パーセントぐらいが充分な緩和ケアが受けられないまま病院で亡くなっている驚くべき状況なんです。これは、私たち医者の責任が大きいと言わざるを得ません」
バングラディシュを援助するNGOの代表


在宅医療に取り組んで10年。拠点となる「にのさかクリニック」は、福岡市郊外の雑居ビルの1階にある。待合室に入ると、壁に母子の写真とともに『特定非営利活動法人バングラディシュと手をつなぐ会』と書かれたポスターに目が行った。
「このNGOの代表を務めています。開業医は地域のヘルスケアで大きな役割を担っているのに、個人的なつき合いをもつ人は少ない。ボランティアでも、和太鼓でも何でもいいので地域のなかで人間的なつながりをもつことが、コミュニティケアの第1歩になると思っています」
ニノ坂さんが初めてバングラディシュに渡ったのは、現地で医療活動を行っていた旧友を訪ねた1989年のこと。その後、福岡市にもバングラ西部のカラムディ村に小学校を設立した「バングラディシュと手をつなぐ会」という団体があることを知る。92年にニノ坂さんが入会した後、医療保健分野にも活動の幅が広がり、95年には「母子保健センター」を募金で設立した。
このNGOの活動は、資金援助にとどまらない。現地の人たちの顔を見て意見交換する現地訪問の活動を行っている。2006年8月にも大学生4人を含む計7人で現地に渡った。若者らは瑞々しい感性で発展途上国の生活を直視し、人生が変わるほどの衝撃を受けて帰国している。
15回目のベテラン、ニノ坂さんも、必ず何かを学んでくる。
「行くたびに新たな発見があるんです。今回は現地スタッフから『トータルサポート』という言葉をよく耳にしました。妊婦や乳幼児の健康を守るには、家族構成や生活状態、ときには経済状態まで知る必要がある。それが生活全体を支えるトータルサポートにつながるわけですが、在宅ホスピスにおける『全人的ケア』の考え方とつながっている、と思いました」



