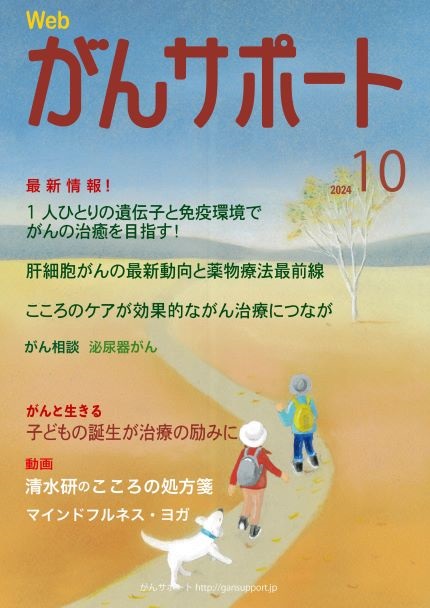妻と共にがんと闘った追憶の日々
君を夏の日にたとえようか 第22回
架矢 恭一郎さん(歯科医師)

顕と昂へ
君を夏の日にたとえようか。
いや、君の方がずっと美しく、おだやかだ。
――ウィリアム・シェイクスピア
ショッピングモールに連れて行ってほしい

恭子の闘病記録には、テレビでオリンピックが放映されていることと、右目が見えにくいことを気にした記載が数日あって、「6月26日(日)」という日付を打ったところで絶筆となっている。
私とのCメールのやり取りも、
「今日は点滴おやすみ? みんなお昼寝中♥」
「お休みだよ、チュッ」
「了解、チュッ。帰りはいつでもいいです」という6月25日が最後。
2016年6月26日。日曜日の夕刻、恭子はさっちゃんの誕生日のプレゼントを買いに連れて行ってほしいという。私たちの大好きなメゾソプラノ波多野睦美さんのCDを選ぶのは、私に任せられていた。つのだたかしさんのリュート伴奏で、2枚を選び、すでに手元に届いていた。波多野さんのソロでハープシコードとバス・ヴァイオルの加わったヘンリー・パーセルの歌曲集とイタリアのソプラノ、ロベルタ・マメリとのデュオアルバム『アリアンナの嘆き』を。
恭子は、フレーバーティを自分で選ぶから、近くのショッピングモールに連れて行ってほしいという。無茶な話だったが、命がけでも行くに決まっているから、2人で出かけた。日曜の夕刻であいにく混み合っていた。助手席の恭子に「眠っていなさい」と声を掛けると、すぐに目を閉じて寝息を立て始めた。やっと、駐車場が見つかって、よろよろと1人では歩けない恭子を引きずるようにして、紅茶店に辿り着く。
恭子は自分で選ぶ思考力も根気も体力もない。私がそっと選んで、「これでどう?」と尋ねると、「わからないから何でもいい」という。「じゃあこれにしよう。可愛らしいセットだよ。さっちゃん、きっと喜んでくれるよ」「うんうん」と恭子はうなずいている。
店の人には、それでも訳のわからないことを言いながら、愛想を振りまこうとしている。これが、命がけということなのだ……。
恭子はこの頃、牛乳を飲まなくなった。おっぱいに関するものはなんでも恨めしいのだ。見当識障害は日に日に、目に見えて進行している。自分は左目が見えにくくて、右のほうがよく見えるはずなのに、右が見えにくくなったとしきりに気にしながらいう。私は黙っている。恭子の頭蓋内で暴れている乳がん細胞が、視神経に悪さをしているのだとわかり切っていることだ。言ってあげることばも思いつかない。
緩和ケア病棟に入院

この2年間、私たちにとって何にもまして優先してきた恭子の延命とQOLを維持するための医学的治療がその色を急速に失った。無意味なものになった。その途端に医学の役割はスーっと消え去って、私たちとは無縁なものになってしまった。私たちは取り残される。
日本の医療は生きるための医療だ。脈のある患者のためだけのものだ。命と健康を守ることが医療の最重要課題とされているのだ。本当は違う! 『死すべき定め』を著した米国の外科医アトゥール・ガワンデがその著書のなかでこう述べている。
「何が医療者の仕事なのかについて私たちは誤った認識をずっとひきずっている。自分たちの仕事は健康と寿命を増進することだと私たちは考えている。しかし、本当はもっと大きなことだ。人が幸福でいられるようにすることだ。幸福でいるとは人が生きたいと望む理由のことである。こうした理由は、終末期や要介護状態になったときだけではなく、一生を通じて必要なものだ」と。「よりよく逝くために、医者は患者とじっくり時間を掛けて〝厳しい会話〟をして、真正面から向き合わなければならない」とも。
終末期に患者から離れなくてはならないのが、日本の先進的な治療を行っている大きな病院の宿命だと感じている。医療者を責めてはいけない。大病院で先進的な治療をされている多くの医者は、キャパシティオーバーの超人的なスケジュールで莫大な人数の患者を診ているのだ。常に最善を尽くして。
だが、1人ひとりの患者に割ける時間が決定的に足りない。誤解を恐れずに言えば、どうしても誰が悪いのかと突き詰めて言えば、より高度な医療を求めて大病院にばかり集中する我々患者が悪いのだ、恐らく……。
6月29日、水曜日。歯科医院での月に1度のミーティングを緊急に中止して、恭子を緩和ケア病棟に入院させるときだと感じていることを病院長であり緩和ケアを中心的に診ておられる中谷先生に伝える。
「なるべく意向に沿うことができるように最善を尽くさせていただきますが、数日から1週間ほどはお待ちいただかないといけないと思います」と言われたが、恭子は翌日、6月30日に緩和ケア病棟に入院させてもらえた。
第六章 水頭症・髄膜播種
16.緩和ケア病棟

私たちには分不相応かも知れないが、緩和ケア病棟の一番広い部屋に入れてもらった。恭子にしてやれる残された数少ないことだから。のちに恭子はこの部屋が気に入っていると、何度か言ってくれた。それはそうだろう、台所も風呂場も広くとってあって、携帯で写しながら長男に見せたら、自分のアパートより広いといっていた。大方の独身の若者のそれに比べても、広くて明るくて清潔で立派だと思う。
「ここは、恭子とパパの別荘なんだよ」と、何度も恭子にいう。
治療のための通院や谷本先生との約束をしきりに気にするが、「いいんだよ。谷本先生たちにもちゃんと連絡してあるから心配しなくていいよ、恭子。ゆっくり休みなさい」
私も誤解していた。緩和ケア病棟に入院しながらでも治療の継続は可能だろうと、高をくくっていたのだ。中谷先生が、「入院されたら、他の医療機関への通院治療はできなくなります」と説明された。通院治療ができることと、入院しなくてはならないこととは、同時に行われては矛盾するのだろう。
7月1日、金曜日。耳の遠い父の代わりに恭子の母親と私が中谷先生の部屋に呼ばれて、緩和ケアの説明を受けた。曰く、「無理に長びかせて生きさせることもしませんし、短くもしません。ただ、患者さんの苦痛は最大限の努力をして取り除かせていただきます」
まことに厳しい話である。これが、医者のすべき、厳しい話なのだと思う。
「気になったことは、何でもおっしゃってください。出来る限りのことは、何でもさせていただきます」
母は、まだそのこころで恭子の病状を受け止められない。
「飛行機が徐々に着陸するようにゆっくりと終わりに向かって高度を下げていきますが、途中、何かのトラブルで飛行機がストンと墜落してしまうこともあるかも知れません」と中谷先生はいわれた。