矢津内科消化器科クリニック コミュニティケアの精神を地域に広めていきたい
心のつながりが在宅ホスピスを支える
「人と人とのつながり、世代間のつながり、地域のつながりがよい終末期を迎えられるカギだと思います」こう話すのは「矢津内科消化器科クリニック」院長の矢津剛さん。政令指定都市・北九州市の南、福岡県行橋市で在宅ホスピスを行いながら、矢津さんはこの「つながり」を模索してきた。
「北部九州ホスピスケアの会」の設立
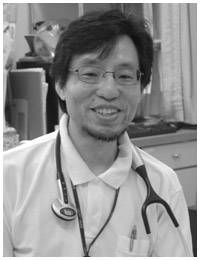
在宅ホスピスは医療者だけでなく、患者さんや地域住民の理解や協力があってはじめて満足のいく形に近づけるといえる。矢津さんが開業医となった1996年から目指してきたのも、地域の人たちを巻き込んだ「コミュニティケアの実践」だった。
1997年には自らが発起人となって「北部九州ホスピスケアの会」を設立。医療福祉関係者やがん患者さん、一般市民などとともに、毎月の定例会や講演会、在宅ホスピス講座などを開いてきた。
「ホスピスや在宅緩和ケアについてお互いに学びつつ、情報発信していこうというものです。できれば元気なうちから予備知識を得てもらいたいと思ったんです」
そうした活動を続けていた2000年、ホスピス医として知られる山崎章郎さん主催の「ニュージーランドホスピス視察ツアー」に同行した。
「それまで日本の緩和ケア病棟のイメージしかなかったため、大きなカルチャーショックを受けました」
ニュージーランドでは在宅ホスピスが中心。ホスピス病棟は患者さんや家族のレスパイト(一時休憩)が目的のあくまでも補完的な施設だった。
「ひと息の村」の誕生

視察から7年あまり。2006年5月に在宅ホスピスの支援拠点「ひと息の村」を誕生させた。当初設立を目指していた国の認可を受けた緩和ケア病棟とは異なるものになったのも、ニュージーランド視察が原点になった。 「ひと息の村」はその名のとおり、在宅生活を送る患者さんや家族に「ちょっとひと息」ついてもらうためのレスパイト施設と、在宅支援のための拠点である。
山崎章郎さんが東京都小平市で取り組む「ケアタウン小平」とほぼコンセプトは同じ。2人で相談したわけではなく、
「たまたま同じところへ行きついたんです」
と、矢津さんは笑顔で言う。
福祉の世界で注目を浴びる「小規模多機能」と同じで、訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所を兼ね備えた複合施設の医療版といえるだろう。
1階には訪問看護・介護ステーションと、デイサービスルームなどを設置。2階にはホテルのシングルルーム感覚の「在宅ホスピス支援ハウス」11室(1室のみツイン)などがある。初回に入居一時金7万2000円が必要で、あとは月額の家賃5万6000円(1人部屋・管理費込み)か、週単位3万円での利用もできる。
完全看護の医療施設や、豪華なケア付き高齢者マンションとは異なり、通常の訪問診療や訪問看護を行う民家と同じ扱い。在宅での症状コントロールが難しくなったときや、家族が介護疲れしたときなどのためのレスパイトケアが目的なのだ。
「これまでも在宅ホスピスで7割の方は在宅で看取ることができましたが、残り3割ぐらいの方は家族の介護疲れなどからやむなく入院にいたってしまう。ご本人も家族も入院を望まれない方々のためレスパイト施設なんです」
在宅生活を支える家族も、介護疲れは当然ある。また患者さんにとっても、いつでも受け入れてもらえる施設があれば、在宅生活を送りやすくなるはずだ。
様々なボランティア活動に着手



「ひと息の村」のユニークさは、1階の正面玄関わきに「北部九州ホスピスケアの会」のボランティアルームがあることだ。
2007年で10周年を迎える同会が2003年にNPO(特定非営利活動)法人となった際、理事長に推挙されたのが森口順司さん。森口さんは、10年前の最初のボランティア講座のときに聞いた言葉が今も忘れられないという。
「矢津先生が『ボランティアというのは、自分ができるときに、できることをやっていただければそれでいいんです』とおっしゃってくださり、気分が楽になったことを覚えています。それなら私でもできるのではないか、と思ったんです」
森口さんは製薬会社に勤務時代から「産業カウンセリング」の資格を取られるような篤実なお人柄。5年前に定年を迎えた後、会の中心的役割を果たしている。
森口さんの提案ではじまったのが「男の料理教室」だ。
「グリーフケアの一環としてやりはじめたんです。最初は毎年行う定例会の行事の1つだったんですが、要望が多くて2007年は結局3回になる予定です」
喪失の深い哀しみを癒すケアを「グリーフケア」と呼ぶが、この名称に抵抗がある人も少なくない。配偶者の死別後の悲嘆期間が長期に及ぶのは男性のほうに多いとされるが、その理由のひとつに男性が引きこもりになることが挙げられる。料理という目的があれば、一石二鳥のグリーフケアになるだろう。
もちろん成功例ばかりではない。
03年には患者さんや家族の電話相談を受ける「傾聴ダイヤル」をスタートし、翌年には行橋駅前の商店街の一角に「ホスピスショップ」をオープン。だが、どちらもいまは頓挫している。
ショップの発案者である矢津さんはきっかけをこう語る。
「その前年に行ったイギリスでは、ホスピスショップが地域の情報発信基地の役割を果たしていたんです。基本はリサイクルショップなんですが、税制で優遇されているうえ、資金集めのための宝くじなども実施しています。ホスピスというむずかしいテーマを、街角の美しいショーウィンドウのなかにさりげなく持ち込む手法がいいなと思ったんです」
しかし、日本初と思われるこの試みも、時期尚早だったのか。会の世話人らが交代で店番をしながら住民との交流を図ったが、借地にホテル建設がもちあがり、やむなく閉鎖した。
「ホスピスショップは上手く行きませんでしたが、遺族会などがそれ以上の伝達効果があることがわかったんです」
在宅ホスピスで看取った患者さんの遺族らが自主的に『星の会』という遺族会を結成。年3回ほど、食事会など自然な集まりを開けるようになり、在宅ホスピスのすばらしさを地域に対して発信しはじめてくれたのだ。
「『コミュニティケア』は10年、20年のスパンで考え、じっくり広めていくしかないんですね」
失敗を恐れないチャレンジャーの矢津さんが、たどり着いた現在の結論だ。



