子宮頸がんステージⅢと診断され、子宮全摘手術を受けたフリーランス・パブリシストが綴る葛藤の日々
「必ずまた、戻ってくるから」 第2回
橘 ハコ さん

<病歴> 2013年3月、子宮頸がんのステージⅠと診断される。転院後の詳細な検査により、右腸骨付近のリンパ節に転移が認められステージⅢと確定。同年6月に準広汎子宮全摘出術を受ける。病理検査の結果、極めて微小な膣がんも確認された。同じく7月末~9月上旬まで、放射線化学療法を実施。治療の後遺症で左脚に麻痺が残り(現在はほとんど見た目にはわからないほどに回復)、10月には1人暮らしを再開し、後遺症で日常生活も必死な状態のまま11月からフルタイムでの仕事をスタートする。
麻痺の残った左脚に極めて軽度のリンパ浮腫発症が見られ、開腹手術の影響で腸が過敏になり、サブイレウス、大腸憩室炎など腹部の疾患に度々悩まされる。2018年現在、経過観察を重ね、今のところ再発はなし
転院を選び、東京をあとにする
【友人Iさんからのメールの引用】「私も調べましたが、確かに子宮頸がんの手術の後遺症はつらいものがあるようですね。私の場合は最初に医師から「手術は出来ません。放射線と抗がん薬の併用になります」と言われたので悩むことがありませんでした。
私は医師ではないので、どちらがいいか判断出来ませんが、いただいたメールで気になったのが医師のコメントです。感じられるのは「手術と決めたのに何を今さら躊躇するのか」という医師の本音です。
この医師は手術が専門なので、放射線になると別の医師になるんですよね。執刀数を増やしたいわけではないでしょうが、「手術の段取りをしたのに」という感じがどうも嫌なのです。それは医師の都合であって患者の都合ではありません。
有名な医師とのことですから失敗例は少ないのでしょうが、何をもって成功と失敗を分けているのでしょうか? 単に5年生き延びたら成功、それまでに死んだら失敗、生存後どんなに後遺症に苦しもうと「成功」だから関係ないとしたら、名医の名声なんて意味がありません。
私も手術を肯定したり否定したりしていい加減ですが、手術をする医師の気持ちで考えると「疑わしきは切除」になってしまうのではないかと今回のメールで思い始めました。取り残したがんが再発すると失敗になるのですから。本当にいい医師なら患者目線=患者の気持ちで応答できるはずです。それを自分=医師の都合で応対しているように思えて嫌なのです。
手術を勧める理由として、「病理に回してがんかどうか分かることがメリット」なんて医師の自己満足でしかなく、患者への負担を考慮してないようにしか聞こえないのです。
私は「首のリンパ腺に転移」との診断で広域放射線照射と抗がん薬治療でした。検査では遠隔転移なしとの診断でしたが、見落としもあるので抗がん薬でその懸念に対処するとも言っていました。
医師はどうしても考えられる懸念に対しては対処しないわけにはいかないんですね。一方で人間の治癒力はかなりのものがありますから、放射線で傷んでも時間をかければ回復する可能性があります(私も自分の唾液腺の復活を待っています)。
残っていれば回復もしますが、切除してしまっては戻りませんね。残すと転移・再発の懸念もありますが、食事や生活に注意して体質改善すれば、万一残ったがん細胞の痕跡も暴発させずに過ごせるのではないでしょうか。
先日、帝王切開出産の例を出しましたが、正常な臓器を取るわけではない帝王切開と、疑いのある器官をすべて取ってしまう子宮全摘ではまったく違うということに考えが及ばなかったことを恥ずかしく思います。
私は手術をしませんでしたが、入院していた耳鼻科病棟には声帯を切除して補助器具でかろうじて会話している患者がいましたので、ああなったらキツイなとは思っていました。
その一方で医師から「放射線で味覚を失う」と言われましたが、それを拒否することは出来ませんでした。幸いにも味覚は残っており心配だけで終わりました。
はっきりしていたのは、妻と未成年の息子2人を抱えて今死ぬわけにはいかない、声を失おうと味覚を失おうとがんに勝って生き延びるということだけでした。
声帯を失っても活躍した人に政治家の与謝野馨さんがいました。私が声を失って今のように回復できたかというと自信はありませんが、負けず嫌いなので何とかしたんじゃないかと思います。
今でも20年近く糖尿病でインスリン自己注射をしながら放射線の後遺症で、口の渇き、首の痛み、顎の硬化などいろいろ抱えていますが、ハンディとは思っていません。生きていくうえで最も大切なのは「気持ち」で、それを維持する上で最低限のQOL(生活の質)を保つというのは、検査の数値などでは現れないけど重要なポイントだと思います。
私のように選択の余地がない場合は悩む必要もありませんが、なまじ選択の余地があり、治癒率が同じだというだけに本当に悩ましいですね。
でもその「治癒率」なるものがどのように算出されているか、治癒率以外に治療後のQOLに影響を及ぼす因子はないか、などを考えて判断されるべきだと思います」【友人Iさんからのメールの引用終わり】
「がん体験」はきわめて個人的な物語だと知る
この時が「どうせ誰にも頼れないのだ、独りきりなのだ」という思いと無意識に対決した最初の出来事だったと思う。当たり障りなく親しかった友人に、私のがんを共有させたのだった。
世間から見れば同じがん体験者かもしれなくても、性、年齢、疾患部位、そして何より違う人生を生きていればがん体験はまったく人により百人百様だった。がんを生きる人の数だけそれぞれのがんと自己の物語が生まれる。
そうして彼は私の物語を充分にキャッチしてくれた。彼はその後も手術当日に絵葉書を送ってくれたり、遠く関西から仕事を終えてお見舞いに駆けつけてくれたり、私の心をいつも奮い立たせてくれている。
とにかく時間が迫っていた。4月も末の診察時には手術の日程も決まっていると言われるなか、幸か不幸か順調にPET-CT検査やMRI検査も進行していた。
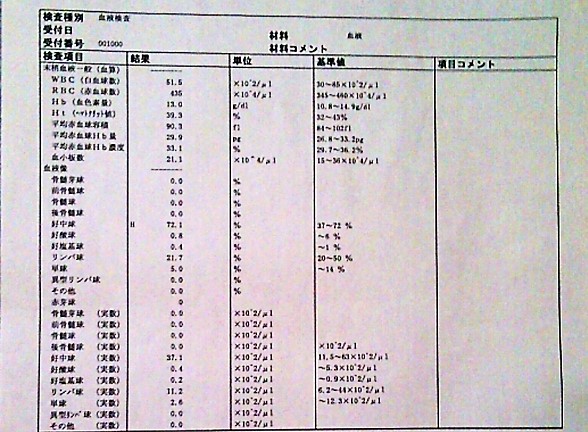
孤独感を救った、姉からの電話
その間、私のなかでは調べが進むほどに手術をしなくて済むのなら放射線治療を選択したいという気持ちが強くなっていた。患者は私なのだ、その私が生きていくための治療を選ぶべきなのだ、そういう患者としての自覚が生まれてきたのだった。それまでの私は恥ずかしいほどに、医師目線で己の病を眺めていたのだった。
問題は、手術を決定事項として伝えていた家族への説明だった。がんという特殊な病に加え、子宮頸がんという女性特有の疾患、それらすべてを初めて聞くような家族に、最新の医療データでは手術だけが有効な治療ではないことを伝えるのは想像するだけでしんどかった。
手術ですべて切除すれば、早期がんなら延命根治が充分可能だと、これまで伝えてきたし、私の親の世代はもともと手術が最良だという考え方があった。そのため、放射線治療という選択肢を提示することが、私の生存を賭けた治療への諦めと取られかねなかったのだ。
そんな折、乳幼児を抱え自分の時間すらままならない姉から深夜に電話があった。
「何だろう」と思っていると姉はこの病について、治療法について自ら調べてくれていた。そして「自分ならどうするのか」という観点で真剣に考えてくれたのだと知らされ、本当に感激して胸が熱くなった。
そして姉は「誰が何て言ってもあなたの身体なんだから、しっかりしっかり考えていいんだよ。手術の締め切りのためじゃなく、納得できるまで時間をかけていいんだよ。それでね、そのうえで私ならやっぱり放射線を選ぶ」と姉は言った。
調べていれば手術の後遺症のつらさはすぐにわかる。手術が悪いというのではなくやはり身体に大きな負担がかかるなら、まだ40にもなっていない私のこれからの人生を考えたとき、より負担の少ない治療法を選択して欲しい。その姉の言葉に強く押され、どの治療法を選ぶか以上に、姉が我がことのように考えてくれていたという事実が私の孤独感を本当に救ってくれた。



