『肝癌診療ガイドライン』をわかりやすく解説する
肝臓がん治療で世界のトップに立つ日本~さらに高い治療成績が期待されている
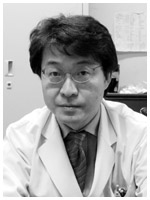
東大医学部付属病院
肝胆膵・人工臓器移植外科講師の
今村宏さん
日本は、肝臓がんの診断・治療では、世界でもトップレベルにあり、2005年には『肝癌診療ガイドライン』も作成されました。
ガイドラインはエビデンス(根拠)を元に現状での標準的な診断や治療法を示したもの。これを患者さんの側からどう解釈すればいいのか、肝臓がん治療と研究の最前線で活躍し、ガイドラインの研究協力者でもある東京大学医学部肝胆膵外科講師の今村宏さんに聞きました。
画像診断がスタンダード

肝臓がん(肝細胞がん)の大半は、B型、C型の肝炎ウイルス感染によって起こります。したがって、ハイリスク者に的を絞って検査ができるのが肝臓がんの大きな特徴です。言い換えれば、危険因子を抱えた人は定期的な検査を受けることで、適切な時期に治療することが可能なのです。「ただ、肝細胞がんのスクリーニングが早期発見とがん死の軽減につながったかという点に関しての研究では、今のところ否定的な報告のほうが多いということも事実なのだと知っておいてください」(今村さん)
「危険の程度は、たとえばBとCの混合感染で上がる、Cではアルコール摂取が危険因子となる、HCVウィルスRNA量、HBV DNA量の高いほうが危険性が高い、あるいはGOT/GPTの高い群、等言われています」(今村さん)
がんの検査というと、大変な検査を想像する人もいると思いますが、今村さんによると、肝臓がんは画像診断がゴールドスタンダード。
現状では、「3phaseダイナミックCT(単純、動脈相、門脈相または平行相)か、これに匹敵するMRI(磁気共鳴診断装置)が診断の中心になる」そうです。ダイナミックCTは、静脈に造影剤を注入して肝臓のCTを撮影します 肝臓は門脈から70パーセント、動脈から30パーセントの血流を受けていますが、古典的肝細胞がんは動脈のみから血液を供給されているので、肝細胞がんはCTの動脈相で濃染され、逆に門脈相で周囲の肝実質に比較して造影されない、という特徴がありこれで診断します。
このCTか、同等のレベルのMRIを行えば、ほとんどの肝臓がんは確定診断、つまりがんと確定することができます。どちらがより優れているかはまだエビデンスがないそうです。
これに対して、超音波検査(以下、エコー)は、腹部に端子をあてるだけで検査ができるので、手軽ですぐに結果がわかる、繰り返しできるなどが利点です。反面、「見えない部位があり、検査している医師にしか病巣の状態がわからない」のが難点。結果を共有して検討することが難しいのです。
最近では造影剤を利用したより精度の高いエコーも現れはじめてはいますが、現状ではエコーで経過を観察して異常があればCTかMRIの検査を行う、あるいはCTかMRIの検査と一緒に行うといった補助的な使い方が一般的です。エコーとCT/MRIは相補的な関係だといえるのです。
一方、検査技術が進歩して、専門家の間では、肝臓の動脈に造影剤を流しながらCTをとるCTAP(経動脈性門脈造影下コンピュータ断層撮影)のほうがより精度の高い検査ができるのではないか、という意見も出ているそうです。しかし、ここで問題になるのが、肝臓がんの性質なのです。
早期がんは治療しないで経過をみる
早期がんが見つかったら、さっさと取ってしまいたいと思うのがふつうでしょう。他のがんでは、確かにそのとおり治療が行われ、成果もあげています。大腸や胃などでのがんでは早期がんといってもそれは胃壁や腸壁の比較的浅いところにとどまるという意味で進行していないという意味で、がん細胞の性質そのものは進行がんのそれと同じようなものであると考えられます。
ところが、肝臓がんは違うのです。今村さんによると、肝臓がんは典型的な多段階発がんの過程をたどるといいます。
多段階発がんとは、簡単にいえばいくつもの遺伝子変異が積み重なって、細胞がしだいに悪性化、がんになっていくという過程です。
肝臓がんの場合、まずB型やC型の慢性肝炎や肝硬変など、非常にがんが発生しやすい土壌があります。ここから「前がん状態」ともいうべき異常が発生、遺伝子の変異が進んでがんの性質が少しずつ出てきた状態が早期がんです。そしてしだいに悪性度を増し、転移浸潤するような性格を持ったのが古典的ながん、つまり本物のがんです。
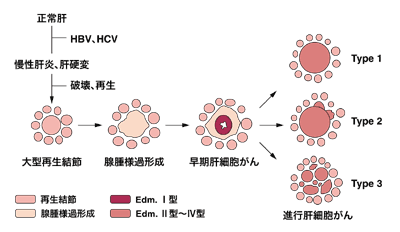
肝細胞がんの多段階発がんの過程
ここで問題になるのが、「どこから治療をすべきか」なのです。
今村さんは、「1個がんができて、それをとれば終わり、もうがんが発生しないというのならば、早く取ってしまいます。でも、肝臓がんはそういうがんではないのです」と語っています。肝臓がんには、さまざまな治療法がありますが、肝臓を丸ごと摘出して取り替えてしまう肝移植以外は、どの治療を行っても「がんになりやすい土壌」はそのままです。残念ながら、肝臓がんを切除しても「2年で5割、5年で8割が再発する」のが現実なのです。つまり、ひとつとってもまたできる可能性がきわめて高いのです。
そうであれば、「本当にがんになるかわからない、がんかどうかもわからない状態で摘出しても意味がない」というのが、基本的な考え方なのです。2センチ以下の早期がんはほとんどがんといってもまだがんらしい性質に乏しく、アメリカではがんの範疇にも入らない段階(高度異型)です。一般的には転移も起こさず、急に増大することもないとされています。一方で、治療はいずれの方法でも決して簡単なものではありません。
こういう「早期がん」の画像上の特徴は、一般に2センチ以下で、かつCT/MRI(あるいは造影エコー)の動脈相で腫瘤の濃染がない、ということです。そこで、2センチ以下の早期濃染のない小さながんはすぐに治療をしないで、定期的な検査を繰り返して経過を観察するというのが、基本的な方針です。早期がんは、経過観察中大きさが不変で、その間に他の部位に治療の対象となる古典的肝細胞がんができてくることもままあります。
「あやしい腫瘍の段階では治療はしない、大きくなったり性質が変わって古典的ながんになった時に治療を開始する」というのが、肝臓がんの治療戦略です。そして、2~3センチ以上になると古典的がんが多くなってくるそうです。
こうした肝臓がんの性質からみると、「CTAPを組み合わせてより精度の高い検査ができたとしても、はっきりがんとわかった時点で治療が始まるのですから、ダイナミックCTで見つかった段階で十分なのです。
その意味でCTAPは必要ないというのが、私の意見です」と今村さん。肝臓がんの場合、検査の感度が高く、早く異常が見つかるほど良いというわけではないのです。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肝細胞がん薬物療法最前線 進行期でも治療法の組合せで治癒を狙える可能性が!
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法



