渡辺亨チームが医療サポートする:肝臓がん編
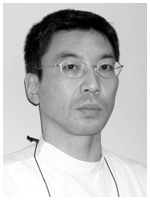
サポート医師・石井 浩
国立がん研究センター東病院
肝胆膵内科医長
いしい ひろし
1960年生まれ。
86年千葉大学医学部卒業後、同大学病院、清水厚生病院にて研修。
90年千葉大学第一内科、
国立横浜東病院を経て92年より国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科医員。
98年千葉社会保険病院消化器診断部長、
01年より国立がん研究センター東病院勤務。
02年より現職。
専門は原発性肝臓がん、胆道がん、膵がんの非手術療法
C型慢性肝炎発見から10年、肝臓がんを発症
| 川上裕輔さんの経過 | |
| 1968年 | 交通事故に遭い輸血を受ける。 |
| 1988年 | 検診から肝機能異常が発覚。「非A非B型肝炎かもしれない」といわれる。 |
| 2000年 | 疲れやすさ、食欲不振、よく足がつる、などの自覚症状あり。 |
| 2001年 12月5日 | 総合病院内科を受診。「すでに肝硬変に移行している可能性あり」と指摘される。インターフェロン+リバビリン併用療法を受ける目的で超音波検査を受ける。5cmの肝臓がんが見つかる。 |
交通事故のけがで輸血を受けた経験のある川上裕輔さん(65)は、1988年に「非A非B型肝炎の疑い」を指摘されていたが、90年にC型肝炎とわかる。
その10年後に症状が現れ始め、がん専門病院を受診すると肝臓がんが見つかった。
川上さんはあまり予後の良くない、このやっかいながんとどう取り組んでいくのだろうか。
「非A非B型肝炎の疑いあり」と言われていた
2005年春、Tがんセンターのホスピス病棟の窓から眼下の風景に目をやりながら、川上裕輔さん(仮名・65歳)は、そばにいる妻の悦子さんにこう語りかけた。
「我ながらよくここまでやってきたと思うよ。でも、今から考えると、月日の流れは本当に早かったなあ」
川上さんは、38年間にわたって電機関連会社に営業マンとして勤務していた。身長177センチと大柄で、若い頃は会社の野球部に所属するスポーツマンであり、病気らしい病気もしたことがなかった。また、仕事柄得意先と酒の付き合いも多く、ウイスキーボトル半分を平気で飲む酒豪でもあった。
1968年10月、道路わきをジョギング中だった当事28歳の川上さんは、車に接触されて弾き飛ばされ、コンクリート塀に激突した。足の動脈を切断したため大量に出血し、加害者に運び込まれた病院で輸血を受けている。しかし、裂傷だけで骨折もなく、1週間で退院、その翌日から職場復帰した。
「あの輸血でC型肝炎(*1)ウイルスに感染したのだとしたら、俺の肝がんももとはといえばあそこから始まったんだよな。でも、お前に感染させていなくて本当によかったと思っているよ」
悦子さんは黙ってうなずいた。交通事故に遭った翌年、川上さんは悦子さんと結婚、千葉市に住み、1男1女をもうけている。
1988年4月、川上さんは社内の検診で、「肝機能に異常があります。精密検査を受けたほうがいい(*2肝機能の検査)」と指摘された。しかし、まったく自覚症状はないし、健康情報に詳しい同僚に聞くと「肝機能異常など、誰にでも起こることだ。すぐに命に関わるようなことはないだろう」などといわれていたのである。
それでも、やはり肝臓のことが気になって、夏になってから、川上家のホームドクターである最寄のY内科クリニックを受診し、採血検査を受けた。検査の結果、当時60代のY院長は、「確かにあんまり肝臓の数字がよくありませんな。非A非B型肝炎といわれているものかもしれません。しばらくは月に1回チェックしましょう」と言い、小柴胡湯(*3)という漢方薬を処方した。
もともととくに自覚症状もなかった川上さんは、小柴胡湯をのみ始めると、ますます快調に感じられるようになる。
疲れやすさと食欲減退が現れる
1991年、川上さんは風邪を引いたために、久しぶりにYクリニックを訪れた。すると、Y院長はカルテを見ながら、「その後、肝臓の具合はいかがですか?」と聞く。川上さんは、「検診で肝機能が異常だといわれてますが、とくに自分では悪いところがないので放っています」と答えると、「もしかすると最近話題になっているC型肝炎だったかもしれません。調べてみましょう」といって採血をしたのである(*4肝炎ウイルスの検査)。
そして、1週間後、川上さんはこの検査の結果を聞きに行った。すると、Y院長は「残念ながら、やはりC型肝炎でした。慢性肝炎になっています」と告げ、今度はウルソというのみ薬を処方し、「これでまた、月に1回検査をしながら、様子をみてみましょう」と言ったのである(*5ウイルス肝炎の治療薬)。
川上さんはその当時のことをこう振り返る。
「あの時点ではまだC型肝炎ウイルスをやっつける薬もなかったのだから、結局俺はこうなる運命だったのかもしれない。しかし、肝臓の専門医に診てもらえばがんの危険性もわかっていたかもしれないし、何か早めに手を打ってもらえたかもしれない。Y先生はずっと血液検査しかしてくれなかった。しかし、専門医なら超音波検査もしてもらえたはずだから、こんなことにはならなかったかもしれないな」
今、ホスピス病棟で、川上さんは少々悔しい思いをしている。
91年にC型肝炎と診断されたあとも、川上さんには肝炎の自覚症状はまったくなかった。再びYクリニックへの通院も中断し、ウルソものまなくなってしまったのである。
そして、それから9年経った2000年、還暦を迎えた川上さんは時々、「なんだか最近疲れるな」と漏らすようになっていた。食欲不振が続き、10年前より10キロ以上やせて体重は60キロそこそことなっている。そのうえよく足がつるという症状も現れている(*6肝炎の症状)。
川上さんは、「そろそろ無理が利かない年になったのかなあ」と考え、酒は控えるようにした。
5センチ大の肝臓がんを発見
2001年3月、川上さんは38年間にわたって勤め上げた会社を定年退職した。ところが、毎日家でゴロゴロするようになっても、川上さんは少しも体が楽になったような気がしなかった。異常な疲労感がとれず、右肩に軽い違和感が生じている(*7肝硬変・肝臓がんの症状)。せっかく陶芸教室に入会を申し込んでおきながら、2カ月も通うともう気力が続かず行かなくなってしまった。
その年の暮れになって、川上さんは「一度大きな病院で診てもらおう」と最寄のG総合病院内科を受診した。さすがに「この具合の悪さは病気のためだ」と自覚したのである。
川上さんは、初めて会ったE医師に、現在の自覚症状と10年前にC型肝炎と診断されたことを話した。E医師は川上さんの血液検査結果を見ると、「血小板が減っているようですね。すでに肝硬変に移行している可能性があります」と話したのである。肝硬変という言葉はよく聞くが、それがどんな病気なのか川上さんにはよくわからない。
「肝硬変は肝臓がんに進行しやすい病気です。発がんを抑えるために、今度保険承認されたばかりのインターフェロンにリバビリンというお薬の併用療法(*8)をお勧めします」
「えっ、そんなに重い病気だったんですか?」
川上さんは、「がん」という言葉を聞いてドキッとした。ここで初めて自分の状態の深刻さを思い知ったのである。呆然としながら、E医師にうながされるまま、超音波検査(*9)の診察台に乗る。検査後、診察室に戻ると、医師は困ったような顔をして川上さんに言った。
「肝臓に5センチの腫瘍があります。肝細胞がん(*10)が強く疑われます。CTやMRIで詳しい検査が必要ですね」
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術
- 肝細胞がん薬物療法最前線 進行期でも治療法の組合せで治癒を狙える可能性が!
- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された
- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)
- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法
- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望
- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント
- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法



