「より多く」から「より適量」へ発想の転換をして、延命をはかった療法の最新成果 がん休眠療法10年の軌跡

金沢大学医学部付属病院
腫瘍外科助教授
高橋豊さん
たかはし ゆたか
1955年生まれ。金沢大学医学部卒。
85年に金沢大学がん研究所外科助手、87年に国立がん研究センター研修医(肺がん)となる。
90年に金沢大学がん研究所外科講師、93年に同、助教授となる。
94年にテキサス大学M.D.アンダーソンがんセンターにて転移の研究を行う。
96年にがん休眠療法を提唱、02年にテキサス大学M.D.アンダーソンがん研究所キャンサー・バイオロジーの客員准教授となる。
現在、金沢大学医学部付属病院腫瘍外科助教授。
[抗がん剤治療の現状]
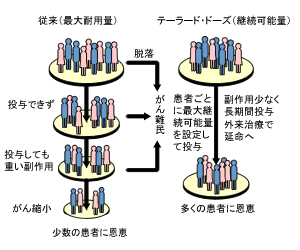
[従来の抗がん剤治療とテーラード・ドーズ化学療法の違い]
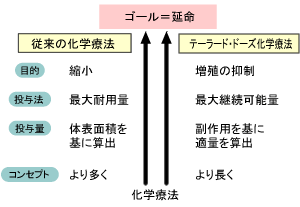
金沢大学医学部付属病院腫瘍外科助教授の高橋豊さんは、1995年、米国の国立がん研究所発行のがん専門雑誌『JNCI』に「縮小なき延命」という新しい考え方を打ち出し、これに基づく「がん休眠療法」(トゥモー・ドーマンシー・セラピー)を発表した。当時このがん休眠療法は、従来の「縮小なくして延命なし」という抗がん剤治療の常識を覆す、斬新かつ革新的な治療方針(戦略)だった。
その内容は、手術不可能な進行・再発がんに対し、がんの縮小を目的に抗がん剤を限界の量まで使っても生存期間を長く延長させることはできず、がんの増殖を抑えることを目的に抗がん剤を少量ずつ継続して用いたほうが生存期間は長くなる――という理論であった。しかし、発表当初、「縮小なき延命」を実現するためにどのような抗がん剤治療を行ったらよいのか、具体的な戦術が十分とは言えなかったようだ。さまざまな批判・非難を浴びた。
そんな中で、高橋さんは、がん休眠療法という治療方針(戦略)に基づいて、「テーラード・ドーズ化学療法(個別化最大継続可能量による抗がん剤治療)」と名付けた治療方法(戦術)を開発した。この療法は飲酒の適量には個人差があるように、抗がん剤の適量も患者1人ひとりで遺伝子学的に個人差があること、抗がん剤による副作用を軽い状態(グレード1~2以下)に止めて長く継続することが延命につながる――という科学的なデータをもとに考案されたものだ。このテーラード・ドーズ療法は、従来の抗がん剤治療に疑問を抱くたくさんの医師から賛同と共感を得た。
その結果、臨床試験(治療の有用性を評価するために患者を対象にした計画的な試験)を行うまでになり、現在、進行・再発胃がんを対象に、世界初のテーラード・ドーズ化学療法による臨床試験(全国50施設)が進行中である。米国国立がん研究所の雑誌に発表してから10年目の今年、がん休眠療法は再び大きな関心を集めている。
腫瘍の大きさが半分になっても延命にはつながらない
[抗がん剤投与による腫瘍の大きさの変化]
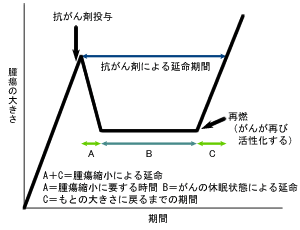
高橋さんは消化器外科医で、研究の専門は「がんの生物学」である。米国テキサス大学のM・D・アンダーソンがん研究所キャンサー・バイオロジーでがん転移の研究に取り組み、帰国後、長年の研究成果をもとにがん休眠療法を発表した。
高橋さんのがん休眠療法は「がんの生物学」と「従来の抗がん剤治療の問題点」から誕生した。高橋さんは「がんの生物学」について、以下のように説明する。
人間の細胞は1個の受精卵から始まり、60兆個で完成し、増殖がストップする。つまり、細胞分裂は止まっている(休眠)状態である。ただし、3000億個の細胞(全体の0.5パーセント。骨髄、消化管粘膜、毛髪など)は分裂を繰り返している。がん細胞は5~6個の遺伝子の異常から生まれる。わずか10ミクロン(ミクロン=1000分の1ミリ)で生まれたがん細胞は猛烈なスピードで増殖し、1センチになると転移を起こす。10センチの大きさでがん細胞の数は1兆個になり、5~6兆個(全体の10パーセント)になると人間は死に至る。
「つまり、がんとは分裂を休止して眠っていた細胞が目を覚まして暴れている状態のことです。そこで、暴れている細胞をもう1度、眠らせてしまう。つまり、増殖を止める治療を行うというのが休眠療法です。がん細胞を消滅させることは難しいが、増殖のスピードを遅らせて、5~6兆個になるまでの時間を先に延ばし、がんと共存しながら延命を図るのです」(高橋さん)
また、「従来の抗がん剤治療の問題点」について、高橋さんは次のように述べる。
遺伝子の異常で発生したがん細胞は正常細胞とほとんど違いがないため、綿密な免疫の網にもかからず、増殖している。がん細胞の大きな特徴は増殖していることである。そこで、増殖する細胞をすべて殺すことを目的に開発されたのが抗がん剤なのだ。そのため、抗がん剤は増殖する細胞はすべて殺す。人間の体の中で分裂を繰り返している骨髄、消化管粘膜、毛髪の細胞(がん細胞よりも分裂が速いものも少なくない)も殺すため、抗がん剤を使うと当然のように骨髄抑制、下痢、嘔吐、脱毛が起こる。
「国立がん研究センター名誉総長の杉村隆先生は『抗がん剤の主作用が白血球減少や下痢で、副作用ががんの縮小』という意味深い言葉をなげかけています。その通りです。つまり、抗がん剤はがんを特異的に殺すのではなく、増殖の速い細胞を殺す薬剤です。ですから、がんを殺すという観点からみると、白血病や肺小細胞がんなど増殖の速いがんにはかなり有効ですが、胃がんなど多くの固形がんには十分に有効とは言えないのです」(高橋さん)
さらに、抗がん剤の投与量にも問題がある。現在、抗がん剤の使用量は10~15人程度の臨床試験(第1相試験)で、少しでも多く投与しようという方針で、「人が死なない限界の量(最大耐用量)」が決められる。「しかし、最大耐用量の抗がん剤を投与しても実際がんが半分程度に縮小するのは5人に1~2人程度です。しかも、半分に縮小しても大きな意味はなく、十分な延命にはつながりません。また、抗がん剤の適量には遺伝子学的に5~50倍の個人差のあることが判明しています」と高橋さんは言う。
現在の抗がん剤治療では「効いた症例」でもがんが半分に縮小しただけで、その確率も20~30パーセントに過ぎず、その程度の縮小では生存期間も2~3カ月延長するにすぎない。そのため、多くのがん患者は大きな効果も得られず、抗がん剤の副作用に苦しむか、もしくは抗がん剤治療を拒否して静かに過ごすかのどちらかを選択するしかなかった。高橋さんは「この現状を何とか変えたい」と思った。そこで、第3の選択としてがんと共存していくがん休眠療法を提唱したのだ。
副作用のグレードを指標に個々の投与量を決定
[従来の化学療法]
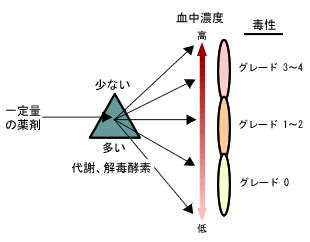
[テーラード・ドーズ化学療法]
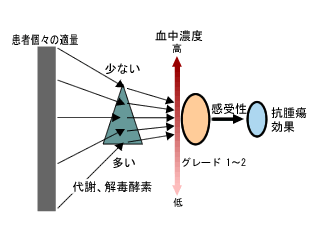
従来の抗がん剤治療は「がんの消失・縮小」を目的に、抗がん剤を限界の量まで、より多くという発想で行われてきた。ところが、がんを縮小しても必ずしも十分な生存期間の延長にはつながらず、すでに述べたようなさまざまな問題点を抱えている。これに対して、がん休眠療法は「がんの増殖の抑制」を目的に、1人ひとりで治療が継続できる最大の量(最大継続可能量)を探りながら抗がん剤治療を行うという点で大きな違いがある。
しかし、この療法が提唱された当初は何を指標にして、継続できる最大の量を決めるのか、はっきりしなかった。そこで、高橋さんが考案したのが抗がん剤による副作用を軽い状態(継続できる最大の副作用)に抑えて(グレード1~2以下)、患者個々で量を調整して、治療の継続を可能にするという「テーラード・ドーズ化学療法」である。
副作用のグレードは0から4まで5段階になっている。この副作用判定基準の内容・項目は、アレルギー・血液・代謝・消化器系を含めて膨大できめ細かく定められている。一般にグレード0は副作用なし。グレード4はきわめて危険という状態だ。
グレード1では、嘔吐は1日1回、下痢は1日3回まで、食欲はないが食べられる程度。グレード2では、嘔吐は1日2~5回、下痢は1日4~6回、口からの食物の摂取量が著しく減った状態だ。高橋さんは、この副作用のグレードを指標にして、抗がん剤の量を減らしたり、増やしたりして、治療が続けられるようにと考えて、実際に取り組んできた。
「胃がんなど固形がんの進行・再発がんの場合、抗がん剤治療で延命効果の得られている症例では、結果的にそのほとんどで副作用がグレード1~2の範囲内に抑えられているものが多いようです。抗がん剤治療を継続していくためには、このことからも、副作用のグレードを1~2にするように、抗がん剤の投与量を調整していくことが重要です」(高橋さん)
[抗がん剤による毒性と各種がんの効果との関係]
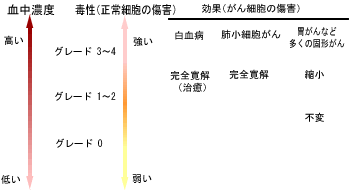
同じカテゴリーの最新記事
- 口腔ケアでがん転移抑制の可能性も! 虫歯菌による血管炎症で血栓症・がん転移が増える
- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために
- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識
- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要
- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩



