妻と共にがんと闘った追憶の日々
君を夏の日にたとえようか 第1回
架矢 恭一郎さん(歯科医師)

顕と昂へ
君を夏の日にたとえようか。
いや、君の方がずっと美しく、おだやかだ。
――ウィリアム・シェイクスピア
第一章 プロローグ
1.発病
それは、2014年9月初旬、まだ暑い夏の日の午前のことだった――。
私はいつものように歯科診察を始め、急患が駆け込んだり、トラブル発生のリスクの一番高い〝魔の1時間〟をなんとかやり過ごした。木曜日だった。いや、金曜日だったかも知れない。
いつもの時刻に郵便の束が配達されたとき、見慣れないやや大仰な分厚い封筒に目が留まった。封筒は、PET-CTで全身がん検診を行なっていることでも知られる放射線科専門のクリニックからで、院長の名前はよく知っていた。私が、大学病院で口腔がんの治療に携わっていた頃、放射線治療で世話になった医師だったからだ。この街の大学病院を離れ、関東の私立大学医学部の放射線科で教授をされていると聞いていたのだが、このような縁になろうとは……。
妻の恭子は、火曜日にそのクリニックでPET-CTによる全身検査を受けていた。恭子がその施設を受診する際に、私は挨拶を兼ねた短い紹介状を持たせてあった。それに返答をいただけるとは期待していなかったので、私はやや怪訝な気持ちで、その持ち重りのする封筒を開封した。
乳がん検診は受け続けていた
恭子の左側の乳房にしこりがあることは、しばらく前から気がついてはいた。が、恭子も私も長年持ち続けている乳腺症のしこりだろうと思っていた。恭子の乳房は乳腺症のためにぼこぼこのしこりが複数あるのが常だった。がんの小さなしこりに気づくには、本当に不利な乳房だったのだ。
しかし、しこりは左乳房全体に硬く広がっているようで、素人の私でもさすがに心配になって、早く診てもらうように恭子を急かせていた。
恭子は16年前に乳がん検診で引っかかり、その道の権威として有名な古木先生に診てもらった。当時の診断は、乳腺症で悪性とは考えられないというものだった。それから半年ごとに、古木先生のもとで乳がん検診を受け続けていた。
そして、2014年2月の定期検診でも乳腺症のほかは問題ないということで、先生は「もう診始めて随分になるから、今後は1年に1回の検診でいいだろう」とさえ言われた。だから、恭子は受診を躊躇していたのだ。
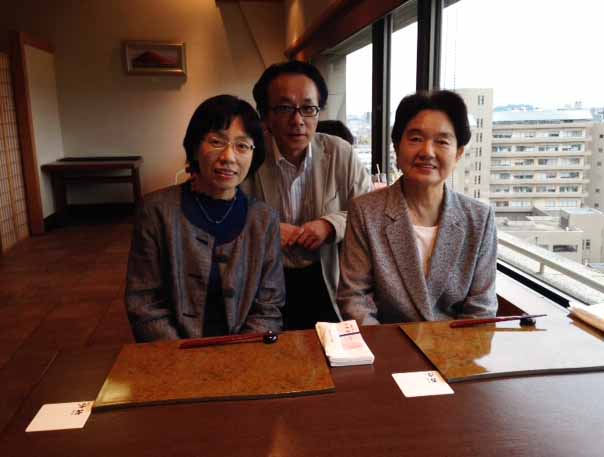
急激な疲労感と虚無感に
8月19日、やっと古木先生のところを受診してくれた。前回の受診から僅か半年。古木先生は診るなり、「大きな病院の乳腺外科部長の山崎先生を紹介するから、受診するように」と言われた。
5日後の24日、私も同行して古木先生の説明を受けた。先生の説明はしどろもどろといった感じでよく理解できなかったが、最悪の事態を覚悟した。乳がんに違いないと。しかし、それは遥かに甘かった。
「半年であれほど急速に大きくなると、むしろ悪性とは考え難いくらいだった」と古木先生が驚かれていたと、のちに人づてに聞いた。
翌25日、恭子は紹介された山崎先生のもとを訪れた。いきなり太い針で細胞診の検査。麻酔の注射も、組織採取もひどく痛かったと恭子がしょんぼりしていた。止血のために、巨大な弾性布絆創膏で左側の乳房が変形するほど圧迫されていて、それを夕方はずすときに私には決して触らせず、1人で慎重に格闘していた。
恭子はリンパ浮腫(ふしゅ)を異常に恐れた。昨年、甲状腺がんの手術を受けた際に、同じく左側の頸部リンパ節の郭清(かくせい)術を受けて軽いリンパ浮腫を経験してから、左腕のことをずっと気にし続けていたからだ。傍目にはわからないほど軽いものだったが、本人ははっきり違和感を感じていたのだ。細胞診の結果のことよりも、浮腫のほうが気になって仕方ない風だった。
9月2日。私たち夫婦は、15人に満たない小さな合唱団に加入していて、私がテナー、恭子がアルトを歌っている。外科医の高嶋先生が主宰され、先生のご自宅で月に1、2回練習がある。私たちは、この合唱団で共に歌うことを無上の喜びとしていた。
その練習をキャンセルして、恭子は山崎先生から紹介された放射線科クリニックで、PET-CTと乳房の造影MRI検査を受けた。その結果が届けられたのだ。
封筒を開くと最初のページに、「園田先生。資料に目を通されたら、すぐ私にご連絡をください」と、自筆のメモ書きが添えられていた。嫌な予感がした。最悪の事態を覚悟した。すぐに、院長室でMRIとPET-CTの報告書を開いた。
「左側乳がん。リンパ節転移。および骨転移の疑い」という文字が、目に飛び込んできた。現実味がなかった。文字は読めても、実感が湧かない。書かれている意味の実体を理解するのに、時間がかかった。覚悟していた最悪を遥かに越える事態が発生している……。
「院長、PMTC(歯面清掃)が終わりました。チェックをお願いします」
歯科衛生士の恵美子さんの声に吸い寄せられるように院長室を出て、マスクとゴム手袋をしながら診療室に歩を進めた。
私のなかで、何かが大きく変貌するのを自覚していた。何か大切なものが、ガラガラと音をたてて崩れ落ちるのを実感していた。何かが、終りを告げているのだ。急激な疲労感と虚無感に襲われながら、その日の午前中の診療をどのようにして乗り切ったのか、私は覚えていない。
めそめそ悩んでいる時間などない
電話の向こうの声には聞き覚えがあった。
「ああ、園田先生ですね。院長の谷本です。今回は、大変なことになってしまって……」
私には、事の重大さが認識できていなかったに違いない。頭の奥が痺れて、脳は正常に思考していなかった。〝悪い夢を見ているに違いない〟という使い古された言い回しが、グルグルと体中を駆け巡っていた。
谷本先生の言われていることを、きちんと理解できなかった。聞こえなかったのだ。いや、きちんと聞こえていて、医学的な意味合いもわかっていたが、どうしても、受け入れられなかったのだ。人が物事の意味をきちんと理解するということと、その理解したことを自分のこととして受けとめられるということは、違う。
「白黒、はっきりさせようじゃありませんか」と谷口先生。
「こんどの日曜日に、我々が開発している従来のPET-CTよりも感度のよい NaF-PETを予定しました。これは、開発段階のものだから、無償で検査させていただきます。朝食を抜いて、9時にはいらしてください」
慌しくお礼の言葉を述べて、電話を切って、やっと呆然とした。自分がしっかりせねばと言い聞かせながら、午後の診療を終えた。午後7時に患者が去って空になった診療室で、また名状しがたい疲労感と絶望感が襲ってきた。スタッフに愛想笑いを残して、私は重い足取りで家路についた。
その後の3日間を私は呆然と過ごした。これは何かの悪い冗談か、そうでなければ悪夢を見ているに違いないと幾度も思った。きっと、目を覚ませばこれまで同様の穏やかで希望に満ちた毎日が戻ってくるに違いないと……。しかし、夢ではなくてこれはれっきとした、しかも過酷な現実なのだ。
もし、恭子がいなくなったら、私は1人で生きていけるだろうか? これまで自分は何のために頑張ってきたのだろうか? 大学での口腔外科の臨床や研究、留学、歯科医院の開業。やっと軌道に乗って、ライフワークといえそうなものも見えてきたのに……。私の人生は損なわれてしまったのだ。
そうして、4日目に私はハタと気がついた。私は自分の辛さや絶望ばかりを気に病んいるじゃないか。もっと辛い思いをして打ちのめされているのは、恭子自身なのに。そうなのだ。めそめそと悩んでいる時間などない。恭子を守って、支えて、是が非でもがんに打ち克って、救い出さなくてはいけない。



