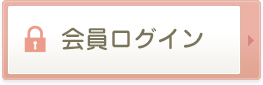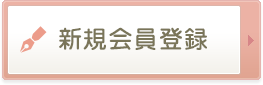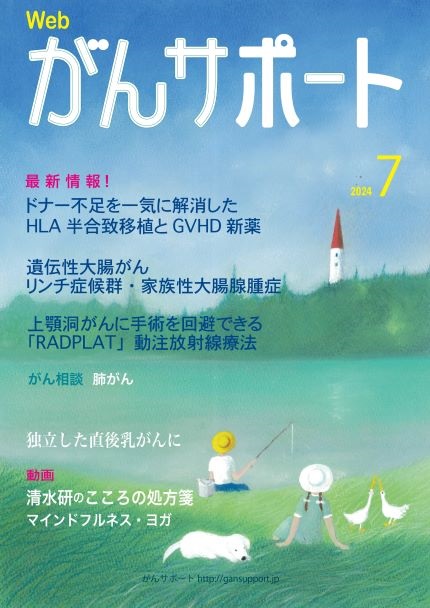造血幹細胞移植後に多発する不妊を防ぐために
あきらめないで!! 妊娠機能を温存する、放射線から卵巣を守る治療
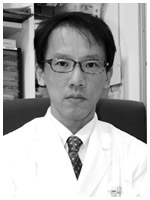 自治医科大学付属
自治医科大学付属さいたま医療センター
血液科教授の
神田善伸さん
若い女性にとって、がん治療で将来の妊娠・出産の可能性を奪われることは大きな苦痛です。
日本でも、最近ようやく不妊対策に目が向けられるようになりましたが、早くからこの問題に取り組んできたのが、自治医科大学付属さいたま医療センター血液科教授の神田善伸さんです。
最近では、放射線から卵巣を守ることで、造血幹細胞移植後の不妊を防ぐことが可能になってきたといいます。
化学療法前に精子の凍結保存
日本で、がん治療による不妊問題に目が向けられるようになったのは、つい最近です。自治医科大学付属さいたま医療センター血液科教授の神田善伸さんによると、「昔は命さえ助かれば、という状態でしたが、少し余裕が出て妊娠機能の温存まで考えられるようになってきたのが、2000年頃からなのです」。神田さん自身は、1995年頃から、不妊問題に取り組んできました。
神田さんは血液がんの専門医。白血病や悪性リンパ腫など血液のがんでは、造血幹細胞移植ががんを根治させる治療法の1つになっています。これは、患者さんの骨髄を大量の抗がん剤や全身の放射線治療で徹底的に叩き、骨髄もろともがん細胞を殲滅。そのあとに、適合する健康な骨髄を移植する治療法です。移植前に強力な治療(移植前治療)を行うため、卵巣や精巣に対する影響が大きく、不妊になる可能性が高いのです。
「移植前のインフォームド・コンセントで不妊の可能性について説明すると、男性でも女性でも若い人はやはりショックを受ける人が多いのです」
それが、早くから不妊対策に取り組むきっかけになったのです。当時、すでに精子の凍結保存は可能でした。精巣は、卵巣より抗がん剤や放射線には弱いといいます。
「一般的な化学療法でも、精巣より卵巣のほうが回復が早いのです。放射線治療でも卵巣は5グレイぐらいまで耐えられますが、精巣は2グレイが限界。いずれにしても、精巣のほうが感受性が高いのです」
ですから、精子を凍結保存して将来の受精に備えられることは意味が大きいのです。
ただし、化学療法を行った後は、精子の運動能力が低下することが多いので、できるだけ抗がん剤を使う前に精子を採取しておくことがポイントだそうです。一方、女性の側にはいくつもの難題がありました。
| 危険性 | 抗がん剤 |
|---|---|
| 遷延性無精子症になるもの | 放射線療法(睾丸に2.5グレイ)、シクロホスファミド(19mg/m2)、プロカルバジン(4g/m2)、メルファラン(140mg/m2)、シスプラチン(500mg/m2) |
| 他の抗がん剤と使用したときにしばしば無精子症となりえるもの | ブスルファン(600mg/kg)、イホスファミド(42g/m2)、アクチノマイシン-D |
| 通常量ではあまり遷延性無精子症は認められないもの | カルボプラチン(2g/m2) |
| 上記薬剤との相加的作用により遷延性無精子症を引き起こす可能性があるが、併用しなければ精子数の減少は一時的なものに過ぎないもの | ドキソルビシン(770mg/m2)、チオテパ(400mg/m2)、ビンブラスチン(50g/m2)、ビンクリスチン(8g/m2) |
| 通常量では精子数が一時的に減少するに過ぎないが、他の薬剤への相加的な作用の可能性があるもの | ブレオマイシン、ダカルバジン、ダウノルビシン、エピルビシン、エトポシド、フルダラビン、フルオロウラシル、6-メルカプトプリン、メトトレキサート、ミトキサントロン |
| 精子の産生に影響する可能性が低いもの | プレドニゾロン |
| 精子の産生に影響がないもの | インターフェロンα |
| 精子の産生に影響が不明なもの | オキサリプラチン、イリノテカン、モノクローナル抗体(トラスツズマブ、ベバシズマブ)、チロシンキナーゼ阻害剤(イマチニブ、エルロチニブ)、タキサン系抗がん剤 |
| 危険性 | 治療法 |
|---|---|
| 高リスク(80%超) | 造血幹細胞移植の前処置での全身放射線照射法と大量シクロホスファミドの併用、あるいは大量ブスルファンと大量シクロホスファミドの併用 卵巣を含む照射野への外照射 40歳以上の女性を対象としたCMF、CEF、CAF療法×6クール (シクロホスファミド/メトトレキサート/フルオロウラシル/ドキソルビシン/エピルビシン併用の乳がん補助療法) |
| 中程度リスク | 30~39歳の女性を対象としたCMF、CEF、CAF療法×6クール (シクロホスファミド/メトトレキサート/フルオロウラシル/ドキソルビシン/エピルビシン併用の乳がん補助療法) 40歳以上の女性を対象としたAC療法×4クール (ドキソルビシン/シクロホスファミドでの乳がん補助療法) |
| 低リスク (20%未満) | ホジキンリンパ腫に対するABVD療法 (ドキソルビシン/ブレオマイシン/ビンブラスチン/ダカルバジン) 非ホジキンリンパ腫に対するCHOP療法 (シクロホスファミド/ドキソルビシン/ビンクリスチン/プレドニゾロン) 急性骨髄性白血病に対するアントラサイクリン系薬剤/シタラビン療法 急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法 30歳未満の女性を対象としたCMF、CEF、CAF療法×6クール (シクロホスファミド/メトトレキサート/フルオロウラシル/ドキソルビシン/エピルビシン併用の乳がん補助療法) 40歳未満の女性を対象としたAC療法×4クール (ドキソルビシン/シクロホスファミドでの乳がん補助療法) |
| 非常に低リスク またはリスクなし | ビンクリスチン、メトトレキサート、フルオロウラシル |
| リスク不明(例) | オキサリプラチン、イリノテカン、モノクローナル抗体(トラスツズマブ、ベバシズマブ)、チロシンキナーゼ阻害薬(イマチニブ、エルロチニブ)、タキサン系抗がん剤 |
出典:Stephanie, Lee. et al:J Clin Oncol 24:2917, 2006
難しい卵子の凍結保存
今、女性の不妊対策には、(1)卵子を凍結保存する、(2)放射線照射から卵巣を遮蔽して妊娠機能を温存する、という2つの方法があります。
ただ、「卵子の凍結保存は今でも簡単ではありません」と神田さんはいいます。配偶者のいる人は、卵子を採取して受精卵として凍結保存することができます。この技術は、95年当時からあったそうです。ただ、精子と違って受精可能な成熟した卵子を採取するためには、排卵周期に合わせて採取しなくてはなりません。かつ、化学療法を行っている場合には、化学療法のダメージから卵巣が回復した時期を見計らって採取しないと、受精可能な卵子は採取できないのです。排卵周期と卵巣機能の回復、白血病などがんの治療中にその時期を合わせるだけでも大変なことなのです。
卵子採取への技術的な問題
さらに、技術的な問題もあります。卵子を採取するためには腹部から卵巣に針を刺して卵子を採ってこなければなりません。しかし、化学療法で治療中の患者さんは、免疫機能が低下し、血液を固める時に必要な血小板の量も減っています。針を刺した時の出血と感染もまた手ごわい相手なのです。さらに、化学療法を何回も行っていれば卵巣がダメージを受けますので、十分な量の卵子を採取することも難しくなります。
従って現実には「10個卵子を凍結保存して、赤ちゃんが1人できる確率」なのだそうです。
それならば、がんの治療を始める前に、卵子を採取しておけばいいのでは、と考える人もいると思います。しかし、神田さんによると「急性白血病の場合は、診断がついたその日から化学療法を始めることもあります。慢性の白血病のように進行が遅いものなら可能かもしれませんが、とても治療前に排卵周期に合わせて卵子を採取する余裕はないことが多いのです」。
またもう1つ、問題がありました。それは、未受精卵の凍結保存が難しかったことです。
未受精卵の凍結保存も可能に
| 移植日 (移植胚数) | 移植胚 総数 | 妊娠数 | 出産数 | 妊娠中 |
|---|---|---|---|---|
| 2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2(3) | 51 | 6 | 4 | 1 |
| 5(1) | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 総計 | 64 | 12 | 7 | 3 |
受精卵の凍結保存は、配偶者やパートナーがいる人にはいいのですが、未婚の女性や10代の若い人の場合、将来妊娠するためには、未受精卵の凍結保存が必要です。
ところが、未受精卵は受精卵と違って、保存が難しかったのです。未受精卵は凍結すると膨脹して壊れやすく、保存しても解凍時の卵子の生存率は2割程度。せっかく保存しても受精して妊娠に至る確率は極めて低かったのです。これを変えたのが「ガラス化法」です。
これは、簡単にいうと卵子の細胞内の液を特別な溶液に置き換え、急速に凍結して氷の結晶を作らないようにする方法です。すると、卵子が壊れることなく凍結保存ができるのです。もともと、体外受精で牛の品種改良を行うために使われていた方法だそうです。神田さんによると「今では、世界的に未受精卵の凍結保存にはガラス化法が行われている」そうです。
がん患者ではなく、一般の不妊治療患者を対象にガラス化法を行った場合、凍結保存した64個の未受精卵のうち、解凍後も9割(58個)が正常な形のままで、52個受精して32個が試験管内で正常な分裂を始めたと報告されています。未成熟卵のほとんどが解凍後も正常で、受精率も高いという結果だったのです。
では、実際の妊娠出産はどうなのでしょうか。
「一般の不妊治療では、97年まではわずか5例しか妊娠例がなかったのですが、顕微授精が始まって妊娠出産例も多くなりました。日本でも、一般の不妊治療では64個の受精卵の移植で12人が妊娠し、7人が出産しています」
ガラス化法の登場と顕微授精の開発で、ようやく未受精卵の凍結療法も本格的に実用化できるようになったのです。
こうした流れの中で、がん患者を対象に未受精卵の凍結療法を行おうという機運も高まっています。血液がんの未婚女性を対象に、未受精卵を採取し凍結保存を行う臨床試験も、現在進行中だそうです。
ただし、「がん患者ではまだ、ガラス化法で未受精卵を凍結保存し、妊娠出産した例はないのです。凍結した卵子を受精して体内に戻すのは、治療が終わって結婚してからのことです。実際に患者さんが子供をうむのはなかなか決心がいることなので、普通は治療から3~4年たって、再発の心配がなくなってから考えるのです」と神田さん。
血液のがんを克服した患者さんが、ガラス化法を利用して妊娠、出産するのは、まだもう少し先になりそうです。