不安やストレスを軽減する心のサポートの重要性
正しく理解することから始まる、症状緩和のセルフケア
 国立看護大学校
国立看護大学校成人看護学教授の
飯野京子さん
いいの きょうこ
1960年生まれ。
82年新潟大学医療技術短期大学部卒。
1999年聖路加看護大学大学院修士課程成人看護学がん看護CNSコース卒。
82年国立がん研究センター中央病院、看護師。
2001年国立看護大学校成人看護学教授。
専門は、成人看護学、がん看護。
正しい情報こそがストレスを小さくする
末期がんの患者さんに対するターミナルケアでは、「心のサポート」ということが大切になります。でも、心のサポートが必要なのは末期がんの患者さんだけではありません。早期がんでも、進行がんでも、がんの患者さんの心は不安にさいなまれやすく、これに対して本人がどのような心構えを持つか、周りがどのようにサポートするかが重要です。
今日の抗がん剤治療は、普通の生活をしながら外来で治療を受ける人が増えてきました。こうした患者さんはターミナルケアの患者さんとは異なる、大きく3つの問題で心を悩まされます。
まず抗がん剤治療を受けている患者さんは、毒性の強い、不安に陥りやすい治療を長期に渡って受けなければならないということです。治療を受ける前に、「脱毛するのではないか」「吐き気に襲われ続けるのではないか」といった不安を持ちます。治療が始まると、「自分の状態は異常ではないか」「もっとつらい目に遭うのではないか」「死んでしまうのではないか」という不安や恐れと向き合っていかなければなりません。これらをどのように解消していくか。それが問題です。
また、抗がん剤治療はかなり長い期間、繰り返し受けなければなりません。手術なら1回受けるだけですみますが、抗がん剤治療は、たとえば「3週間で1クール(セット)を3回繰り返す」というように、数カ月あるいは数年かかって終了し、はじめて1つの治療が完結します。
もし途中で治療を中断することになれば、効果は得られずに副作用ばかり現れるというつらい思いをするのです。そこで、闘病意欲をしっかり継続していかなければなりません。
さらに抗がん剤治療を受け始めると、以前とは生活が一変してしまいます。治療を受けながら仕事を続けるという人も増えていますが、そのために様々な精神的、社会的な問題と直面することになります。ある患者さんは「診断書に“がん”と書くと、会社で仕事を減らされてしまう」というので、医師に“悪性腫瘍”と書いてもらいました。このように、社会生活とどのように調整をはかっていくかということも大きな問題になってきます。
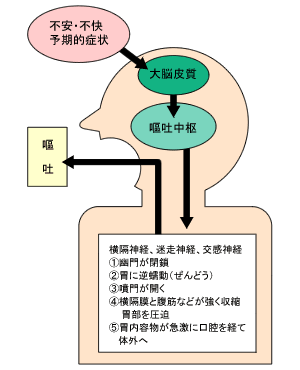
これらの3つの問題を患者さんが克服するために必要なのは情報、予備知識です。不安を解消するためには、まず「その症状はだれでも体験するものですよ」とか、「治療から○日目くらいまでは食欲が落ちることがありますよ」、さらに「苦痛を緩和する手段がありますよ」といった説明が求められます。長期間闘病の気持ちを維持する上では、「データからいうと症状の程度はどのくらいなので、あとどれくらい副作用を我慢すれば解消しますよ」という情報が大切です。さらに、生活の調整をする上では、「これからどの時期に体調が変化しますよ」「治療スケジュールがこうなので、こんな強さの副作用がこのように出ますよ」という情報が役立ちます。
こうした側面からの正しい情報は、抗がん剤治療を受ける患者さんの心がまえをつくり、不安や不快などのストレスを小さくする役割があるのです。その結果、実際に抗がん剤の副作用である悪心・嘔吐を軽減できることがわかっています。
抗がん剤によって悪心・嘔吐が生じるには、3つの大きなメカニズムがあります。1つは抗がん剤が血液を介して脳の化学物質受容体に刺激が伝達され、嘔吐中枢に至って起こるもの。もう1つは抗がん剤が消化管の神経末端の受容体と結合し、迷走神経や交感神経を経て嘔吐中枢に至るもの。
さらにもう1つは、嘔吐した経験などによる不安や不快などの感情が、大脳皮質を通って嘔吐中枢を刺激するものです。この悪心・嘔吐は、不安を小さくすることで抑えることになります。一方、感情が影響して起こる悪心・嘔吐には、セルシン(一般名ジアゼパム)などの精神安定剤が用いられます。
聞きたいことをメモ用紙にリストアップして持っていく
現在は医療情報を探求しようとすれば、医療者以外にも雑誌やインターネットなどいろいろな手段があります。しかし、そこから知ることができるのはあくまでも一般論であり、そのまま個別的な病態に当てはめることは無理なのです。
とくにがんの場合は、同じ乳がんという病名であっても、細胞のタイプや病気の進行度など病態が異なっていれば、治療方法も違ってきます。抗がん剤の副作用もどういう時期にどういうことが起こるかは、投与している医療者にしかわからないことも少なくありません。
また、医療者から正確な情報を仕入れるためには、患者さんのほうもどういうストレスがあるかということも含めて、正確な情報を医療者に伝える必要があります。医療者も患者さんの自覚症状を把握できれば、それを考慮した治療が可能になってくるかもしれません。
たとえば痔の症状が出ていたとしても、患者さんは「がんとは関係ないだろう」と勝手に判断して医療者に伝えないことがあります。ところが、医療者なら「今は粘膜症状が出やすい時期だから、その1つとして痔になっているのだ」と判断し、そのことを的確に説明し、治療を行うことができます。
自分に現れている症状の意味が理解でき、気になる症状を少しでも減らすことができれば、患者さんは自分のストレスをより小さくできるでしょう。
しかし、患者さんは医師の前に出ると、うまく話ができないといったことが少なくありません。とくに「お金はどのくらいかかるのか」とか、「医師は手術を推奨しているけれど、放射線治療についても聞きたい」という場合は、そのことを担当の医師になかなか伝えにくいものです。
そこで、口に出して聞きにくいなら、聞きたいことをメモ用紙にリストアップして持っていくという方法もいいと思います。医師に「今日はこんなことをお聞きしたいと思ってきました」と、そのリストを見せて順番に聞いていくと聞きやすくなるでしょう。今や、患者さんは医師に「何を聞いてもいい時代」なのだということをぜひ再認識してください。
医師の前で「いい子」になる必要はまったくない
医師へ伝える情報は、あくまでも具体的で正確である必要があります。気をつけなければならないのは、たとえば医師が「おかげんはいかがですか?」と聞いたとき、つい反射的に「はい、調子はいいです」と答えてしまう患者さんがわりと多いということです。べつに演技をしているわけでもなく、本当は訴えたい症状があるのに、医師の前ではつい「いい子」になってしまいがちなのではないでしょうか。入院中の患者さんなどでも、回診のとき医師の顔を見るとそれだけで安心して、「いつもありがとう」と笑顔を見せて具合がいいように思わせてしまうところがあるようです。
その結果医師は、「副作用が出るはずの時期なのに、ニコニコしているから体調は悪くないんだな」というふうに受け取ってしまうことになります。ですから、医師に体調を伝えるとき患者さんは「昨日より○○が少しはいいです」というふうに、できるだけ具体的に伝えるようにしましょう。
また、体の各部が痛いときは痛みの度合いを示すものさしのチャート表があるので、そうしたものを利用して痛みの強さを示すようにします。そして、医師には必要以上に「いい」という話をして安心させてしまわないようにすることが基本です。
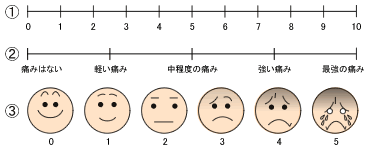
抗がん剤の通院治療は、できるだけ仕事をしながら普通の社会生活を続けていけるようにしないと、長期にわたって続けることができません。患者さんとしては、医師との間で来院日を決めるにしても、「私は金曜日は仕事があるのでどうしても来ることができません」というふうにきちんと主張すべきです。
もっともいろいろな状況から、必ずしも主治医に相談しやすい環境が整っているとは限りません。しかし、このように医師に直接聞きづらいときのために、「看護相談」のような窓口を置いている病院もあります。ぜひそうした窓口を見つけて活用するようにしてください。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 症状が長く続いたら感染併発やステロイドの副作用を考える 分子標的薬による皮膚障害
- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する
- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事
- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療
- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を
- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く
- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明
- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント



