内視鏡的切除と低用量化学放射線療法、膀胱部分切除を組み合わせた膀胱温存療法
進行した膀胱がんでも膀胱温存が可能!

膀胱温存療法を
広めていきたいと話す
木原和徳さん
現在、浸潤性膀胱がんの標準治療は膀胱全摘術である。しかし膀胱全摘術は、QOL(生活の質)の面でさまざまな問題が残る治療法でもある。それを解決したのが、膀胱温存療法だ。再発も少なく、根治性も高い治療法だと期待されている。
膀胱を全摘するとその後が大変
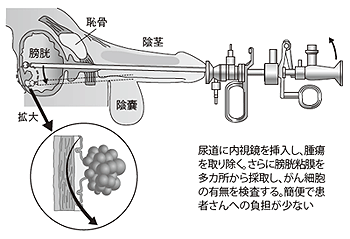
膀胱がんの標準治療は、表在がん(筋層非浸潤がん)と浸潤がん(筋層浸潤がん)で、大きく異なっている。表在がんなら、膀胱鏡を使ってがんの部分だけを切除する経尿道的膀胱腫瘍切除術(以下、経尿道的切除)と呼ばれる方法で、膀胱を残すことができる(図1)。一方、浸潤がんの場合は、膀胱全摘術が世界的な標準治療となっている。
東京医科歯科大学大学院腎泌尿器外科学教授の木原和徳さんは、膀胱全摘はいろいろな意味で問題が残る治療法だと指摘する。
「膀胱を全摘すると、通常、回腸導管や自排尿型新膀胱などの尿路変向術が行われます。手術は、ときに死亡例も報告されるリスクを伴うもので、腸閉塞などの合併症も稀ではありません」
回腸導管は、腹壁に作ったストーマ(排泄口)から尿を出す方法。自排尿型新膀胱は、小腸で袋を作って代用膀胱とする方法で、腹圧で尿道から排尿することができる。
「これらの技術で、膀胱全摘を受けた後でも普通に近い社会生活を送れるようになったことは確かです。しかし、回腸導管では、多くの方がストーマからの尿漏れなどのトラブルを何度も経験していますし、新膀胱は、伸展して多量の尿が残るようになったり、夜間尿失禁を起こしたりします。また性機能障害も伴います。こうした身体的・精神的ストレスに加え、集尿袋など排尿管理のための装具や器具の費用も、生涯にわたって必要となります。膀胱全摘・尿路変向という治療は、まだまだ課題の多い治療法なのです」
標準治療には、大きな問題が残されているようだ。
世界中で膀胱温存療法が試みられてきた
こうした問題が残されている中、浸潤性膀胱がんでも膀胱を温存して治療したいというのは、世界中の患者さんの願いであり、これまでに多くの温存療法が試みられてきた。
「膀胱鏡を用いてがんの部分だけを切除する経尿道的切除ではどうか、放射線治療ではどうか、抗がん剤治療ではどうか、あるいは膀胱の中でも、がんとその周囲の膀胱壁の一部を切除する部分切除ではどうか。いろいろ行われましたが、問題となるのは根治性でした。その中で、部分切除は、まずまずの成績を残しました」
膀胱全摘の場合、5年生存率は50~60%程度。これに対し、部分切除の5年生存率は70%程度だった。ただし、この手術を受けられるのは、単発のがんで、がんから2㎝離して切っても尿管口(尿管と膀胱の接続部)にかからないのが条件。対象となる患者さんは多くはなかった。
「経尿道的切除でがんの部分だけを取り除き、その後に化学放射線療法を行う治療も、いい成績を残すことがわかりました。5年生存率は、膀胱全摘とほぼ同等でした」
この治療の問題点は、残した膀胱に浸潤がんが再発することだった。約4人に1人の割合で、がんがもとにあった場所に出てくる。このとき膀胱全摘ができればいいが、高用量の放射線治療で組織が障害されているため、リスクが高くなる。
それまでの欠点を補う膀胱温存療法
| ①範囲 | がんが膀胱腔内で1カ所に留まっている (浸潤がんを含む) |
| ②部位 | がんが膀胱の出口に及んでいない |
| ③低用量化学 放射線療法 | 低用量化学放射線療法後の検査で残存腫瘍が 見られない。 あるいはわずかな非浸潤腫瘍がみられる |
[図3 膀胱温存療法の流れ]
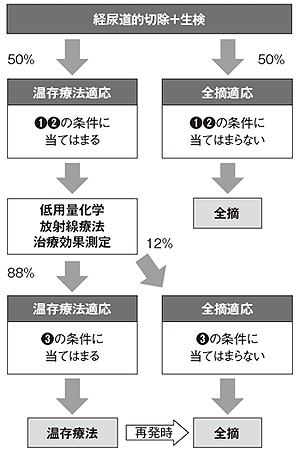
世界で行われてきたこれらの研究を踏まえて、どうすれば最も効果的な治療になるかに焦点を合わせて開発されたのが、「経尿道的切除+低用量化学放射線療法」と「膀胱部分切除」を組み合わせた「根治的膀胱温存療法」である。つまり、経尿道的切除によって、がんの部分を削り取り、化学放射線療法を行う。その結果に基づいて、がんのあった部分だけを、骨盤のリンパ節とともに切除し、膀胱を温存するという方法だ。
「経尿道的切除と化学放射線療法の併用療法は、がんのあった部位に比較的高率に再発するのが欠点でした。そこで、その部分を取り除くとともに、リンパ節転移への対応としてリンパ節も取る(郭清)ことにしました。さらに、高用量の放射線を照射してしまうと、その後の手術が難しくなるので、線量も低く抑えて、さらに抗がん剤の量も少なくして行うことにしたのです」
この治療を実施するにあたって重視したのは、患者さんを的確に選択することだった。たとえ膀胱を残せても、根治性が低かったら意味がない。最も大切なのは患者さんの命なので、膀胱を残しても大丈夫な人を、慎重に選び出すことにしたのだ。
そこでできたのが、膀胱温存療法を行うための適応基準である(図2)。経尿道的切除や低用量化学放射線療法を行いながら、この①~③の条件をクリアした人だけに、膀胱温存療法を行うことにしたのである(図3)。
同じカテゴリーの最新記事
- 新たな併用療法や新薬でまもなく大きく変わる! 進行性尿路上皮がんの1次治療
- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!
- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療
- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える
- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~
- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!
- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます
- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに
- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%
- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは



