補助化学療法の有用性をよく理解して治療を受けることが大切
経口抗がん剤による肺がんの術後の治療。2~3センチの腫瘍径の生存率がアップ

神奈川県立がんセンター
呼吸器外科医長の
坪井正博さん
肺がん手術でがん細胞をきれいに切除できても微小転移が起きている可能性がある。この微小転移が徐々に大きくなって再発につながることがあるので、再発予防のための術後補助化学療法としてUFTを服用することで2~3センチの腫瘍径の患者さんに有効であることが、神奈川県立がんセンター呼吸器外科の坪井正博さんらの無作為化比較試験の結果、明らかになった。
補助化学療法は効果が目にみえにくい治療であるため患者さんがその有用性をよく理解する必要があると坪井さんは語る。
1B期の術後補助化学療法にUFTの有用性を証明
肺がん(非小細胞肺がん)の手術を受けると、その後に補助化学療法が行われることがある。神奈川県立がんセンター呼吸器外科の坪井正博さんは、その必要性をこう説明してくれた。
「画像検査で明らかになっているがんをきれいに切除できても、病状によっては検査で見つからないほど小さな微小転移が、すでに起きていると言われています。この微小転移が徐々に大きくなって再発につながるので、手術後に化学療法を行い、その再発予防に期待するわけです」
この手術後の補助化学療法に、UFT(一般名テガフール・ウラシル)という抗がん剤が使われることがある。この薬は、古くからある5-FU(一般名フルオロウラシル)という抗がん剤を改良したテガフールとウラシルの配合剤である。UFTに含まれる主成分のテガフールが、肝臓の酵素の働きで5-FUに変化し、ウラシルを配合することにより、5-FUの効果が増強されるのが特徴である。
「1~3期非小細胞肺がんに対するUFTによる補助化学療法の臨床試験の中で、6つの無作為化比較試験を対象にしたメタアナリシス(複数の研究データを統合して効果の大きさを推定する統計学的解析方法)を行いました。
その結果、1期全体で5年生存率が4.6パーセント改善されることが明らかになっています。そのうち、私たちの行った試験ではとくに1B期肺腺がんでUFTによる術後補助化学療法を行うことで、5年生存率を11パーセント改善することが示されました。手術後に経過観察のみの患者さんの5年生存率が74パーセントだったのに対し、UFTを服用された患者さんは85パーセントだったのです」
肺がんの1期とは、がんが肺の中に止まり、リンパ節への転移や遠隔転移がない段階である。この中で、がんの大きさ(腫瘍径)が3センチメートル以下の場合を1A期、3センチメートルより大きい場合を1B期としている。
「1A期はもともと手術後の生存がよいため、補助化学療法の有用性を証明するのは簡単ではありません。ただ、1期を対象にした臨床試験が行われたとき、腫瘍径が2センチメートル以下の場合と、2~3センチメートルの場合で、差があるのではないかと思われる結果が出ていました」
そこで、腫瘍径2センチメートルにボーダーラインを設け、それ以下の場合と、それを超える場合での比較が行われることになったのである。
1A期でも2センチを超える場合は有用と判明
前述した6つの無作為化比較試験を対象にしたメタアナリシスでは、1A期を腫瘍径2センチメートル以下と2~3センチメートルの患者さんに分け、補助化学療法の効果を調べている。その結果、2センチメートル以下では統計的に意味のある差は見られなかったが、2~3センチメートルの症例では、手術後にUFTを服用することの有用性が明らかになった。
5年生存率で比較すると、手術だけの患者さんが82パーセントだったのに対し、UFTを服用した患者さんの5年生存率は88パーセントに向上していたのである(図1)。
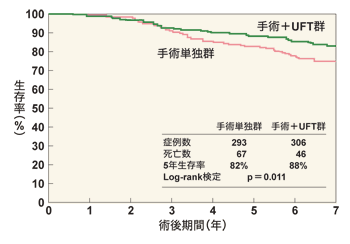
「肺がんの病期分類は2010年から新しくなります。これまでは腫瘍径3センチメートル未満を1A期とひとまとめにしていましたが、新しい分類では腫瘍径を2センチメートル以下と2~3センチメートルの2つに分類することになっています。2センチメートルのところにラインが引かれることを考慮して、今回の解析を行ったのですが、腫瘍径2~3センチメートルの患者さんには1A期であっても手術後に、UFTを服用することで生存率が改善することが明らかになりました。肺がんの生存曲線から考えても、2センチメートルというのは、腫瘍学的な分かれ目なのかもしれません」
まとめると、UFTによる肺がんの術後補助化学療法は、1A期で腫瘍径が2センチメートル以上の場合と、1B期の場合に有用性が証明されている。
重い副作用は少ないが個人差は大きい
UFTは内服薬なので、点滴で投与する薬に比べれば、患者さんは受け入れやすい。ただ、その反面、代謝の影響を受け個人差があり、飲み忘れるという欠点もある。
「補助化学療法は効果が目に見えない治療です。進行がんに対する化学療法なら、次第に腫瘍が小さくなるのが画像検査で確認できたりします。ところが、補助化学療法では、効いているかどうか確認できないし、そもそも微小転移が本当にあるのかどうかもわかりません。効果が見えず、副作用ばかりが見えてくるわけです」
UFTの副作用として比較的起きやすいのは、食欲低下や味覚異常などである。一般的な抗がん剤に比べれば、重い副作用が少ないのが特徴だ。ただ、副作用の現れ方や感じ方は個人差が大きい。たとえば、爪が少し黒ずむという副作用が現れることがあるが、ほとんど気にならないという人もいれば、薬をやめたいというほど気になる程度までになる人もいるという。
「効果が見えず、副作用ばかりが目につく補助化学療法を継続するためには、どのような目的でこの治療を受けるのかを、患者さん自身がしっかり理解している必要があります」
UFTは副作用が比較的軽いといわれる抗がん剤だが、補助化学療法は2年間の継続が基本となる。補助化学療法の有用性をよく理解することが、治療を続けるためのモチベーションとなるはずである。
同じカテゴリーの最新記事
- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん
- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療
- 肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで
- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場
- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法
- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン
- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる
- ゲノム医療がこれからのがん治療の扉を開く 遺伝子検査はがん治療をどう変えるか
- 血管新生阻害薬アバスチンの位置づけと広がる可能性 アバスチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が未来を拓く



