鎌田實の「がんばらない&あきらめない」対談
独立行政法人国立病院機構広島西医療センター病院長・田中丈夫さん VS 「がんばらない」の医師 鎌田實
がん患者さんの家族をつなぐ「サポートブック」の静かな広がり
自ら書き込むことによって家族の絆を深める絵本を作りませんか

たなか たけお
1947年、鳥取市生まれ。広島大学医学部卒業。東洋工業付属病院(現マツダ病院)で小児科医としてスタート後、広島大学病院で臨床と研究に従事。1982年、アメリカのUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)血液腫瘍部門の研究室に留学。1987年、国立呉病院(現国立病院機構呉医療センター)を経て、2008年より広島西医療センター病院長。サポートブック作成プロジェクトチーム代表として、『親子をつなぐサポートブック』の普及に努めている

かまた みのる
1948年、東京に生まれる。1974年、東京医科歯科大学医学部卒業。長野県茅野市の諏訪中央病院院長を経て、現在諏訪中央病院名誉院長。がん末期患者、お年寄りへの24時間体制の訪問看護など、地域に密着した医療に取り組んできた。著書『がんばらない』『あきらめない』(共に集英社)がベストセラーに。近著に『がんに負けない、あきらめないコツ』『幸せさがし』(共に朝日新聞社)『鎌田實のしあわせ介護』(中央法規出版)『超ホスピタリティ』(PHP研究所)『旅、あきらめない』(講談社)等多数
医療関係者と市民が作った「サポートブック」
鎌田 田中さんが中心になって、医療関係者と市民が協力して作られた、『親子をつなぐサポートブック』(以下「サポートブック」)という絵本が、がん患者さんの親子の絆を結ぶ本として話題を呼んでいます。「サポートブック」というのは、患者さんやその家族が絵本の中に書かれている、「○○○○がうまれた日はどんな日だった?」とか、「おとうさん、おかあさんからみて○○○○はどんな子?」とか、「おとうさん、おかあさんのであったときのおもいでは?」といった問いに、家族がそれぞれ答えを書き込みながら、自分たちで完成させていくスタイルの絵本ですよね。この本を作られたきっかけは?
田中 実は「サポートブック」は、私が仕掛けたものではありません。サポートブック作成プロジェクトの私の前任の代表である広島県赤十字血液センター所長の沖田肇先生が、患者さん向けの本はたくさんあるけれども、若いがん患者さんで最後までがんばったけれどもダメだった人の家族、とくに残された子どもさんをサポートするような本はないものだろうか、と声を掛けられたのがきっかけです。
鎌田 「サポートブック」は、子どものがん患者さんやその家族をサポートすると同時に、がん患者さんの親を持った子どもさんをサポートする本でもあるわけですね。
田中 スタートは、がんになったお父さんやお母さんの子どもさんをサポートすることから始まっています。私は小児科医ですから、それとは逆に、子どものがん患者さんをサポートする立場から入っています。子どもさんが小児がんになった場合、ご両親がその子の看病に一生懸命になりますから、残されたその子の兄弟が忘れられるという現実があるのです。
鎌田 サポートブック作成プロジェクトのチームは、病院の中にできたのですか。
田中 いえ、外です。「サポートブック」の最後にプロジェクトのメンバーが出ていますが、医療関係者だけでなくさまざまな分野の人で構成されています。
鎌田 それがいいですよね。こういう本は、内科医、小児科医、看護師、心理療法士、ケースワーカーなど、病院の中だけでできてしまいそうですが、絵本作家、色彩プロデューサー、一級建築士、翻訳家、新聞の論説委員などに参加してもらい、病院の外で作っている。そういう人たちからもいろんな意見が出たでしょう。
田中 侃々諤々、結構熱い議論が行われました(笑)。議論の最初の段階で参考にしたのが、イギリスのホスピス関係者の資料でしたが、その議論の中で出てきたのは、やっぱりイギリスと日本では土壌が違うということでした。イギリスでは、病気そのものが前面に大きく出てきて、死とか生きるということが表に出てくるわけですが、医療関係者ではないメンバーから、日本ではそれはちょっと違うのではないか、という意見が出てきました。
書いたものが残されると家族の絆はより深まる
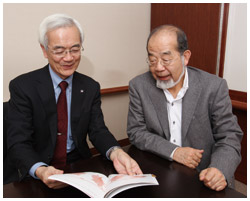
鎌田 たとえば、お母さんが乳がんになった場合、小さな子どもたちにお母さんの病気を伝えたり、お母さんがどんな思いで子どもたちを育ててきたかを伝える「サポートブック」を作っていくときに、乳がんとか死といったことは前面に出ないほうがいい、という意見が出たということですね。田中さん個人としてのお考えはどうだったんですか。
田中 実は私の母が大腸がんで亡くなっていますが、その最期の10カ月を自宅で看取りました。その頃に「サポートブック」の話が出てきたわけです。私は全然知らなかったのですが、母もよく知っている私の娘のアメリカ人の友だちから『マイ・ペアレント・ブック』という書き込み型の本が送られてきたのです。そして、家内と娘はその本をツールとして、末期がんのおばあちゃんとコミュニケーションを取っていたんですね。その本には、私が知らなかった若いときの母の話が、いっぱい書いてあるんです。母が亡くなってから読みましたが、父と知り合ったのはいつで、何回目の見合いだったということなどが、いろいろ書かれていました。読みながら、泣きました(笑)。
鎌田 ご両親の出会いが初めてわかった。
田中 はい。家内にも娘にも、それほど大事なコミュニケーションをしているつもりはなく、私も全然知らなかったのですが、結果的にその本はわが家の宝物になりました。
鎌田 言葉でしゃべりあうだけではなく、書いたものが残されれば、家族の絆はより深まるということを、田中さん自身が実感されていたわけですね。それは「サポートブック」ができる前の話ですよね。
田中 そうです。ですから、その後、「サポートブック」が出来上がったとき、『マイ・ペアレント・ブック』と同じような本ができたなと感じました。サポートブックの生みの親である沖田先生も、あまり生きる・死ぬにこだわらない、家族がお互いを大切に思う気持ちの通じ合う本にしたいというのがコンセプトでしたから、それにふさわしい本になったと思っています。
鎌田 そもそも「サポートブック」は、乳がんのお母さんが不幸にして亡くなったとしても、その子どもたちにお母さんの気持ちを何か残る形にして伝えたい、というところからスタートしたものでしょう。だから、がんとか死とかに触れないわけにはいかない。しかし、議論をしていく中で、そこにはあまり触れないほうがいいということになった。それが結果オーライだったわけですね。
田中 やはり、医療関係者だけでなく、一般の方に議論に加わっていただいたのが良かったと思います。
中国新聞の連載により予期せぬ広がりが出た
鎌田 最近、朝日新聞が「孤族の国」を連載したり、NHKが「無縁社会」を取り上げたりしていますが、人が孤立を深める社会状況の中で「サポートブック」を見て感心しました。大上段に振りかぶって哲学的な話をするよりも、私たちの生活の場の中で、もう1度小さな絆を作り直す、結び直すことが必要ではないかと思いました。日本が直面している「孤族」「無縁」といった問題を解決するためには、みんなの少しずつの努力が必要だと、改めて思います。
田中 私たちはそこまで考えて「サポートブック」を作ったわけではありません。しかし、私たちが「サポートブック」の出版に取り組んでいるときに、地元広島の中国新聞が私たちの取り組みを連載で取り上げてくれたのです。私たちは当初、そんなに長い連載になるとは思ってもいなかったのですが、結果的に第4部まで続きました。
鎌田 中国新聞はときどき優れた連載をやりますよね。
田中 第1部は、がんの親から子どもへメッセージを伝えるというテーマで、6回ほど連載されました。第2部は、子どもががんになったときの親子、兄弟、家族の絆がテーマでした。第3部は子育ての親子の絆がテーマでした。
鎌田 子育てにおける家族の絆がテーマでも、「サポートブック」という切り口で連載が続いたわけですね。
田中 そういうことです。
鎌田 シリーズを担当していた記者は、がんから離れても「サポートブック」のシリーズでいけると思ったんだ。
田中 第4部は介護がテーマでした。お父さん、お母さんを介護している私たちの世代の話に取材が広がりました。私たちが予想もつかない展開でした。そして最後は、お父さんが不況で失業した家族の絆の話にまで広がっていきました。
鎌田 「サポートブック」はそこまで社会性があったということですね。
田中 がんとか死とかの問題をそぎ落としたことから社会的な意味が広がった、と実感しています。
同じカテゴリーの最新記事
- 再発難治性急性リンパ性白血病の画期的治療法 CAR-T細胞療法とは 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (後編)
- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)
- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)
- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)
- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實
- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して
- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている
- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)
- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)



