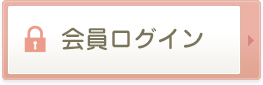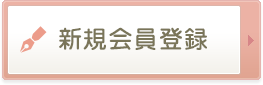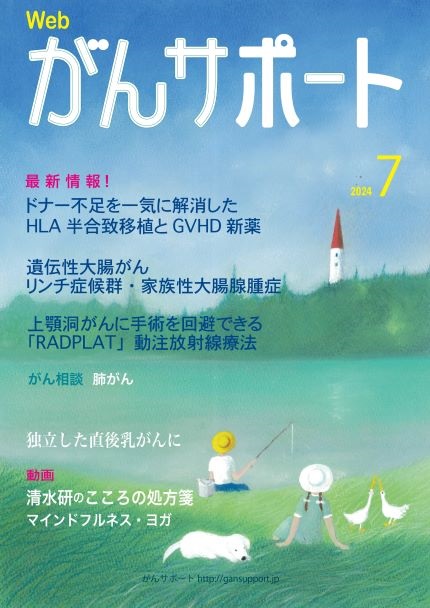震災に負けない特集・災害時にパニックに陥らない7箇条
災害時にがん患者がパニックに陥らないための7箇条
未曾有の大災害。地震、津波、原発の三重苦に苦しめられている人もいる。これら被災者の方々にどう声をかけ、何をすればいいのか、戸惑ってしまう。「がんばれ」「がんばろう」の言葉が広がっているが、被災者たちの、家族を失い、家を失い、町や村を失った境遇に思いをはせれば、そうストレートに言えるものではない。落胆しているところへ鞭を打つ形になるからだ。そうではなく、がんばるのは、被災しなかった、あるいは被災の軽かった私たちだ。私たちこそがんばって彼らにサポートの手をさしのべればいいのだ。それを考える意味で、今回、震災特集を組んだ。被災者の方々、被災されたがん患者さんたち、どうか、震災に負けないでほしいと願って。負けなければ、希望が見えてくる。そしてその先には復興がある。
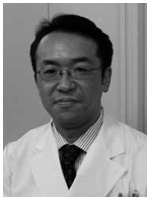 放射線への過剰反応がかえって
放射線への過剰反応がかえってパニック を引き起こすと指摘する
大竹徹さん
今回の大震災のようなことが起こると、巷に流言飛語が飛び交い、風評被害が生じる。 こうしたことに踊らされると、結局、踊らされた者がバカをみる。 心身両面で不安を抱えるがん患者さんがこのようなパニックに陥らないためにはどうしたらよいか。
放射線への過剰反応がパニックをもたらす危険が
自宅や会社の倒壊、流出、さらに原発事故による放射性物質汚染、避難生活につきまとうストレスなど、今回の大震災では被災者の間に多様な悩みが生じている。
心身両面で不安を抱えるがん患者さんの場合、当然のことながら悩みはより深刻さを帯びている。
このような不安を乗り越えるにはこれにどう向き合えばいいのか。震災直後から、被災地の乳がん患者さんの治療に取り組み続けている福島県立医科大学特任教授の大竹徹さんに聞いた。
1.放射線を用いた検査や治療は危険ではない

震災後、もっとも大きな関心を集めているのが原発事故にともなう放射性物質汚染の問題だ。
被災地のがん患者さんには、放射線に被曝したために放射線を用いるX線やCTなどの検査、さらに放射線による治療を危険視する人も少なくない。人体に影響のある被曝量をオーバーするのではないかという不安だ。福島医大では長崎大学と協力して、こうした誤解を解消するために講演活動を続けている。
「たしかに震災2日目に水素爆発が起こってからは、福島市内でも大気中の放射性物質量がわずかですが上昇しています。しかしまだ危険レベルにはほど遠い。4月中旬時点で、原発から30キロ地点でも1年でX線検査を1回受けた程度の被曝量にすぎません。そのことを考えると、検査や治療が危険になることは全く考えられません」
他地域に避難して治療を受けている人は安心して継続したい。
2.放射線への感受性が増えることはない
もう1つ放射線に関連して、多くのがん患者さんが抱いている大きな不安が、1度がんを患った患者さんは、放射線への感受性が高まっているのではないか、ということだ。幸いなことにこれも杞憂に過ぎないと、大竹さんはいう。
「よほど放射線量が高ければ、また事情は違ってくるのかもしれませんが、現在の線量は感受性を云々するレベルではありません。全く心配はありません」
それよりも大竹さんが心配するのは、こうした不安が高じて患者さんの間でパニックが起こらないかということ。過剰な不安が逆に問題を引き起こす危険があるのだ。
3.治療中断が悪化を招くかどうかはがん種による
岩手、宮城、福島と被災地域では、薬剤はもちろん、水、電気の供給が途絶えたために、多くのがん患者さんの治療が中断された。そのことで症状が悪化するのではと不安を持つ患者さんが少なくなかった。しかし、実際の危険度はがん種によって異なっているという。
「たしかに治療中断が症状の進行につながることも考えらます。しかし乳がんの場合、1~3カ月の中断は長い目で見れば、ほとんど結果に影響はない。しかし肺がん、膵がん、血液がんなどはそうはいかない。迅速な手当てが必要です」
自分のがん種、症状を考えた上で冷静に対応したい。
4.病院で治療を受けられなくなったら?
今回の震災では避難によって、それまで通っていた病院で治療を受けられないこともあった。どうやって次の病院を見つければいいのか。
「各学会のホームページをネットで検索すれば、がん種ごとの受け入れ病院リストが見つかります。ネットが使えなくても避難所近くの病院などに連絡して、自分の病状を伝えれば必ず対応してもらえます」
まずは最寄りの病院に連絡をとってみることだ。
5.異常を感じたら保健師や医師に相談する

避難生活は心身両面でストレスが募る。またがん患者さんの場合には、薬剤が補給されないことで発熱、不眠、不安などの症状が顕在化することもある。そんな場合は、とにかく医療関係者に相談するのがよい。
「避難所などでは負傷者に遠慮してか、緊急を要する状態でもそのことを口にしない人もいます。とくにがん患者さんの場合には、免疫力が低下しており、肺炎などの感染症の心配があります。心身に異常を感じたら、遠慮せずに保健師や医師に相談してもらいたいですね」
6.病院や保健師から情報を入手する
たとえばある避難所では近くの薬局で入手できるのに、薬が手に入らないと不満を漏らしていたがん患者さんもいた。
「がん患者さんのように心身に不安のある人は、病院の医師や看護師、避難所なら保健師にも密に連絡して、情報を入手してほしい。それは安心感にもつながります」
7.1人にはしないので安心して
治療中でベッドから動けない患者さんの中には、災害時の逃げ遅れに恐怖を覚える方もいるという。しかし、ここは1つ医療者を信頼しよう。
「私たちは患者さんを決して1人にはしません。安心してもらいたいと思います」
こうした「もしも」の場合の対応は他人事とはいいきれない。いつ、どこで起こるかわからない緊急事に備え、誰もが心しておく必要がある。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性ヨウ素に過敏にならないで!
- 風聞・間違ったイメージに惑わされず、正しい知識に基づいた判断を期待 国立がん研究センター緊急会見「原発事故による健康被害、現時点でほぼ問題なし」
- 大震災で学んだ、弱者の視点に立った新たなまちづくりを 末期がんを乗り越えたその力を今度はまちの復興へ
- ストーマ装具を失った患者たちの不安の声にどう対処したか 被災地のオストメイトたちの危機はこうして解消された!
- がん患者さんはもっと声をあげて! 不安に満ちた被災地のがん患者さんたちの声
- 型にはめた支援ではなく、人と人とのつながりを重視した支援を 未曾有の大災害から考える人間の本質的な生き方とは
- 巨大地震発生!そのときがん患者は、看護師は、医師は
- 原発事故を乗り越え、自然の声を聞け