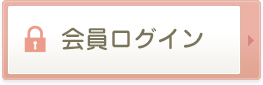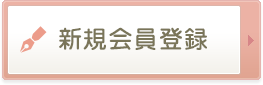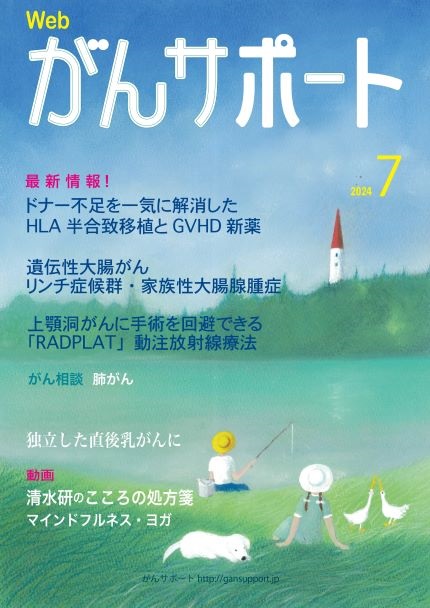治癒力を引き出す がん漢方講座
第13話 乳がんの漢方治療
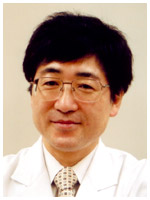
ふくだ かずのり
銀座東京クリニック院長。昭和28年福岡県生まれ。熊本大学医学部卒業。国立がん研究センター研究所で漢方薬を用いたがん予防の研究に取り組むなどし、西洋医学と東洋医学を統合した医療を目指し、実践。
乳がんの漢方治療の注意点
がんの漢方治療は、患者さんの体力や抵抗力や回復力を高め、不快な自覚症状を改善してQOL(生活の質)を良くすることを主な目標としています。
通常は、体力や食欲の状態、自覚症状、がんの進行状況や治療方針により、漢方薬の処方内容を決めることが多く、胃がんや肺がんといったがんの種類はあまり関係ありません。つまり、症状や病状の違いが処方の差になります。
しかし、女性ホルモンのエストロゲンによって増殖が刺激されるがんの場合、注意が必要です。女性ホルモン作用をもった生薬が存在するからです。
乳腺組織や子宮内膜組織はエストロゲンの作用によって増殖が促進されます。それらの組織から発生する乳がんや子宮体がんの中には、エストロゲンによって増殖が促進されるものがあります。エストロゲン依存性の乳がんや子宮体がんの場合、問題となるサプリメントの代表が大豆イソフラボンです。マメ科の生薬の葛根にもイソフラボンが多く含まれています。高麗人参のエストロゲン作用は第6話で解説していますが、米国では乳がん患者は高麗人参の使用は避けるべきだという意見が一般的です。
植物エストロゲンに注意
大豆イソフラボンは、体内でつくられるエストロゲンと構造や働きが似ているため、植物エストロゲン(フィトエストロゲン)と呼ばれています。
エストロゲンの低下で起こる更年期障害や骨粗鬆症を改善する効果が期待され、サプリメントとして注目されるようになりました。しかし最近、食品安全委員会は1日の大豆イソフラボンの摂取量の上限を70~75ミリグラムとし、サプリメントから摂取する場合は1日30ミリグラム以下という指針を出しています。イソフラボンの取り過ぎが、人体においてホルモンバランスに影響する可能性が否定できないからです。
大豆イソフラボンのような植物エストロゲンの摂取はエストロゲン依存性の乳がんの再発を促進する可能性が指摘されています。抗エストロゲン剤を使ったホルモン療法を受けているときは、摂取しないように指導されるのが一般的です。米国では大豆製の食品も控えるべきだという意見もあります。
このような、イソフラボンに対する最近の見解から、エストロゲン依存性の乳がんや子宮体がんの治療中や再発予防を目的とした漢方治療でも、生薬に含まれる植物エストロゲンに対する注意が必要と思われます。
注意が必要なハーブ、生薬
乳がん細胞のエストロゲン依存性の有無は、病理組織検査でホルモン受容体の量を調べることで判別できます。非依存性(エストロゲン受容体がマイナス)の場合は、漢方治療は他のがんと同じです。手術後の回復促進や、抗がん剤や放射線治療の副作用軽減、治療後の再発予防目的で、適切な漢方治療は有用で、生薬のエストロゲン活性への配慮は必要ありません。
依存性(エストロゲン受容体がプラス)の場合には、植物エストロゲンを多く含むハーブや生薬の使用は極力減らしたほうが良いと言えます。ただし、ハーブや生薬中の植物エストロゲンの量に関する情報は乏しいのが実情です。文献的に報告されている生薬として、前述の葛根と高麗人参が良く知られています。漢方処方で使用頻度の高い甘草にもエストロゲン作用があるという報告もあります。日頃食べている野菜の中にも植物エストロゲンが含まれているものがありますので、使っている生薬にエストロゲン活性を持つものがある可能性はあります。
ホルモン依存性の乳がんの治療や再発予防では抗エストロゲン剤が使用されます。これは細胞のエストロゲン受容体を塞いだり、体内のエストロゲンの産生を阻害したりする薬剤で、更年期障害のような症状が副作用として出現します。
大豆イソフラボンは更年期障害に有効ですが、乳がん患者さんには使えません。生薬の中にはエストロゲン作用がなく、更年期障害に効くものがあります。これらをうまく利用すると、ホルモン療法の副作用を軽減しながら、再発予防効果を高めることができます。
エストロゲン作用のない当帰芍薬散、桂枝茯苓丸
当帰は米国でも更年期障害のサプリメントとしてよく知られている生薬ですが、当帰にはエストロゲン作用がないことが証明されています。当帰を含む漢方薬の当帰芍薬散は、卵巣を摘出したマウスの実験で、ストレスを緩和する効果が認められています。更年期の症状に対して、中枢神経に作用して、不安や不眠や抑うつを軽減する効果が示唆されています。
顔面のほてり、のぼせ、発汗といった末梢血管の拡張による自律神経症状に対しては、桃仁、牡丹皮、桂皮が効果があります。桃仁と牡丹皮は血液循環改善や抗炎症の効果があり、桂皮はおだやかな解熱発汗、鎮痛作用があり、これらを含む桂枝茯苓丸は、のぼせのような自律神経症状を緩和します。桂枝茯苓丸にはエストロゲン作用がないことは乳がん細胞を用いた実験で示されています。
当帰芍薬散は当帰・芍薬・*川キュウ、蒼朮(または白朮)・茯苓・沢瀉の6つの生薬から成り、利水作用と補血作用の加わった駆血剤です。貧血やむくみを伴う比較的体力の低下した状態に適します。がん患者では皮膚につやがない、顔色が悪いなどの症状(栄養不良症状)とともに、浮腫・軟便・下痢などの症状が見られる場合に適します。
桂枝茯苓丸は桂皮・茯苓・桃仁・牡丹皮・芍薬の5つの生薬から成り、組織の血液循環を良くし、ダメージを受けた組織の修復を促進する効果があります。このような漢方薬をベースにしながら、さらに症状に合わせた生薬や抗がん作用を持つ生薬などを組み合わせて処方を作ります。
高麗人参や甘草や葛根などのエストロゲン作用が指摘されている生薬は、少しであれば問題はないはずですが、無理に使用しないほうが無難かもしれません。このような注意を守れば、ホルモン療法を妨げずに、副作用を軽減しながら再発予防効果を高める、乳がんの漢方治療が実践できます。
| 桂枝茯苓丸 | 桂皮 | クスノキ科のニッケイ類の樹皮。血行を促進して体を温める 解熱発汗・鎮静・末梢血管拡張・抗菌作用などが認められている | |
| 桃仁 | バラ科のモモの種子。血液循環改善・抗炎症作用・鎮痛作用を有し、とくに炎症による 充血や血行障害による疼痛を軽減する | ||
| 牡丹皮 | ボタン科のボタンの根皮。炎症に附随する血液循環障害を改善する 鎮痛・鎮静作用があり、タンニンを多く含み強い抗酸化作用を持つ | ||
| 当帰芍薬散 | 芍薬 | ボタン科のシャクヤクの根。抗炎症作用と血液循環改善作用、補血作用を持つ 骨格筋や平滑筋の痙攣を緩和して鎮痛する | |
| 茯苓 | サルノコシカケ科のマツホドの菌核。胃腸虚弱や浮腫を改善する 精神安定に働き不安感や不眠を軽減。多糖成分に免疫増強作用がある | ||
| 当帰 | セリ科のトウキの根。血管拡張・血行促進によって体を温める 造血機能を高める補血作用を持つ。皮膚や粘膜の潰瘍の治りを促進する | ||
| 川キュウ | セリ科のセンキュウの根茎。血行を促進して体を温める。憂うつ・抑うつを改善する 鎮痛作用があり頭痛・腹痛・筋肉痛などにも効く | ||
| 蒼朮 | キク科のホソバオケラ、シナオケラの根茎。消化管機能を高め、浮腫や疼痛を軽減する 効果や、免疫増強作用がある | ||
| 沢瀉 | オモダカ科のサジオモダカの塊茎。利水作用と抗炎症作用がある 多糖類には免疫増強作用が認められている |
*川キュウ:キュウは草かんむりに弓
同じカテゴリーの最新記事
- がん治療中の食欲不振やしびれ、つらい副作用には漢方薬を使ってみよう!
- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること
- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が
- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療
- エビデンスの認められた漢方薬をがん患者さんへ届ける!
- 医師や認定薬剤師に相談して、正しい漢方薬の使い方を
- 手術や抗がん薬投与前からの漢方薬服用も有効
- 婦人科がん化学療法における食欲不振に 六君子湯が効果発揮
- 半夏瀉心湯で 乳がん治療薬による下痢が軽減
- 「元気な体で延命」を目指す癌研有明病院・漢方サポート外来 漢方薬を使うと、がん治療で弱った患者が、元気になる