大腸がんのペプチド・ワクチン療法
変装するがん細胞を追いつめ、攻撃するワクチン療法
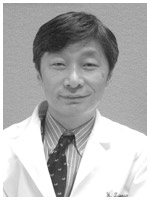 東京大学医科学研究所外科教授の
東京大学医科学研究所外科教授の田原秀晃さん
人間の体にもともと備わっている免疫の力を利用して、がんをたたく。この免疫療法は、がん治療の分野で、手術、放射線、抗がん剤に次ぐ、第4の治療法として、昔から大きな期待を寄せられてきた。
しかし、これまでの免疫療法は、免疫賦活剤を皮切りに、インターフェロン、ミサイル療法、養子免疫療法などと呼ばれる療法が次々と生まれたが、その効果が科学的に証明できずに今日に至っているものも多い。
なぜか。それは、簡単に言えば、これまでのどの免疫療法も、がんを攻撃する免疫を有効に誘導できなかったからにほかならない。
では、どうすればがんを攻撃する免疫を有効に誘導することができるのか。その前に、がんを攻撃する免疫とはどんなものなのか。実は、その答えを探し出すプロセスが免疫療法の研究がたどってきた歴史でもあったのだ。そしてその中から、ついに一筋の光明を見つけ出した。それがペプチドを用いるがんのワクチン療法である。ワクチン療法でこのペプチドが投与されれば、がんに対する免疫の主役であるT細胞(細胞障害性T細胞ともいう)が誘導され、T細胞ががんを攻撃していくことが明らかになったのである。

東京大学医科学研究所(港区白金台)
ペプチドを用いるワクチン療法では、悪性の皮膚がんとして知られるメラノーマ(悪性黒色腫)で先行し、すでにいくつか成果も上がっているが、東京大学医科学研究所教授の田原秀晃さんらの研究グループでは、大腸がんでのペプチド・ワクチンの探索に挑み、ついにペプチドの合成に成功。昨年からそのペプチドを用いたワクチン療法の臨床試験をスタートさせている。安全性などを確かめるための第1相の臨床試験である。
日本では1年間に約8万4000人が大腸がんと診断され、約3万5000人が大腸がんで死亡している。その数は年を追うごとに増え、罹患者数は胃がんに次いで第2位、死亡者数は肺がんに次いで第2位を占めるに至っている。
大腸がんは肺がんや膵臓がんなどに比べて比較的おとなしいがんといわれるが、進行・再発したものに対しては治療法が尽きてしまうことが少なくない。だからより強力な、あるいはより患者にやさしい新しい治療法が求められているのである。
では、大腸がんのペプチド・ワクチン療法とは、どんな療法なのか、田原さんはこう説明する。
「今回のワクチンは、大腸がんの抗原から取り出したペプチドです。使用するワクチンは2種類。患者の白血球の型(HLA)によって分かれています。日本人では約6割の人がA2402というHLA型を持っています。もう1つは、A0201というHLA型で、約2割の人が持っています。その両者で8割の人をカバーできます。それでこの2種類のワクチンを作り、これまで2402というタイプのワクチンを6人に投与し、0201というタイプのワクチンを1人に投与しました」
リンパ球、なかんずくT細胞ががん細胞かどうかを識別する目印を抗原というが、その抗原に、T細胞を増やすための補助剤を加えたものがワクチンである。そのワクチンを1回1ミリグラム、2週間ごとに計4回、脇の下か、太ももの鼠径部の皮内へ注射する。脇の下や鼠径部に注射するのは、リンパ球の多く集まった部分に注入し刺激をしてリンパ球をより多く増やすためである。
がん細胞を特定するエピトープ・ペプチド
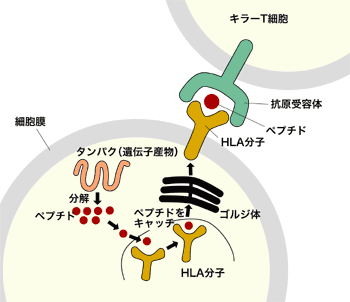
そもそもがんの治療にワクチンを活用できるのではないかという考えが出されたのは19世紀に始まる。
「米国メモリアル病院のウィリアム・B・コーレー医師が丹毒を患った骨軟部腫瘍の患者の中に、自然に治った症例を見出したことから始まりました」(田原さん)
丹毒は連鎖球菌による高熱を伴う皮膚の激烈な炎症で、コーレー医師は培養した連鎖球菌を骨軟部腫瘍の患者に注射したところ、約40パーセントの患者に治療効果が得られた。その後、連鎖球菌を弱毒化するため、異なる別の細菌を混ぜ合わせた混合ワクチン「コーレー・トキシン」をつくった。しかし、当時は免疫についての科学的研究の蓄積が乏しかったことから、コーレー・トキシンによるがんの縮小や消失のメカニズムが十分に説明できなかった。
このように細菌やウイルスを弱毒化したり無毒化するのがワクチンの手法で、がんのワクチンでは、それに代わってがん細胞をすりつぶして作るということが行われてきた。しかし、いずれもはかばかしい成果が得られなかった。それは、前にも述べたとおり、がん細胞に照準をあわせた免疫力の誘導に成功しなかったからである。
ところが、1990年代に入るとT細胞ががん細胞かどうかを識別する、そのメカニズムがようやく解明され、がんワクチン療法の科学的発展の端緒が切り拓かれた。
「実は、T細胞ががん細胞を判別する抗原(目印)は、がん細胞のつくる特定のタンパクの一部とHLAが一体となったものだったのです」(田原さん)
HLAは白血球の型を示すタンパクとして発見されたが、個人個人の細胞のタイプを示すタンパクでもある。現在、200種類以上のHLA型が確認されている。
一方、がん細胞のつくる特定のタンパクは、アミノ酸が長い鎖のように連なったものから構成されており、その中の一部(8~11個)のごく短いアミノ酸がつながったものをペプチド(タンパク質の破片)と呼ぶ。
「このペプチドががん細胞かどうかを識別する目印なのですが、ペプチドはがん細胞の中のHLAというタンパクの上に乗せられて細胞膜の表面に浮き出てくるため、ペプチドとHLAの一体となったものが抗原となっているのです」(田原さん)
つまり、HLAを船とするなら、ペプチドはその上に立つ帆で、リンパ球のT細胞はこの帆を見つけ出して攻撃するというわけである。
「そのペプチドの中でも、とくにT細胞ががん細胞かどうかを識別している部分が1991年に発見されました。これはエピトープ・ペプチドと呼ばれますが、ベルギーのブーン博士らによってメラノーマの抗原探しの研究から得られたものです。これはがん免疫療法においては画期的な成果でした」(田原さん)
それまでのがん免疫療法はがん抗原を特定できなかったことから、むやみやたらに免疫反応を起こしたり、それを強めたりすることに力が注がれていた。しかし、このエピトープ・ペプチドの発見によって、がん細胞に照準を絞って攻撃する免疫を誘導させる方法が突き止められたのである。
同じカテゴリーの最新記事
- 「積極的ポリープ摘除術」で大腸全摘の回避を目指す! 代表的な遺伝性大腸がん——リンチ症候群と家族性大腸腺腫症
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法



