抗がん剤の使用方法に関する基本的な考え方
抗がん剤の投与量、投与間隔をきちんと守る
投与量を減らしたり投与間隔を延ばしたりすることはいいことか

「先生、吐き気がとても激しくて苦しいんです。この治療、もう少しなんとか和らげてもらえませんでしょうか」
診療室でこう患者さんに訴えられた主治医は、少し考えて、答えます。
「いいでしょう。それでは今回から抗がん剤の投与量を少し減らしましょう」
医師の言葉に患者さんは安堵の表情を見せます。最近、がんの診療現場でよく見られる光景です。
抗がん剤の点滴を行うときは、前もって血液検査をします。その検査の結果、白血球数が2000以下に下がっていたりすると、担当医が患者さんにこう告げることもよくあります。
「白血球がちょっと下がりすぎですねぇ。体に危険なので今日のところは抗がん剤の治療は見合わせておきましょう。また1週間後に来てください」
「せっかく会社を休んで来たのですから、何とかならないのでしょうか」
「白血球が下がりすぎなので、残念ながら今日は無理ですね」
どちらのケースも、一見患者さんのためを思ったいい治療のように見えます。
しかし、実は、そうではないのです。このように抗がん剤の用量を下げたり、投与間隔を引き延ばしたりすることは、がんの種類にもよりますが、患者さんにとって、あまり有益ではなく、かえって、不利益な治療になる可能性が示唆されてきているのです。もっとも、このことをきちんと認識している人は、患者さんはもとより、医師をはじめとする医療関係者の間でも、あまり多くないのが現状ではないでしょうか。
その点を明らかにした明白な証拠(エビデンス)も出ています。まずは、それを紹介しましょう。
決められた用量を計画どおり使用することの重要性
リンパ節に転移のある乳がんに対して、根治的乳房切除術を受けた386名の患者さんを、再発防止を目的とした術後補助療法として抗がん剤治療を受けるグループと、受けないグループに分け、その後に生存した患者さんの割合を20年にもわたり観察した結果が報告されています。抗がん剤治療は、*CMFと呼ばれる3種類の抗がん剤を併用して投与する治療で、月毎に12サイクル続けました。
無病生存率と全生存率]
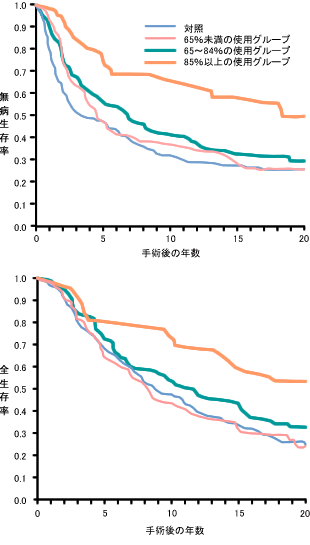
それによれば、術後補助療法として抗がん剤治療を受けたグループのほうが、治療を受けなかったグループに比べ、がんが再発することなく生存された患者さんの割合(無病生存率、あるいは無再発生存率)も、がん再発の有無には関係なく生存された患者さんの割合(全生存率)も、明らかに高率でした。この結果から術後補助療法として抗がん剤治療を行うことの有効性が確かめられました。
また、抗がん剤の使用量については、「予定された用量を予定どおり投与された場合を100パーセントとした場合」その85パーセント以上を使用できたグループ、65~84パーセントを使用できたグループ、さらに65パーセント未満のグループという3つのグループで、抗がん剤治療の効果が比較・検討されました。
その結果、ほぼ決められた用量どおりにきちんと使用したグループほど、無病生存率や全生存率が高いことも明らかにされました(図1)。
この結果は、転移のある高リスクがん患者さんにおいて、手術後の早い段階から補助療法として抗がん剤治療を行うことが有効であると共に、抗がん剤治療はあくまで決められた用量をきちんと計画どおりに使用することが重要であることを示唆しています。
したがって、ある種のがんにおいての抗がん剤治療では、安易にその使用量を減らしたり、投与間隔を延ばしたりすることは、副作用を招かないかもしれないものの、その代わり患者さんの生存期間を縮めてしまうことになりかねないというわけです。その際に重要なことは、決められた用量、投与間隔どおりにきちんと使用すること、これが抗がん剤治療の基本なのです。
*CMF=エンドキサン(シクロフォスファミド)、メソトレキセート(メトトレキサート)、5-FU(フルオロウラシル)の3剤併用療法
抗がん剤治療を確実に行うためには
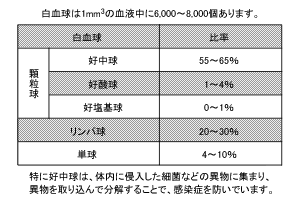
[図3:好中球減少程度/期間と重症感染症のリスクとの関係]
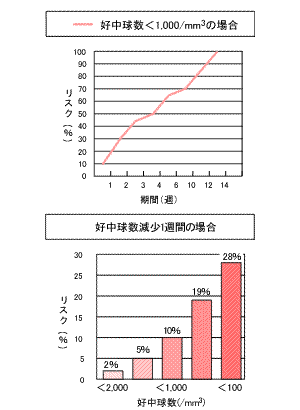
しかしながら、そうはいっても、抗がん剤治療を確実に行うには大きな壁があります。それは、抗がん剤には程度の差こそあるものの、必ずと言ってよいほど、副作用を引き起こす恐れがあるということです。
ただし、抗がん剤の副作用については、その対策がかなり確立されており、それをきちんと実行しさえすれば抗がん剤治療はそれほど苦しまずに乗り切っていくことができます。
たとえば副作用の主要なものでは、吐き気・嘔吐があります。吐き気・嘔吐による苦しさで抗がん剤治療が続けられないという患者さんがいたことは事実です。しかし、それはもう過去のことで、現在では吐き気や嘔吐を止める有効な薬が開発されており、その吐き気対策をきちんと行えば大部分は抑えられます。
もう1つは、血液中の成分の1つである白血球、その中の、とりわけ好中球という種類を減少させる副作用です。血液中の好中球が減少(好中球減少症)すると、細菌などに対する抵抗性が低下し、感染しやすくなります。感染症を起こす危険性は、好中球の減少の程度とその持続期間に比例して増加することも知られています。
たとえば、白血病の患者さんにおいて、抗がん剤治療後の感染症発症の危険性は、好中球の最低値が1立方ミリメートル当たり1000未満の場合、その期間が長くなればなるほど、また、好中球が減少している期間が一定であれば、好中球の最低値が低いほど、重度の感染症を発症する危険性が高くなると報告されています(図2、3)。
そこで、冒頭で述べたように、抗がん剤治療を受けるために病院に行ったにもかかわらず、事前の血液検査で「好中球が減少していますので今回の治療は見合わせましょう」と言われかねません。そこで、そうならないように好中球減少症を予防する必要があります。
減少した好中球を増加させる造血因子である、顆粒球コロニー刺激因子(granulocyte colony stimulating factor :G-CSF)とよばれる薬の使用が必要となります。
わが国でもG-CSF製剤は使用できます。このようなG-CSF製剤を使用することで、好中球減少症からの回復が早められ、予定された量の抗がん剤治療を予定通り行うことが可能になるというわけです。
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 「過剰検査・過剰治療の抑制」と「薬物療法の進歩」 甲状腺がん治療で知っておきたい2つのこと



