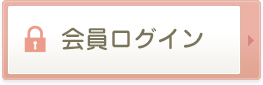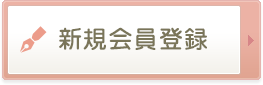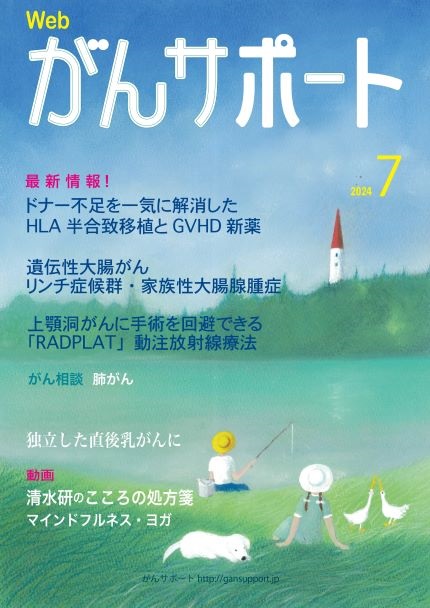慢性骨髄性白血病~新薬の登場で完全治癒への期待がふくらむ
新しい分子標的治療薬がもたらすインパクト

CMLの最終ゴールは治癒をめざすことと語る
高橋さん
慢性骨髄性白血病(CML)の治療や予後は、グリベックの開発によって一変しました。
そして最近、これをさらに進化させたタシグナ、スプリセルという2つの新薬が登場し、完全治癒へ期待を大きくふくらませています。
異常な染色体の発現が引き金になる病気
白血病は、白血球や赤血球などのもとになる造血幹細胞ががん化し、未成熟な白血球(白血病細胞)が、骨髄や血液中で無制限に増えていく病気です。
慢性骨髄性白血病(CML(*))はその1つで「フィラデルフィア染色体」と呼ばれる異常な染色体が生じることで起こります。ちなみに、染色体は生命の設計図であるDNAがまとまったもの。
ヒトには22対の常染色体と、1対の性染色体の計23対あり、常染色体には1~22まで番号が振られています。
CMLでは、その中の9番と22番の染色体の一部が互いに入れ替わって、異常な染色体が作られます。これがフィラデルフィア染色体です。
では、この異常染色体ができるとどうなるのか。秋田大学医学部血液・腎臓・膠原病内科講師の高橋直人さんは次のように説明します。
「新たに生じたフィラデルフィア染色体の上で、22番染色体由来のBCR遺伝子と9番染色体由来のABL遺伝子がくっついて、正常ではみられないBCR-ABLという異常な融合遺伝子が出来上がります。このBCR-ABL融合遺伝子からBcr-Abl蛋白が作られ、そこにATPというエネルギーのもとになる物質が結合すると『白血病細胞を作れ』という指令が出て、白血病細胞が限りなく増殖していくのです。つまり、CMLはBcr-Abl病であるといえるのです」
*CML=慢性骨髄性白血病(chronic myelogenous leukemia)
検診で発見されるのが増えている
もっとも、BCR-ABL融合遺伝子ができたからといって、すぐCMLが発症するわけではありません。フィラデルフィア染色体を持った1個の細胞が1012個(10の12乗個=10兆個)に増えるには約6年かかるといわれます。ですから初期はほとんど無症状でゆっくり進行します。この時期が「慢性期」で、まだ白血病細胞も少なく、抗がん剤でコントロールできます。その後「移行期」(6~8カ月)へと進み、やがて「急性転化」を起こし、急性白血病のような症状をきたすようになります。こうなると、治療成績は極めて悪くなります。
「したがって、CMLは慢性期から急性転化させないよう、慢性期の段階で食い止めることが重要です。しかし無症状ということが災いして、以前は悪化してから受診する患者さんがほとんどでした。ところが最近は、健康診断や人間ドックなどで、白血球数の異常を指摘され、精密検査を受けてCMLと診断されるケースが増えています」と高橋さん。
グリベックが治療を変えた
少し前まで、CMLは白血病の中でも、とくに予後が不良の病気でした。多くの抗がん剤を組み合わせてもコントロールが難しく、治癒を目指すには造血幹細胞移植(骨髄移植)を行うしか手がなかったのです。切り札と目されたインターフェロンも、治療成績を好転させるところまではいきませんでした。
こうした状況を一変させたのが、2001年に登場した「グリベック」(一般名イマチニブ)という薬剤です。それまでの抗がん剤は、細胞分裂を阻止してがんを叩こうというものが主流でした。しかし正常な細胞の分裂も止めるので、副作用が強く出てしまいます。
グリベックは、これとはまったく違った発想から生まれた薬です。先に触れたように、CMLはBCR-ABL遺伝子が作る異常な蛋白(Bcr-Abl蛋白)が、白血病細胞を無制限に増加させて、がんを起こすと考えられています。つまり、CMLはBcr-Abl病といえます。そこで、Bcr-Abl蛋白を標的とし、その働きを邪魔すれば、白血病細胞は無秩序な増殖を止め、本来の姿に戻るのではないか。グリベックはこうした考えに基づいて開発されたものです。ある特定の分子に結合するところから分子標的治療薬と呼ばれます。
治療現場で臨床応用されると、グリベックは期待以上の効果を発揮しました。同薬を服用した場合、9割近い患者さんに細胞遺伝学的完全寛解が認められました。つまり、CMLの原因であるフィラデルフィア染色体が消えたのです。グリベックが登場する前の標準治療であるインターフェロンを用いた治療では、細胞遺伝学的完全寛解が5~20パーセントに過ぎませんでしたから、これは驚異的な数字でした。
高橋さんも「治療が一変した。この武器を使えば、CMLを克服できるという手ごたえを感じました」
と当時を振り返ります。
第2世代の新薬が次のドアを開く
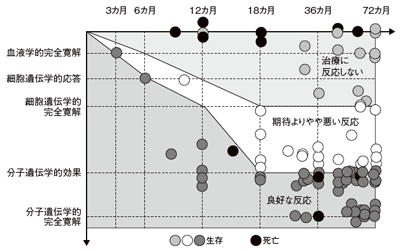
"治癒させるには造血幹細胞移植しか手はない"といわれたCMLの予後を劇的に改善したグリベックは文字通り"奇跡の薬"でしたが、使い続けているうちに課題も浮かび上がってきました。
高橋さんは、秋田県内の100人の患者さんを対象に、グリベックを投与した効果を調べていますが、それによると、 6年間の治療で60パーセントの患者さんは治療が奏効しましたが、20パーセントは今一歩、そして20パーセントは改善が認められなかったのです(図1)。
なぜ、20パーセントの患者さんで効果が得られなかったのか。分析すると、半数の患者さんは副作用で薬を十分飲めなくなったことが、残り半数はBCRABL遺伝子に突然変異が起こってグリベックが入り込めなくなったり、BCR-ABL遺伝子以外のがん遺伝子が重なって出てきたことなどが原因とわかりました。
こうしたグリベックの弱点は、高橋さんだけでなく、CMLに関わる多くの医師や研究者が指摘しています。そこで、これを克服するための研究が続けられ、新たに開発されたのが「タシグナ」(一般名ニロチニブ)、「スプリセル」(一般名ダサチニブ)という第2世代の2つの分子標的治療薬です。
*ELN=欧米、オーストラリアの血液専門家19名によって組織される慢性骨髄性白血病の研究組織(European Leukemia Net)
同じカテゴリーの最新記事
- 従来の治療薬と作用機序が異なり新しい選択肢として期待 慢性骨髄性白血病に6番目の治療薬が登場
- 第3世代の新薬も登場! さらに進化する慢性骨髄性白血病の最新治療
- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~
- 治療薬に新たにボスチニブが加わる 慢性骨髄性白血病の最新治療
- 慢性骨髄性白血病 治療薬を飲み続けなくてもよい未来
- 休薬してよいかどうかの臨床試験も始まり、将来的には完治できる可能性も! 効果の高い第2世代薬が登場!慢性骨髄性白血病の治療薬をどう選ぶか
- 一生薬を飲み続けなくてもいい時代が来るかもしれない!? 完全治癒を目指して慢性骨髄性白血病の最新治療
- グリベックの10倍以上の効力を持つ新しい分子標的薬も近々承認 分子標的薬の登場で大きく変わる白血病治療
- 渡辺亨チームが医療サポートする:慢性骨髄性白血病編