分子標的薬と抗がん剤併用による大腸がん休眠療法
何を投与するかよりも、どのくらいの量を投与するかが決めて
 金沢大学がん研究所助教授の
金沢大学がん研究所助教授の高橋豊さん
海の向こうでは、すでにアバスチンとアービタックスという分子標的薬が進行再発大腸がんの標準治療薬になっている。その足音がひたひたとこちらにも近づいている。その分子標的薬の視座から今日の抗がん剤治療をのぞき見ると、そこから何が浮かび上がってくるか。血管新生阻害剤の先駆けである金沢大学がん研究所の高橋豊さんに聞く。
血管新生阻害剤の第1号
大腸がんの抗がん剤治療の分野で、ただ今、分子標的薬のアバスチン(一般名ベバシズマブ)という薬が脚光を浴びている。中外製薬が、ついにこの4月、予想よりも大幅に早めてこの新薬の製造販売承認を厚生労働省に申請したからだ。
分子標的薬は、ご存知の方も多いと思うが、すでに他のがんでは医療現場で使用されており、大きな成果を上げている反面、問題点も浮かび上がっている。乳がんのハーセプチンや慢性骨髄性白血病のグリベック、肺がんのイレッサなどで、イレッサでは重篤な間質性肺炎により死亡者が続出して社会問題になったことはまだ記憶に新しいところだ。
ところが、大腸がんでは分子標的薬が登場するのは、これが初めて。それだけではない。アバスチンという薬は、これまでの分子標的薬とは薬のコンセプトからして大きく異なっている。がんそのものをターゲットにするのではなく、がんが生み出す血管を標的にしたもので、血管新生阻害剤と呼ばれる。
がんが大きくなるには、自ら血管をつくる因子を出し、近くの血管から新しい血管を引っ張り込む必要がある。そこから栄養を補給し、それを糧にどんどん大きくなるのだ。そこで、新しい血管、血管新生をつくらせないように邪魔をしてやれば、がんは大きくなれないのではないか。そうした発想で生まれたのが血管新生阻害剤で、これは開発途上から世界で注目されていた。その第1号がアバスチンというわけだ。
このアバスチンは、すでに米国では進行再発大腸がんの標準治療薬の1つになっている。しかも最近は、大腸がんを皮切りに、乳がんや肺がんでも効果が証明され、さらには腎臓がん、前立腺がんなどへと次々に広がる模様で、やがては分子標的薬の代表的な薬に成長する可能性があるとされる。日本の医薬品業界でも、抗がん剤史上初の1000億円を超える売上げの商品になるとささやかれているほどだ。
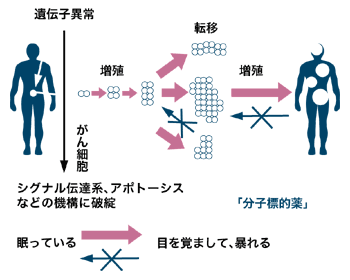
増殖抑制効果に着目
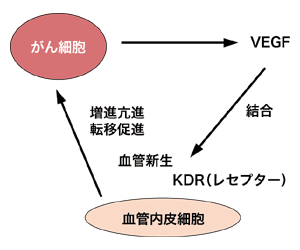
[アバスチンの臨床試験の結果]
| IFL/プラシーボ | IFL/アバスチン | |
|---|---|---|
| 症例数 | 412 | 403 |
| 50%生存期間(月) | 15.6 | 20.3 |
| 増殖抑制期間(月) | 6.24 | 10.6 |
| 奏効率(%) | 35 | 45 |
| 出血(グレード3/4)(%) | 2.5 | 3.1 |
| 蛋白尿(グレード3)(%) | 0.8 | 0.8 |
| 高血圧(グレード3)(%) | 2.3 | 10.9 |
実は、このアバスチンの研究開発、製薬化に大きく貢献した日本人医師がいる。金沢大学がん研究所腫瘍外科助教授の高橋豊さんだ。高橋さんは、「がんの休眠療法」を提唱したことで知られるが、何を隠そう、その提唱の元になったものこそこの血管新生阻害剤の研究であったのである。
アバスチンは、血管新生因子の中でも最も有名なVEGFと呼ばれる因子(血管内皮増殖因子)を中和する抗体である。このVEGF自体は、米国・ジェネンテック社のフェラーラ博士が発見しているが、高橋さんは、このVEGFが大腸がんの血管新生、ひいては大腸がんの増殖や転移に大きな影響をおよぼすことを見出し、それを証明する初の論文を発表した。1995年のことだ。
この論文は、その後600を超える論文に引用され、大腸がんにおけるVEGFの意義が確立されることになった。ジェネンテック社では、この結果を受け、大腸がんをはじめとする各種がんでVEGF抗体を用いた臨床試験を開始し、アバスチンの誕生へとこぎつけたというわけだ。
一方、高橋さんのほうは、血管新生阻害剤の「がんの増殖を抑制する効果」に着目し、そこから「がん休眠療法」を提唱するに至る。
「それまで抗がん剤の世界では、がんが縮小しなければ延命しないと言われてきた。これに対して私は、たとえがんが縮小しなくても、増殖を止めれば患者は延命できることを証明しました。しかし、当時、血管新生阻害剤の実用化はすぐには無理でして、そこで、この血管新生阻害剤を使わずとも、抗がん剤でそのことができるのではないかと考え、がんの縮小を目指さない、増殖を抑える方法をすべてひっくるめて休眠療法と呼んだのです」
「大きさが変わらない」が多い
この抗がん剤を用いたがん休眠療法については後述するが、高橋さんによれば、血管新生阻害剤、そして分子標的薬の特徴こそがん治療の本当の姿であり、がん休眠療法はその分子標的薬の戦略を代弁したものだという。なぜなら、分子標的薬は、がんの本質的な原因である増殖を果てしなく続ける分子の働きを抑え、増殖を抑える薬だからだと。
ポイントは増殖抑制。その代表的な例がGIST(消化管間質腫瘍)に対するグリベックの効果に見られる。
GISTは、まれな病気だが、胃腸の壁の中に腫瘍ができるため発見されにくく、発見されたときはかなり進行しているケースがしばしば。そのため、治療が極めて難しく、1年で8割以上が死亡するのが普通だった。しかし、このグリベックの出現により患者は2年、3年と生き延びるようになったという。
「グリベックを服用しても治る人はほとんどいないんです。がんが小さくなる人もあまりいない。がんの大きさが変わらないのが一番多く、それで生存期間が延びたのです。なかでも注目すべきは、がんが小さくなった例と変わらなかった例とを比べて、生存期間に差がなかったことです」
しかし、このことに疑問を感じたフランスのグループでは、がんの大きさが変わらないというのはがんが死滅しているためではないかと考え、そこで、変わらなかった場合にはグリベックの投与を中止するという臨床試験が行われた。ところが、予想に反して、中止した途端にがんが再び増大してくるという結果になった。つまり、がんの大きさが変わらないということには、増殖抑制という点で大きな意味があったというわけだ。
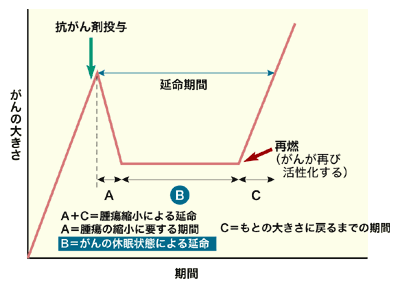
同じカテゴリーの最新記事
- 「積極的ポリープ摘除術」で大腸全摘の回避を目指す! 代表的な遺伝性大腸がん——リンチ症候群と家族性大腸腺腫症
- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法
- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線
- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!
- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法



