自分がキレイになると、まわりの反応が違うんです 自らの抗がん剤体験をベースに、女ざかりの乳がん患者がキレイでいるためのバイブルを作った美容ジャーナリスト・山崎多賀子さん

1960年大阪生まれ。会社員、女性誌の編集者を経てフリーライター、美容ジャーナリストに。スキンケアやメイクアップにとどまらず、メンタル・健康医療分野まで美容に関わる幅広い分野で長年にわたり取材を続ける。女性誌を中心に美容記事や美容ルポルタージュ、エッセイなどを手がけている。
美容ジャーナリストの山崎多賀子さんが著した『キレイに治す乳がん宣言!』という本は画期的な一冊だ。一言でいえば、この本は「キレイであること」に徹頭徹尾こだわった本だ。前半部では患者でもある彼女がキレイでありたい本音を実況中継風に語り、後半部では、キレイであるためのハウツーや知識を自分でモデルやインタビュアーをこなしながら巧みに紹介している。そのエネルギーには驚嘆するほかない。今回はその山崎さんのお話を軸にしながら「女ざかりの乳がん患者にとってのQOL(生活の質)」という問題を考えてみたい。
悪い例の中のラッキーなケース
山崎さんは最初から乳がんに高い関心を持っていたわけではない。むしろ逆で健康に自信があったこともあって、ここ10年間1度も女性疾患系の検診を受けたことがなかった。
乳がんが見つかったのも、ほかの目的で検診を受けてみようと思ったのがきっかけだった。
「10年ぶりに検診を受けたのは乳がんではなく子宮の病気が気になったからです。
マンモグラフィは検診を受けた婦人科クリニックの検診に付いていたので、それでたまたま受けることになり、引っかかったんです。ですから私の場合、ちゃんと検査にも行かず、放っておいた悪い例の中のラッキーなケースなんです(笑)」
最初の検診ですぐにがんが見つかったわけではなかった。早期の見つけにくいタイプの乳がんだったため、クリニックからはマンモグラフィで気になることがあるので、乳腺外科の医師が来る日に再来院するように連絡があったが、いくら触ってもしこりのようなものはまったくなかったので、彼女自身は乳腺症ぐらいに考えていたようだ。
「私の場合、乳管に沿ってブドウの枝葉状にゆっくり進むタイプだったんです。がんによって死んだ細胞が石灰化するんですが、石灰化が乳房の中に点在していることがわかり、細胞を採取して調べることになりました。あとで最初に見ていただいた医師に取材で確認すると、私のマンモグラフィの画像は明らかに乳がん特有の画像だったらしく、良性の中に悪性(がん)が混じっているという感じだったので、なかなか見つからなかったんですね。
その後紹介された病院で針生検をやって、それでも良性で、マンモトームをやってたくさん組織を採取して調べたらその中にいたという感じでした」
乳首へのこだわり
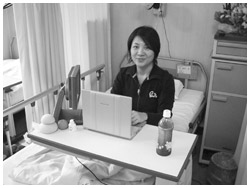
診断は非浸潤性の乳管がん。早期なので患部を切除すれば転移の怖れもほとんどなく、乳房を温存できるはず。しかし、彼女の場合はそういかなかった。石灰化の範囲が広がっていたため全摘にならざるを得ないと病院の医師から言われたのだ。
そのこと自体、受け入れるのにしばらく時間がかかったが、彼女は納得し乳房温存は諦めた。しかし、乳房の正面にメスを入れる手術の方式には抵抗を覚えた。
「結果的にはがんを見つけてくれた病院ではなく、聖マリアンナ医大病院で手術を受けることに決めました。最初の病院で手術を担当する外科の先生から、乳房の正面を切り、万全を期すために乳首も取る手術になると説明を受けたんです。とても親切に応対してくださる医師で、乳房再建の話の際に術後の写真を見せていただいたのですが、片胸だけ乳首がなく傷跡だけが目立つ写真はさすがにショックでした。
できることなら乳首は残したいし、乳房再建もできるだけ早くしたかったので、知り合いの形成外科クリニックを開いている女性医師に相談したんですね。そしたら聖マリアンナ医大では全摘手術でも乳房の脇から切開する方式もやっていて、手術の際の検査で乳首にがん細胞がない可能性が高ければ残すことは可能だという話でした。
しかも、その医師は聖マリアンナ医大で再建手術も行っていて、同時に再建手術をすることも可能と知り、悩んだ末病院を変わることに決めました。インプラントを再建手術は2段階に分けて行われるのが一般的ですが、私はてっきり乳がんの手術と同時に再建するものとばかり思っていました。」
彼女が病気のことより、普通に見える乳房を取り戻すことに意識がいったのは、その形成外科の医師のクリニックで、自分が受けることになる手術を経験した人たちを紹介してもらい、彼女たちから直に術後の経過や、傷跡の現状などを聞いたり見たりできたことも大きかったようだ。
数週間前~数カ月前に手術を受けた同じ年代の女性たちが見せてくれた傷跡は、想像していたよりきれいで、術後1カ月経過した人の切開跡などはブラジャーの跡のほうがずっと目立つほどだった。
山崎さんが手術を受けたのは2005年12月27日。雑誌の連載や、特集企画の取材がかなりあって大変だったようだが、何とかこなして聖マリアンナ医大病院に入院することができた。
しかし、そんな慌ただしい時間が過ぎていく中でも、彼女はキレイでいることへのこだわりを早くも見せて、入院前、ヘアをおしゃれなショートカットにし、まつげにパーマをかけている。それだけでなく、親しいカメラマンに頼んでセミヌードの撮影まで行っている。
「親しい編集者、カメラマンと3人で飲んでいるとき、その場のノリで『私の胸を撮って』と言ったら、実現しちゃったという感じです。失う前に残しておきたかったんです」
本当はスタート地点だったゴール
手術は無事終了した。しかし、それはゴールではなくスタートだった。病理検査で浸潤個所が多数あることが判ったのだ。
事前に主治医からその可能性があることを聞かされていたが、検査で浸潤部は見つからなかったので、その可能性はないと信じていたのだ。
「1つ1つは小さかったんですが、たくさんあるということで、主治医の先生からは、ホルモン療法、できれば抗がん剤治療をやるように勧められました。
ただ抗がん剤に関しては悪いイメージがあったし、自分ではそれを使わなければならないくらいがんが進んでいると思っていなかったので、抗がん剤なんて有り得ないという気持ちでした。ホルモン療法に関しても、それによって閉経させる不自然さを考えると、絶対イヤでした」
同じカテゴリーの最新記事
- 人生、悩み過ぎるには短すぎてもったいない 〝違いがわかる男〟宮本亞門が前立腺がんになって
- またステージに立つという自分の夢もあきらめない 急性骨髄性白血病を乗り越えた岡村孝子さん
- がん患者や家族に「マギーズ東京」のような施設を神奈川・藤沢に 乳がん発覚の恩人は健康バラエティTV番組 歌手・麻倉未希さん
- がん告知や余命を伝える運動をやってきたが、余命告知にいまは反対です がん教育の先頭に立ってきたがん専門医が膀胱がんになったとき 東京大学医学部附属病院放射線治療部門長・中川恵一さん
- 誰の命でもない自分の命だから、納得いく治療を受けたい 私はこうして中咽頭がんステージⅣから生還した 俳優・村野武範さん
- 死からの生還に感謝感謝の毎日です。 オプジーボと樹状細胞ワクチン併用で前立腺PSA値が劇的に下がる・富田秀夫さん(元・宮城リコー/山形リコー社長)
- がんと闘っていくには何かアクションを起こすこと 35歳で胆管がんステージⅣ、5年生存率3%の現実を突きつけられた男の逆転の発想・西口洋平さん
- 治療する側とされる側の懸け橋の役割を果たしたい 下行結腸がんⅢA期、上部直腸、肝転移を乗り越え走るオストメイト口腔外科医・山本悦秀さん
- 胃がんになったことで世界にチャレンジしたいと思うようになった 妻からのプレゼントでスキルス性胃がんが発見されたプロダーツプレイヤー・山田勇樹さん
- 大腸がんを患って、酒と恋愛を止めました 多彩な才能の持ち主の異色漫画家・内田春菊さんが大腸がんで人工肛門(ストーマ)になってわかったこと



