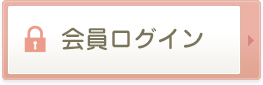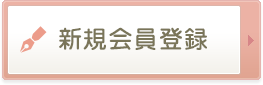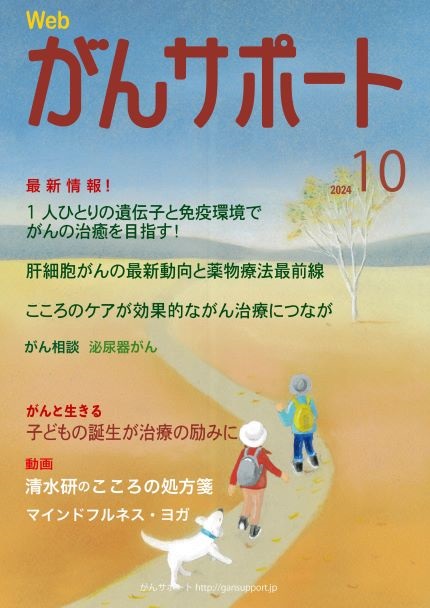- ホーム >
- 連載 >
- 吉田寿哉のリレーフォーライフ対談
「なぜベストな治療にまっすぐたどり着けないのか」という疑問から出発した医療改革の道
日本の医療を良くするには、アメリカの医療の良い面を取り入れるのが早道

はにおか けんいち
1959年兵庫県生まれ。大阪大学卒。1992年7月から1997年3月まで『日経ビジネス』のニューヨーク特派員と同支局長。1999年4月から2003年3月まで骨髄移植推進財団(骨髄バンク)の事務局長。現在は『日経メディカル』編集委員。著書に『インターネットを使ってガンと闘おう』(中央公論社)、『もっといい社会、もっといい人生』(河出書房新社)など

よしだ としや
1961年北九州市生まれ。84年一橋大学卒業後大手広告会社入社。89年アメリカ国際経営大学院(サンダーバード)でMBA取得。2003年秋に急性骨髄性白血病発病、臍帯血移植を行い、05年6月復職、現在部長。著書に『二人の天使がいのちをくれた』(小学館刊)
仕事をやめ、志願して骨髄バンク事務局長に
吉田 埴岡さんはご活動が骨髄バンクの改革そのものだったり、まさに闘うジャーナリストだと思います。今日は楽しみにしてきました(笑)。まず、いろいろ肩書きをお持ちなので、簡単にご紹介いただけますか。
埴岡 一応、4つのことをしていますが、ややこしいので最近はまとめて「がん医療コミュニケーター」と言っています。がん医療の進歩・改善のために新しい情報を流し、各方面の間の交流を促進する役目です。それを分解すると、第1にがん患者をサポートする仕事、第2に医療現場からがん医療を変える仕事、第3が情報を伝達したり交流したりするメディアの仕事、そして第4ががん医療政策を変える仕事です。患者、患者団体、医療者、行政と、がんにかかわる立場はいろいろですが、みんな良くしたいという気持ちをもっている場合が多い。けれども、コミュニケーションがないために、誤解したり対立していることも多いので、私がコミュニケーター役を果たすことで、がん医療を変えていくパワーにできるのではないか。最近は、そんなふうに考えています。
吉田 がん医療を考え始めたきっかけは、『日経ビジネス』誌のニューヨーク特派員のころ、奥様が白血病になられたことですか。
埴岡 ひと言で言えばそうですね。まず、家族ががん医療でたいへん多くの皆さんにお世話になったので、そのお返しをしたいという気持ちでした。と同時に、治療を模索する中で、「なぜベストな治療にまっすぐたどり着けないのか」という疑問がありました。
というのは、96年にニューヨークに駐在しているとき、妻が白血病になったのですが、私は経済ジャーナリストで医療のイの字も知らず、白血病ががんということも知りませんでした。で、医師に聞けば、「これがベストです」と百人が百人言うと思っていたのに、実際にはまったくそうではなかった。医師によって言うことが異なりましたし、こちらの質問によって医師が考えを深めて別の治療を推奨することもあった。それはなぜだろうと考えたのが、もうひとつのきっかけでした。
吉田 埴岡さんは骨髄バンクの事務局長もされましたね。仕事をしながら兼任されたのですか。
埴岡 帰国して約2年後、会社を辞めて事務局長になりました。帰国して半年ほどは茫然自失でした。それからがん仲間に手伝ってもらって闘病記のホームページを作ったりしていたのですが、だんだん「なぜ骨髄バンクは助けられるはずの人を助けられないのか」と発言するようになり、インターネットで提言をするようになりました。
そのうち、足しげく事務局に通い始め、異例ですが委員会に参加させてもらい、さらに、外から意見を言っていても埒があかないので、「私が事務局長をやりましょう」と手を挙げたんです。最終的に、4年間やらせていただきました。
吉田 そのあと日経メディカルに復帰されたのですね。
埴岡 すぐ復帰したというのではないのです。骨髄バンクに入るときに前の会社に帰るオプションを残していたわけではありません。あとのことは何も考えていませんでした。365日24時間というか、骨髄バンクの運営と改革のことばかり、あまり帰宅もせずにやっている状態でした。で、4年めには体力と気力の衰えも感じ、やれることはやったとの気持ちになりました。もともと2年のつもりが4年やったので、まあ潮時だろうと。
その後、無職になり、失業保険をもらう予定でしたが、前の会社に挨拶に行ったところ、契約社員にと誘っていただきました。今も契約社員です。ただ、経済・経営にはまったく興味をなくしていて、医療の記事を書く職場への配属をお願いしました。
努力が効果を生み出す仕組みを作ることが大事
埴岡 私が骨髄バンクをやりたかったのは、「改革できたら、今移植できない人が100人できるようになる」といった、患者さんの命にかかわる具体的な成果が期待できたからです。
たとえば、移植したい患者さんもドナー候補もいるのに、斡旋・調整に250日もかかり、間に合わずに亡くなる人が300人もいる。100日へと150日短縮すれば、150人が間に合うという計算ができる。1日あたりほぼ1人という数字です。その6割が生存されるとしたら、90人の命が助かるのです。そこで、コーディネートのプロセスを見直しました。簡素化・省略・同時平行処理などをしたら、今ではかなりの件数が、100日以内でできるようになり、米国の水準に近づきました。
献血時にドナー登録をお願いすれば、1年ででも目標の30万人ドナーが達成できるとも思えるのに、それができないという問題もありました。理由を調べたら、法的な壁でも何でもなく、平成4年、「本業の献血事業に影響がないように、骨髄登録は積極的に行わない」という内部通達が、日本赤十字社で出されていたことがわかったのです。
吉田 そうだったんですか!
埴岡 ボランティアとしてみんなで寒風の中で何万枚のチラシを撒く、といった努力も大切ですが、みんなの努力を最大限に生かすためには、逆に努力しなくてもできる「仕組み」を作らなければならないのだと思います。
吉田 最近は「がん難民」とか「がん囚人」という言葉を使って、がん全体にご発言されていますね。

アメリカの医療事情をつぶさに取材してきた
埴岡さんの話を中心に、2人は大いに語り合った
埴岡 ええ。あれは東京の医師、平岩正樹さんが言い始めた言葉ですが、私ががん全体に発言しはじめたのは、2003年3月にウエブサイトで「がんの治療成績を読む」という連載で成績格差について警鐘を鳴らしはじめたときでした。すると、ほかのマスコミも問題視するようになり、当時の坂口厚生労働大臣が「がん診療格差の問題を取り上げよう」と、大臣をやめるとき置き土産として「均てん化委員会」を作ってくれたのです。
吉田 1年間に新たにがんと診断されるのが約60万人、亡くなるのが約30万人。そのうち、医療レベルの格差解消で4万人は救えるというお話は、具体的でとてもわかりやすかったです。
埴岡 ジョン・レノンの『イマジン』という歌がありますが、この議論も「少し想像力を働かせよう」ということなんです。1人ひとりの患者さんが適切な医療を受けているかどうかが問題であると同時に、日本全体でどれだけの人命のロスが出ているか、それを考えることが大切です。実感できることでなくても、想像力を働かせばその問題が見えてきて、その大きさに驚きます。そして、それを解決することをイメージするのです。そのためにはがん診療の体系全体を再構築していかなければなりません。患者さんとしてみれば、がんになると、自分や家族がどうなるのかという不安や、闘病の快不快がほとんどになります。それで当然ですが、頭の隅で闘病仲間のことを考えるときがあってもいいでしょう。それをもう少し広げ、日本全体のことを考えてみようということです。
吉田さんも、臍帯血移植のときの主治医に出会わなければ、結果は違ったかもしれないと著書に書いておられますが、「正解」にたどりつける人とつけない人がいて、正解への道筋がむずかしすぎる。結果、助かっていい人が4万人、1日110人も無駄に失われている。何とかしなければならないと考えました。
同じカテゴリーの最新記事
- 骨髄バンクの活動から生まれた、国境を越えたドラマ「IMAGINE9.11」 他人を思いやってみよう。そうすれば心が豊かになる
- がん医療の弱点を補完するアンチ・エイジング医療 病気を治す医療から健康を守る医療へ
- 医療の第一歩は患者さんから話を聞くことから始まる
- 治療困難な「難治性白血病」の子どもたちが3割以上もいる 行政には医療制度のしっかりした骨格を、血肉の部分は「みんな」で育てる
- 本邦初のチャリティレーベルに10人のプロミュージシャンが参集 音楽、アートを通して白血病患者支援の輪を拡げたい
- 何よりも治療のタイミングが大切。治療成績向上の秘訣はそこにある 血液がん治療に新たな可能性を開く臍帯血移植
- がん患者、家族1800人を対象にした大規模調査から問題点をアピール 患者の声を医療政策に反映させようと立ち上がった
- 人の痛みや苦しみを体感した彼女が、自ら生み出した“LIVE FOR LIFE” 同じ境遇の人たちに勇気と希望のエールを。美奈子はそれをライフワークに選んだ
- ポイントは、ナース。ナースが意思決定に加われば医療の質も、患者満足度も上がる がん医療全体の質を上げるために、骨身を惜しまず取り組む