- ホーム >
- 連載 >
- 田原節子のもっと聞きたい
田原総一朗手記 がんを生き抜いた人生のパートナーに捧ぐ
「5年10カ月」の価値―生きる意志をエネルギーにした妻・節子
1日1日が全力投球の日々

8月13日の朝、妻・節子が息を引き取った。
彼女が炎症性乳がんに冒されたのは6年前、1998年のことだ。
最初に彼女を診た医者は、余命は6カ月程度と見ていた。しかし、結果的に彼女は6カ月ではなく6年も生きた。
これほど長い間生きることができたのは、彼女が正面から病気と向き合い、1日1日をまさに全力投球で生きたからだ。
それに加え、彼女には並外れた行動力と探求心があった。この2つの長所を活かして、彼女は多くの人とめぐり合い、知識を深めていった。人の面で言うと、とくに重要なのは頼りになる主治医にめぐり合ったことだ。聖路加国際病院の中村清吾先生である。
自分の体、自分の病気なのだから、知りうることはすべて知っておきたいという強い意志を持っている彼女は、中村先生にあらゆる疑問点を質し、がんがどのような状態にあるのか明確な答えを求めた。
有難かったのは中村先生が女房の性格や生き方を理解したうえで、誠実に回答をおくり続けてくれたことだ。前の日に、彼女がメールで送っておいた質問には翌日の朝、回答が来た。
主治医との尋常ならざるコミュニケーション
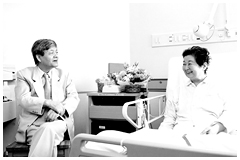
2003年9月
本誌の対談でお互いの本音を語り合う2人
私はこの中村先生と女房との緊密なやりとりを「尋常ならざるコミュニケーション」と高く評価し、感歎していた。それは、中村先生に電話を入れたときに受けた説明と、女房から聞いていたことが常に一致しているからだ。
持ち前の探求心でがんに関する知識をどんどん深めている彼女に、中村先生はすべてを話し、ありのままを伝えた。
彼女にはそうするのが一番という判断があったのだろうが、それを実際にやるとなるとそれに要するエネルギーは並大抵のものではない。先生から帰ってくるメールは単に女房に正確な情報を伝えただけでなく、のちのち彼女が様々な仕事に取組んでいく際には「知的なこやし」になっていった。
介護が楽しくてしかたなかった

車椅子押しは夫婦の絆を
いっそう強いものにした
いま振りかえって見ると、5年10カ月に及んだ女房と「炎症性乳がん」との闘いは、3つの時期に分けることができる。
第1期は、女房が「炎症性乳がん」という本当の病名を知らされないまま、医者と上手くコミュニケーションを取れずに悩んでいた時期。
第2期は、中村先生という素晴らしい主治医にめぐり合い、がんの再発はあったものの、一進一退を続けながら、小康を保っていた時期。
第3期は、脊髄や脳への転移が見つかり、車椅子の生活を余儀なくされてから亡くなるまで。この3つの時期のなかで、最も思い出深いのが第3期だ。私だけでなく、女房もそう感じていたと思う。
彼女が車椅子か松葉杖に頼らないと、どこにもいけない体になったのは2003年5月のことだ。がんが脊椎と腰椎に転移し、それがもとで歩行が困難になってしまったのだ。これによって、わたしたち夫婦を取り巻く環境はドラスティックな変化を見せるようになる。
わたしが直面した最も大きな変化は、女房を介護しなくてはいけなくなったことだ。それまでも、私は手術の影響で右腕が上がらない女房のために、洗髪を手伝うことはよくあった。しかし、介護はそんな次元の話ではない。

2002年2月10日
伊豆長岡にて
とくに、女房を風呂に入れる作業ははじめ、骨が折れた。
風呂は下が濡れているため滑りやすい。しかも、人の体というものは、ずっしり重いものだ。慣れないうちは上手くバランスを取れず、転ぶことも少なくない。かく言うわたしも、はじめて彼女を風呂にいれたとき足を滑らせ、2人とも溺れそうになった。
しかし、こうした失敗をするのも最初のうちだけ。回を重ねるうちにコツがわかってきたこともあって私は風呂入れが楽しくなって来た。
「風呂入れ」で私がとくに気に入っていたのは、肌と肌が触れ合うスキンシップを常に感じながら、作業できることだ。湯船に入れるとき、背中を流すとき、私は夫婦の絆がこれまでにないレベルで深まっていっていることを実感できた。
これ以外にもう一つ私が気に入っていた介護作業がある。
車椅子押しだ。それまで、車椅子を押すことがどんなものなのか全く知らなかったが、押してみると自分が彼女の「足」の部分を代行しているからか、一体感のようなものを感じることができた。
女房を介護するとき、私はこうしたメリットを十分感じながら作業することができた。だから、介護を苦痛と感じることは一度もなかった。それどころか、介護は実に楽しく、年をとることは悪いことばかりじゃないと思ったほどだ。
人生でもっとも濃密な時間
この第3期は、女房にとっても人生の中でもっとも濃密な時間だったのではないかと思う。
今年に入ってからは、がんが体のあちこちに転移して辛さと苦しさに耐える日々が続き、自分の病状の進行を感じるゆとりすらないように見えた。そんな状態なのに、仕事に強い使命感を抱いている彼女は、頼まれればストレッチャ―で運ばれながら車に乗りこみ、集会で発言したり、対談をこなしたりした。
7月にはNHKの『生活ほっとモーニング』に出演したが、このときは、もうかなり衰弱していたので気が気ではなかったが、出番まで横になって体力を温存し、本番を何とかこなした。
それ以外にも俵萠子さんが主宰したがん患者の集会にパネリストのひとりとして出席したり、毎月楽しみにしていた本誌の対談のホステス役をつとめたりしていた。 このように彼女はまさに死の直前まで、仕事をこなした。これは、使命感を感じていなければできるものではない。
「6カ月の命」を6年にした原動力

2004年5月31日
長女敦子に双子誕生。病院にかけつけて
彼女が頼まれた仕事に強い使命感をもって臨むことができたのは「自分に残された時間はもうわずかなのだから、今頑張らなければ」という強い思いがあったのが一つ。もう一つは、日本のがん医療を改善するには、自分のような、がんに泣いた一方で、がんに多くのことを学んだ人間が発言しなければならないという強い信念があったからだ。
とくに前者の「残された時間は、もうあまりないのだから、1日1日全力投球で行かなくては」という思いを、彼女は、がんになって以来、ずっと持ちつづけていた。持ちつづけていただけでなく、その思いは時間の経過とともにどんどん強くなっていった。
結論から言えば、これが彼女を6年も生き長らえさせてくれた原動力なのだ。彼女はこれを心のエネルギーにして、がんと闘ってきたのだ。
ついでに言わせてもらえば、この彼女の仕事に対する強い使命感が、わたしが彼女の死に目に会えなかった原因でもあるのだ。
私はだいぶ前から8月上旬にアメリカに3日間、中国と北朝鮮に6日間取材で出掛けることになっていた。とくに北朝鮮では日朝交渉のキーマンに会えることになっていたので、わたしはこの取材旅行を楽しみにしていた。
ところが、7月下旬になって彼女の病状が日増しに悪化し、予断を許さない状況になってきた。
中村先生に相談したところ、北朝鮮から帰ってくる8月14日まで持ちこたえられそうもないという。
最後の意志
その時点で、私は海外取材にいくことを断念した。
ところが、彼女にそのことを言うと、何か言おうとして咳き込んでしまった。もうその頃には、ものを言うのも苦しい状態になっていたので、言いたいことが言えないのだ。しかし、何を言いたいかは、私の顔をキッと睨みつけていることで理解できた。
「キーマンに人が訊けないような質問をぶつけるのは、あなたの使命よ! 行って! こんなところにいる場合じゃないでしょ!」
これで、わたしは海外取材に行く腹を固めた。それが、彼女の意志であればそれに従うしかないと思ったのだ。
結局、彼女は北朝鮮から帰国する前日の8月13日に息を引き取った。その日の未明、私は娘が携帯電話を使ってかけてよこした国際電話で叩き起こされた。もう心臓がいつ機能を停止してもおかしくない状況だと言うのだ。
「ケータイをお母さんの耳のところに置くから、お父さん、話しかけてくれる?」
「わかった」
それからしばらく、わたしは、言葉を変えながら女房に語りかけた。
「どう? 反応ある?」
「……」
それから2時間後、娘からの2度目の電話で、わたしは女房が息を引き取ったことを知った。
いま、彼女の遺骨は家に置いてある。
線香を上げたりはしない。いるつもりでいれば、賑やかだからだ。
朝起きてから寝るまで、家にいるときは、遺骨を入れた箱をなでたり、叩いたりしているし、出かけるときは「行ってくるよ」と必ず声をかけてから出掛けることにしている。
もちろん、そんなことをしたからといってポッカリ空いた穴が埋まるわけではない。しかし、最後の最後までどれだけ頑張ったか知っているので、49日が来たからといって土に返すことはできない……。
それが、現在の偽らざる心境である。
同じカテゴリーの最新記事
- 乳がんとの「闘い」の6年間を支えた「生きる意志力」 エッセイスト田原節子が遺したがん患者たちへの遺言
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・竹中文良さん 『がん』と『心』の深い結びつきにさらなる注目を!!
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・佐々木常雄さん 腫瘍に精通したホームドクターが増え、チーム医療が充実すれば、がんの在宅治療は定着する!
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・青木正美さん 大いに語り合った医師と患者がよい関係を築く秘訣
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・荻野尚さん コンピュータと情報の時代の申し子 陽子線治療は手術に匹敵する治療法
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・幡野和男さん さらに副作用を少なく! 放射線の最先端治療 IMRTのこれから
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・西尾正道さん 初期治療から緩和ケアまで、がん治療に大活躍する放射線治療のすべて
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・堤 寛さん 診断するのは病理医。この事実をもっと広めて、患者と医療を真に結びつけたい
- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・渡辺 亨さん 知れば知るほど奥の深い抗がん剤、もっともっと知りたい



