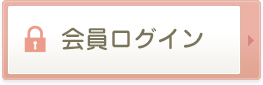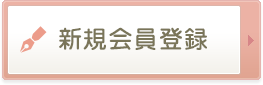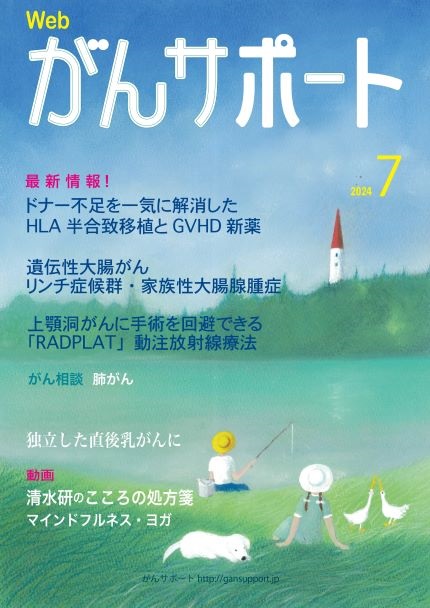がん患者を支える「栄養」とは
闘病中や回復期、症状が安定していれば、健康な人以上に栄養を摂ることが重要

東口髙志さん
がん患者さんの約2割は診断時点で低栄養に陥っており、治療が進むとその割合は8割以上にのぼるという。これは、がんそのものが多くのエネルギーを消費する上、手術、抗がん薬、放射線などの治療がエネルギーを必要とするためだ。奪われたエネルギーを十分補給できないと、低栄養によって体力が低下し、せっかくのがん治療も期待通りの効果を得られない。
かねてから〝栄養〟の大切さを訴えてきた藤田保健衛生大学医学部外科緩和医療講座教授の東口髙志さんに、がんが引き起こす栄養障害のメカニズム、それを防ぐための適切な栄養管理などについて伺った。
がん患者の8割はがんで死なない
2年前に出版した「『がん』では死なない『がん患者』―栄養障害が寿命を縮める」(光文社新書)の中で、かつての話ではあるが「がんで入院しても、本当にがんで死ぬのは2割に過ぎず、8割の患者さんは低栄養によって引き起こされる感染症などによって亡くなっている」と著者の藤田保健衛生大学医学部外科緩和医療講座教授の東口髙志さんは指摘し、センセーションを巻き起こした。
多くの人は、がん患者なのだから、がんで亡くなるのは当然と思っているはずだ。ところが、がん患者の死因のデータを調べると、多くのがん患者ががんではなく、感染症で死亡していたというのである。
「感染症には、食べ物の誤嚥(ごえん)による誤嚥性肺炎、菌が血液中に入って起こる敗血症、カテーテルから菌が侵入するカテーテル敗血症など様々なものがあります。ではなぜ、がん患者さんはこうした感染症にかかりやすいのか。ひと言でいえば免疫機能が低下したからで、それは〝栄養障害〟によってもたらされます」
栄養障害とは、栄養素のバランスが崩れることによって起こる代謝障害だ。栄養障害に陥ると、生命活動の全般がうまくいかなくなり、身体の様々な機能に支障が出る。
外敵から身を守る免疫機能もその1つで、低下すると、健康な人なら何でもない弱い菌でも感染しやすく、回復も難しくなる。がん患者の多くでは、それが死因に直結しているという。
忘れがたい患者さん
では、適切な栄養管理を行えば、感染症や合併症のリスクを回避できるのか。東口さんは、そうしたケースを多く経験しているが、その1例を紹介してくれた。
患者は70代後半の男性。喉頭がん末期で、余命1カ月と宣告され、同院の緩和ケア病棟に転院してきた。そのときは、ガリガリにやせ、まるでミイラのような状態だった。スタッフの誰もが一目みて「これはダメだ。よくもって2週間かしら」と思ったようだ。
しかし、東口さんは「悪いのは咽頭だけ。明らかな栄養不良を是正すれば、延命も可能」と判断し、栄養アセスメントに基づいて適切な栄養を補給し、口腔ケアやリハビリテーションも行った。
すると、1週間後ぐらいからみるみる回復し、わずかではあるが口からものを食べられるようになった。患者は、その後退院、自宅で5年間、奥さんと仲睦まじく幸せに暮らし、亡くなられた。死因は感染症や合併症ではなく、「がん」だったという。
東口さんは、「私は、これまで多くのがん患者さんの診療に携わってきました。その中でも、この方は『栄養管理は医療の基本』であることを、改めて実感させてくれた、忘れがたい1人」と振り返る。
がんによる代謝異常が栄養障害を引き起こす
さて、すでに触れたように、がん患者の多くでは栄養障害がみられる。そして、がんの進行とともに、体重が減り、やせ細っていくケースが少なくない。これは、がんが代謝異常を引き起こすためだ。
東口さんによると、代謝とは、摂取した食べ物をエネルギーに変えたり、筋肉などの組織を作ったりするためのもので、体内で起こる生化学反応全般のことをさす。私たちの身体は、この代謝が正常に機能することで、生命活動を維持している。ところが、がんはこの代謝を狂わせるという。
「まずみられるのが糖の代謝異常です。炭水化物などが消化・分解されてできるブドウ糖は、我々の大切なエネルギー源ですが、がん細胞にとっても唯一のエネルギー源なのです。そこで、がんは、自身が生き延びるためにブドウ糖を取り込んで、それをエネルギー源として活用しながら、増殖していくのです」
さらにがん細胞は、サイトカインという物質を分泌して、身体のタンパク質を分解し、そこから糖を得ようとします。サイトカインは様々な細胞に働きかけて細胞の働きを変えるホルモンに似た物質だが、がん細胞はこれを過剰に分泌して、タンパク質の分解をどんどんと促進する。筋肉の材料はタンパク質なので、それが不足すれば、筋肉が減少していく。
「さらに、過剰なサイトカインは、脂質代謝にも悪影響を及ぼし、脂肪細胞を分解して、これからも糖を得ようとします。そして、こうした代謝異常が重なることによって、がん患者さんは栄養不良となり、筋肉が細り、体脂肪も減って、あっという間にやせていくのです」
タンパク質、糖質、脂質をしっかり補給する
では、がんになっても栄養障害に陥らないようにするには、どのような栄養を摂ればいいのか。
東口さんによると、がん患者で多くみられる栄養障害は「タンパク・エネルギー栄養障害」だという。
「つまり、身体を作る材料となるタンパク質やアミノ酸、エネルギー源となる炭水化物(糖質)や脂質が足りないのです。タンパク質、糖質、脂質は3大栄養素といわれているように、これがないと人は生きていくことができません。したがって、この基本中の基本の栄養素をしっかり補給し、がんと闘う力をつけることが大切になります」
ただ、糖質はがん細胞にとって大好物の栄養素。摂ると、がんの増殖を促すのではないかと心配する患者もいる。この点について東口さんは「それは大きな間違い。がん細胞は、私たちが糖を摂取しようがすまいが、全く関係なく糖を作って消費します。逆に糖を取らないでいると全身衰弱が進み、意識障害や高度の貧血になります。要するに、がんは身体からどんどん生きるために必要とする栄養を奪っています。
その分の栄養を補給しなければ、瞬く間に栄養障害をきたしてしまい免疫能までの健常組織の働きが抑制されるのです。そして、栄養を絞りつくされれば、先にあるのは死。それを防ぐためにも、まずは十分な栄養の摂取が必要なのです」と強調する。
同じカテゴリーの最新記事
- 栄養療法+消化酵素補充療法で予後が改善! 膵がんは周術期の栄養が大事
- がん患者さんのサルコペニアを防ぐ ――カギを握るのは栄養管理とリハビリテーション
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる
- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン
- 脂質で増殖する前立腺がんには脂質の過剰摂取に注意! 前立腺がんに欠かせない食生活改善。予防、再発・転移防止にも効果
- がんと診断されたら栄養療法を治療と一緒に開始すると効果的 進行・再発大腸がんでも生存期間の延長が期待できる栄養療法とは
- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理
- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス