より負担が少なくて、精度の高い検査法
肺がんの確定診断に威力を発揮するCTガイド下気管支鏡検査
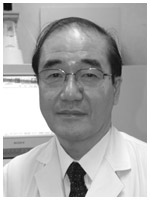
国立がん研究センター中央病院
内視鏡部咽喉内視鏡室医長の
金子昌弘さん
X線やCT(コンピュータ断層撮影)検査などで肺がんを疑う病変が見つかっても、肺がんと確定診断するにはがん細胞を確認する必要がある。そのための検査として気管支鏡検査、CTガイド下肺針生検、開胸生検などがあるが、より負担が少なくて精度の高い検査法として新たに開発されたのがCTガイド下気管支鏡検査だ。
気管支鏡が届かない病変
「がんかどうかの確定診断を行う場合、胃とか腸でしたら、消化管という1本の管なので、胃カメラや大腸カメラを入れればどんな奥でも病巣を観察できて、組織の採取もできます。しかし、肺の場合、中央部分の気管支は太いものの、枝分かれしている奥のほうは、どんどん細くなるので気管支鏡と呼ばれる内視鏡が届かず、肉眼での観察がほとんど困難になります。このため、肺がんの疑いがあっても、病巣そのものを目で見られるのは全体の1~2割にすぎず、残りの多くは気管支鏡では見えないところにあります。そこで、何らかの方法で肺の奥にある隠れた病巣を確認し、組織を採ってくるようにしなければいけません」
こう語るのは、国立がん研究センター中央病院内視鏡部咽喉内視鏡室医長の金子昌弘さんだ。NPO法人日本呼吸器内視鏡学会と同じく、NPO法人日本CT検診学会の理事長でもある。
たしかに、肺がんといってもさまざまな種類があり、発生する場所によっても「肺門部肺がん」と「末梢部肺がん」に大別される。
「肺門部」は肺の入口の太い気管支にできるがんで、扁平上皮がんが多いが、初期にはX線写真で発見するのが難しい。その代わり咳や痰などの症状が現れやすい特徴がある。太い気管支にできるので、気管支鏡を用いて病巣から細胞や組織の一部を取り出すのが比較的容易だ。
一方の「末梢部」は気管支の末梢から肺胞にできるもので、多いのは腺がん。初期にはなかなか症状が現れないが、比較的早い段階にX線写真で見つけることが可能。ただし、写真だけでは肺の中を走っている血管や肋骨、心臓などに邪魔をされ、がんを見落とすことも少なくない。また、肺の奥だけに、気管支鏡が届きにくいという難点がある。しかも、患者さんの数が圧倒的に多いのがこのタイプのがんというわけなのだ。
肺から組織を採取する3つの方法

国立がん研究センター中央病院の気管支鏡検査室
そもそも肺の細胞を取り出す方法として、もっとも簡単にできるのは痰の中のがん細胞を確認する喀痰細胞診だが、痰が出なかったり痰による診断ができない場合、これまで行われてきたのは次の3つの方法だ。
1つは気管支鏡検査。気管支鏡は自在に曲げられるようになっていて、先端にはライトがついており、気管支を通して肺の内部まで肉眼で観察することができる。また、気管支鏡に生検用の器具を通し、病変がある部分にそれを差し入れて、生検用の検体を採取したりもする。気管支鏡は鼻や口から挿入するが、喉や気管の刺激を軽減するため局所麻酔をして行う。気管支鏡では見えない末梢病巣に対しては、X線透視下で細い器具を誘導し、病巣から細胞を採取する。
次に経皮的肺穿刺法。これは気管支鏡での検査が困難だったり、採取された検体が診断に十分でない場合、局所麻酔をしたうえで、外から皮膚を通して細い針を挿入し、肺の病巣に命中させて細胞を採取する。針は注射針のように中空になっているので、細胞を針の中に取り込んで持ってくる。X線で透視をして、病巣を確かめながら行う場合もあるが、最近ではCTを用いて目標を定め、針を病巣に命中させて細胞を採取するCTガイド下肺針生検が一般的に行われている。
もう1つは開胸生検といって、全身麻酔下で、胸を開ける手術によって直接病巣から細胞をとり、診断する方法。気管支鏡や経皮的肺穿刺法でも診断が困難な場合に行われる。近年は、胸の皮膚を小さく切開し、胸腔鏡と呼ばれる内視鏡を挿入して細胞をとる方法も普及してきている。
そこに、最新の検査法として登場したのがCTガイド下気管支鏡検査である。
どんな検査かというと、CTによって病変の正確な位置を特定し、そこに気管支鏡を近づけ、生検用の器具をX線透視とCTとで病変に誘導することにより、その病変から診断用の検体を採取する。
従来のX線透視下の検査にCTを加えた検査法だが、近年めざましいCTの技術革新によって実現した検査法といえよう。
CTガイド下肺針生検に代わる方法

CT画像を見ながら検査をしているところ
この検査法が登場してきた背景を金子さんに解説してもらうと――。
「従来、肺がんを見つけるのに活躍してきたのがX線写真です。ところが、X線写真だと大動脈などの太い血管や心臓、骨、横隔膜などが死角になって見えない部分があるとか、小さい影や淡い影は映らないといった限界がありました。そこに現れたのがCTです。CTの発達によって、X線写真では見えないような小さな病巣が見つかるようになってきました。すると、CTで見つかった病変を気管支鏡で診断しようとすると、X線写真ではだめで、気管支鏡検査をやっている最中にCTで確かめないとわからないわけです」
そこで、現在、多くの医療機関で行われているのが、CTガイド下肺針生検だ。
この検査は、CTで正確な位置を確かめながら行うので、命中率は高い。しかし、外から胸の中に針を刺すのだから、合併症の危険も少なくないという問題点がある。
「もっともポピュラーな合併症が気胸ですが、まれではありますが空気塞栓や腫瘍細胞の播種の可能性があります。さらに、この検査がうまくいかなくて胸腔鏡下生検が行われるケースも少なくありません」
と金子さんは指摘する。
気胸とは、肺や気管支などを損傷することにより胸腔に空気が入り込んだ状態を言い、放っておくと呼吸困難になってしまう。すぐに処置すれば心配はないが、以前に胸の手術をして片肺になっている人などは注意が必要だ。CTガイド下肺針生検は、肺を覆っている胸膜に外から穴を開けるので、そこから空気が漏れて気胸になる可能性がある。
また、空気塞栓という合併症は、漏れた空気が血管に入り込み、血流を阻害するもので、悪くすれば命の危険もある。やはりまれではあるが、針先についたがん細胞によって、針を刺した経路にがんが播種することも起こりうる。
胸腔鏡下生検も、開胸生検と同様に入院して全身麻酔が必要となるため、患者さんへの負担は大きいし、気胸や出血、空気塞栓といった合併症の危険が否定できない。
こうしたなかで、新たに開発されたのがCTガイド下気管支鏡検査。CTガイド下肺針生検のような合併症の心配が少なく、より安全に行われるのがメリットの1つだ。
「デメリットとしてあげられるのは、従来の気管支鏡検査と比べて多少時間がかかることと、被曝によって新たながんが引き起こされる恐れがあること。しかし、1年に何度も検査を受けるわけではないし、この検査で用いるのは低線量なので、被曝の問題はそれほど心配はいりません」 と金子さんは語る。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍
- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!
- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと
- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に
- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に
- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ
- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に⁉ ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に



