子供との安らぎの場を提供し母親を助け、成長を見守る
「せっかく、子供に外出許可が出たのに、大好きなハンバーグをつくってあげることもできない」
「ホテル暮らしは落ち着かないし、宿泊費がかさんでやっていけない」
「1人で泣くことができる場所がほしい」
――がんをはじめとする子供たちの難病は、同時に母親にとっても深刻な状況の到来を意味している。なかでも地方から東京の病院に入院している場合には、母親たちを取り巻く環境は過酷そのものだ。
とくに白血病など小児がんの場合は、入院期間が年単位と長期化することが多く、母親たちの負担は否がうえでも増し続ける。恐れや不安を抱えながら、慣れない東京で、わが子を見守り続けるために、たった1人で無味乾燥なビジネスホテルや狭いアパートで送る毎日に、多くの母親たちは身も心も消耗しつくしている。
行き場のない母親たちをサポートしたい

「ファミリーハウス」事務局の
植田洋子さん
そうした母親たちの願いは、ただ1つのセンテンスに集約される。東京にもう1つの家があれば――。
その願いを実現しているボランティアグループがある。
「がんや心臓病など、難病を患っている子供の母親の多くは精神的にも経済的にも疲弊しきっています。そうした状況に陥らないように母親たちをサポートしたい。そのためには何より、子供たちとも一緒に落ち着ける場所が必要でしょう。そこで東京都内で安全で安心できる滞在型施設を提供しているのです」
と、話すのはNPО法人「ファミリーハウス」の植田洋子さんである。
小児がんの子供を持つ母親たちが立ち上がり、「ファミリーハウス」の前身である「愛の家」が発足したのが1991年。それから現在に至るまで17年の間に、施設は8カ所に増加し、昨年3月までの延べ利用者は約1万3000人に達している。「無理な背伸びをせず、ゆっくりと事業を進めていきたい」という植田さんの言葉どおり、「ファミリーハウス」の活動は着実に、その幅を広げ続けてきた。
さらに現在では、「ファミリーハウス」が先鞭をつけた施設提供事業が各地に広がり、現在では難病の子供を抱える家族を対象にした滞在施設は、日本全国で約70団体、125施設にまで膨れ上がっている。その多くは地元に帰った「ファミリーハウス」の利用者が、立ち上げた団体だと植田さんは言う。
少し前にはそうした各団体でJHHHネットワークというゆるやかなネットワークが組織され、「ファミリーハウス」がそのホスト役を任されている。 もっともここまでにいたる道程は、決して平坦なものではなかった。
母親たちが始めた「もう1つの家」探し

「かんがるーの家」の外観

「かんがるーの家」の室内
アメリカには多くの大病院の近辺に「マクドナルドハウス」と呼ばれる小児患者の家族の宿泊施設がある。企業が利益の一部を社会還元するためにつくられている施設だ。
東京・国立がん研究センター中央病院で小児がんを扱う6A病棟で子供たちを見舞っていた母親たちが、当時、ボランティアとして、こどもたちのケアを行っていたアメリカ人シスター、キャサリン・ライリーさんから、そのことを教えられたのが、「ファミリーハウス」発足のきっかけだった。
「日本でも同じような施設ができないものか」
自らのためにそして、これから自分たちと同じ道を歩むであろう多くの母親のために彼女たちは結束、「6A母の会」を結成する。そこに彼女たちに共鳴した、当時、国立がん研究センターで小児科医長だった故・大平睦朗さん、現在はNPO法人「ファミリーハウス」の理事長で、当時は小児科の看護師長だった江口八千代さんが加わり、「愛の家」という活動グループがスタートした。
初代理事長に就任した大平さんや母親たちは、窮状を訴えるために新聞社に働きかけ、フォーラムも開催、さらに支援を求めて企業まわりも続けるが、手ごたえは芳しいものではなかった。バブル経済の余韻が残る当時に、いわば「打ちでの小槌」のような資産価値を持つ不動産を提供しようという企業は皆無だったという。
しかし、翌年12月には地道な活動が報われることになる。ある女性小児科医から渋谷のマンション2LDK1室を提供するという申し出があった。これが最初の滞在型宿泊施設「パピーの家」である。そうしてさらに、翌93年には、愛息を白血病で失くした東京・調布市の家具店オーナーが店舗の屋上に5室の大型滞在施設を建設して、提供してくれる。これが日本では初めての小児患者の家族のための本格的な滞在施設「かんがるーの家」となる。
その後97年には「愛の家」を現在の「ファミリーハウス」に改称しNPО法人格を取得、そのころから新聞報道などで母親たちの活動を知った篤志家からの不動産提供が続き、「おさかなの家」(東京・港区、5室)、「ちいさいおうち」(東京・港区1室)「ぞうさんのおうち」(東京・台東区1室)、「ひつじさんのおうち」(東京世田谷区3室)と、施設は順調に増加を続ける。さらに01年からは企業からの支援の申し出もあり、「アフラックペアレンツハウス亀戸」「アフラックペアレンツハウス浅草橋」と大型の滞在施設も整えられ、現在に至っている。
これらの施設は提供者が管理している場合を含め160名にものぼる無償、有償のボランティアのハウス・マネジャーによって運営されている。ちなみにいずれの施設も利用料金は1泊1000円。利用条件は20歳未満の子供が病気であること、そしてもう1つ、利用者本人が連絡することも必要だ。これには理由があると植田さんはいう。
「私たちの施設はホテルではありません。皆が助け合い、自覚を持って安全で安心できるスペースを守らなければ、施設の安全な運営はできません。そのことを理解し、協力してもらうために、自分自身での連絡をお願いしています。私たちスタッフは利用者の状況に必要以上に立ち入りませんが、それもわずらわしさを感じずに安心して施設を利用してもらいたいという思いによるものです」
がん患者の母親ならずとも、人はプライバシーを侵害されると腹立たしい思いを覚えるし、時には誰とも話したくなく、1人になりたいこともある。そうした1個人としてのささやかな思いが、かなえられているからこそ、多くの人たちが「もう1つの家」として、「ファミリーハウス」の施設を利用しているに違いない。
運営には中立的な視点も不可欠
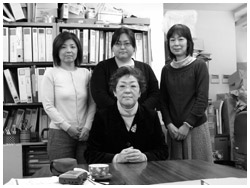
植田さんと「ファミリーハウス」事務局のスタッフさん
現在、「ファミリーハウス」の事務局スタッフは5名。全員が病気の子供をもつ当事者ではない。植田さん自身も98年に相談員としてスタッフの仲間入りをした人だ。そうした事務局のありようは、結果的に施設の運営、拡充のプラスになったのではないかと植田さんは言う。
「以前にはがん患者さんや施設の利用者さんが事務局の運営に直接携わるべきではないかという思いもありました。しかし、当事者が直接かかわるのはつらすぎるというご意見もうかがい、今の形態でやってみたわけですが、活動の客観性を保つためにはこの形もよかったかなという思いです。私たちの活動は支援者や一般の人たちの協力があって、初めて成り立つものです。活動に参加している人たち全員に納得してもらわなければ施設の運営は立ち行きません。そしてそのためには、ニュートラルな視点は欠かせないと考えているんです。もっとも、実際にはバランスのとり方が微妙でとても難しい。片足は常に利用者の側に置いていますが、もう片足は、外側に置いて大きな目で状況を判断するように心がけています」
ファミリーハウスは人が成長する場でもある
そんな植田さんが施設を運営するなかで、折々に思い起こすのが初代理事長だった大平さんから聞かされた言葉だ。大平さんは「ファミリーハウスは人のいいところを引き出すための活動でなければならない」と口ぐせのように話していたという。
「私たちの施設は人が成長する場でもあると感じています。子供が重い病気になった直後は周りが見えず、自分のことだけで精一杯のお母さんが、子供の病状が落ち着くと、ハウスで他の人たちと助け合い、交流を深めていくことで成熟し、魅力的な人間に変わっていく。そうした変化の過程に接することは、楽しみでもあるし、やりがいでもあります」
と、植田さんは眼鏡の奥の目を細める。
現在の「ファミリーハウス」の施設稼働率は約60パーセント。その数字だけを取り上げると、切実な状況はひとまずクリアされているようでもある。しかし植田さんはそうした数字は必ずしも的確に現実を反映していないという。
「子供がオペを受ける場合などは、すぐに駆けつけられるよう病院から徒歩圏内にある滞在施設が必要です。そうした施設は少ない。ハウスを支えるマンパワーもまだまだ不足しています。利用者さんにとって役に立つハウスであるために、多くの企業やボランティアの人たちに、細く長くつき合っていただければと思っています」
人を助け、人を育むサポートのあり方を探りながら、植田さんたちの奮闘が続く。
NPO法人ファミリーハウス
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-19
TEL:03-5825-2931 FAX:03-5825-29351
ホームページ



