乳房を失った悲しみや孤独感を写真で表現することで、自分を解放できる
自分が表現者であることを失くした右胸が教えてくれた
 荒多惠子さん
荒多惠子さん(写真家)
あら たえこ
1963 年生まれ。30 歳で写真を撮り始める。04 年に乳がんを発症し、右乳房を全摘。07 年、「『胸神(muna kami)』─乳がんになった日から─」で第13 回土門拳文化賞奨励賞を受賞。現在も写真家として活動し、写真ワークショップ「セレーネ」を主宰するほか、がん患者の支援活動も行っている
乳がんの手術で右胸を失ったことによる喪失感や絶望と闘い、
ホルモン治療の副作用によるうつ症状に悩まされながらも、
ファインダーを通して自らの心を見つめ続けた写真家、荒 多惠子さん。
自分らしさを探して、もがいていた荒さんが、がんとの闘いを経て、
表現者としての立ち位置を見つけるまでの苦悩とは──。
自分の身代わりとなって天に召された右胸に誓う
今春、熱海市の有形文化財「起雲閣」の開館10周年を記念して、ある写真展が開催された。「瞬光」と名付けられたこの写真展は、「熱海の3大別荘」と謳われた起雲閣の"今"を表現したもの。大正の遺香漂う名邸の多彩な表情を、モノクロームで見事に切り取ってみせたのが、写真家の荒 多惠子さん(47歳)だ。
荒さんが乳がんを発症したのは40歳のとき。右胸を全摘し、5年間のホルモン治療を行った。副作用の激しいうつに苦しめられながらも、荒さんはファインダーを通して自らの心をひたすら見つめ続けた。
その写真は高く評価され、第13回土門拳文化賞奨励賞を受賞。現在は新進写真家として活躍するかたわら、いろいろな活動を通じて、がん患者の支援活動にも取り組んでいる。
受賞対象となった作品には、「『胸神(muna kami)』─乳がんになった日から─」というタイトルが冠せられている。
「私がこの世に生きていられるのは、失った右胸のおかげ。自分の身代わりとなって天に召されてしまった右胸は、私にとって神様のようなものなんです。胸の神様に誓って、私は必死に生きていきます──そんな気持ちを、『胸神』という言葉に込めたのです」
写真家・荒多惠子の原点には、ある1枚の写真がある。右胸の全摘手術直前に撮影した、荒さん自身のセルフヌード写真だ。
「そのファースト・カットは、今でも自分の部屋に飾っています。その写真を見るたびに、『ここから私は始まったんだ』と思えるんです」
このあり余る感情をどこに持っていけばいいのか
大学で国文学を専攻し、卒業後はOLとして経理事務などを担当。数値を扱う仕事はそれなりに面白かったが、どこかでもどかしさも感じていた。
荒さんは、ある日の情景を、今でもはっきりと覚えているという。会社の給湯室でお茶汲みをしていたときのことだ。
(このあり余る感情を、どこに持っていけばいいのかな)
心の奥深くから突然噴き出してきた、やり場のない想い。荒さんの内なる表現欲求が、OL生活のなかで行き場を失い、悲鳴を上げたのだった。
「当時から、自分は会社員向きではないな、と感じていましたね。仕事で満たされない分、お芝居や映画に通っていました」
そんな荒さんが、表現の世界へと1歩踏み出したのは、20代後半のこと。1人旅の楽しみを覚え、一眼レフカメラを購入して旅先での印象をカメラに収め始めた。だが、なかなか思うような写真が撮れない。そんな折、奈良の仏像などの写真で知られる入江泰吉の写真集に出合う。
「自分もこんな写真が撮れるようになりたい」
そう思い、30歳のときにカルチャーセンターの写真教室に通い始めた。
33歳で転職し、結婚・退職。だが、荒さんは、専業主婦としての自分になじめずにいた。
「仕事を辞めたことで、自分が何のために生きているのかわからなくなり、精神的なバランスを崩してしまったんです」
満たされない想いをぶつけるように、荒さんは写真に打ち込 んだ。37歳のとき、2000年度JPS(日本写真家協会)展の銅賞を受賞。このまま写真家としてやっていけるかも──そんな自分の考えがいかに甘かったかを、荒さんは発病によって思い知らされることになる。
手術直前に、鏡の前でセルフヌードを撮影
乳がんが発覚したのは2004年5月、40歳のときのことだ。予兆がなかったわけではない。その1年半ほど前、右胸にしこりができ、総合病院の乳腺外科を受診。「良性の乳腺症」と診断され、日帰り手術でしこりを除去した。しかし、03年暮れごろから右胸に鈍痛を感じるようになった。
「これは普通の痛みではない、と思いましたね。細胞が死んでいくような感じがしたんです」
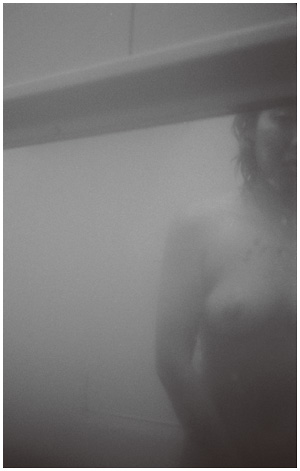
セルフヌードを撮る(2004年5月)
翌年4月に受けたマンモグラフィ(*)検査の画像を見て、主治医はこう言った。
「これは間違いなく、がん細胞です。手術することを考えてください」
主治医の言葉は重く響いた。このときのことを、荒さんはこう述懐する。
「とにかく『どうしたら生き続けられるか』という想いでいっぱいでした。できることなら胸は残したい。でも、命は永らえたい。生きるためにはどうするべきか、冷静に考えました。だから、泣いている暇はなかったですね」
検査の結果は、ステージ1。主治医からは右胸全摘を勧められたが、荒さんは手術までの2週間、最良の選択肢を探して走り回った。数軒の病院でセカンドオピニオン(*)を求めたが、どの医師からも「全摘がベスト」と告げられた。
最終的に、荒さんは全摘手術を受ける覚悟を固める。だが、その前にやっておくべきことがあった。それは、40年間連れ添ってきた自分の身体との、訣別の儀式だった。
手術前、荒さんは自宅マンションの鏡の前で、セルフヌードを撮影している。
「愛おしい自分の身体がもう見られなくなってしまう。だから、写真として記録に残しておきたいと思ったんです」
*マンモグラフィ検査=乳房専用X 線撮影検査
*セカンドオピニオン=第2の意見」として病状や治療法について、担当医以外の医師の意見を聞いて参考にすること
右胸を全摘。5年間のホルモン治療へ
5月下旬、右乳房を全摘し、腋窩リンパ節も郭清。胸の術巣から廃液を体外に排出するため、2本のドレーン(*)が挿入された。
「手術翌日はショックが大きくて、言葉になりませんでした」
そんなとき救いとなったのが、同室の患者さんとの交流だった。なかでも、白内障を患う老婦人は、冗談を言っては、ふさぎがちな荒さんを笑わせてくれた。
「看護師の皆さんも、入院中は『がん』という言葉を一言も発しなかった。そのことが、どれほど患者の気持ちを楽にしてくれるか。というのも、患者にとっては、やはり『がん=死』なんです。家族を置いて、1人であの世に旅立たなければならないかもしれないという孤独──それが何よりつらいし、怖い。だから、周囲が患者にできる最良のサポートは、患者を孤独にさせないことだと思います」
退院後は、毎日のように1時間ほど浴室にこもり、傷跡を見ながら泣いた。涙が浴槽にたまるほど泣かなければ、浴室から出ることさえできなかった。
「それは、新たに生き直すための、みそぎの場だったのかもしれません」
右胸を失い、女性らしい身体を失うことは、それほど受け入れ難いことだった。
病理検査の結果、幸いリンパ節に転移は見つからなかった。このため、抗がん剤治療は行わず、ホルモン治療を5年間継続することになった。
(このまま治療すれば、本来の自分に戻れる)
退院の日、荒さんの心は喜びでいっぱいだった。この先、副作用との壮絶な闘いが待ち受けていることなど、知るよしもなかったのである。
*ドレーン=創傷部にたまった液、尿などの排出に用いる排液管
同じカテゴリーの最新記事
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って
- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる
- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん
- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫
- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発



