白血病を乗り越え、骨髄バンク支援に立ち上がる舞踊家 日本舞踊「錦流」宗家、錦加宝光・前原レイコさん
音楽が生きがい。唄と踊りがあったから、彼女の今日がある
踊りは私の人生そのもの

前原レイコさん
(まえはら れいこ)
日本舞踊「錦流」宗家、錦加宝光
急性骨髄性白血病の発病から6年。生死の境を乗り越え、治癒後に辿り着いた念願の舞台は、骨髄移植を待つ人々のための「チャリティー発表会」だった。定員約500人の北九州市の会場はほぼ満員。
舞台に立ったのは大病を患った前原レイコさんではない。もう1人の自分、日本舞踊「錦流」宗家の錦加宝光だった。
長唄の調べに乗って踊り、鼓に合わせて力強く足を踏み鳴らす。20分ほどの演目「長唄 老松」を見事に演じ切った。が、幕が降りた瞬間、もう立ち上がれなかった。闘病生活で弱った下半身が1年の稽古で元通りになるはずがない。痛み止めを射ち、ただ舞台に立ちたい一心で自分を奮い立たせただけだった。
「足がフラフラしとるんで、いったん座ったら幕を降ろして抱えてもらわないと立ち上がれないんです。頭下げたら下げたままでした」
でも、思いは伝わった。
大勢の人たちが寄せてくれた80万円ほどの浄財を骨髄バンク後援会に寄付。発表会は大成功に終わった。錦さんは、そのときのことをこう振り返る。
「私にとって踊りは人生そのもの。自分が生きて、舞台に立てたってことだけで幸せなのに、あんなにも大勢の人が集まってくれ、寄付をしていただいて本当に嬉しかった」
姉が必死に伏せた「白血病」という病名
最初は風邪のような症状だった。5歳のときから踊りで鍛え、病気ひとつしたことのなかった体がどうにも重い。人と会話するのも、椅子の背もたれに寄りかからないと息があがるようになった。いくつかの病院で「過労でしょう」とか「ストレスじゃないですか」と言われ、そんなはずはないと小倉記念病院(北九州市)へ行くと、血液内科医の澤田仁さん(現・高の原中央病院)からこう言われた。
「命にかかわります。すぐに入院してください」
その日も発表会を目前に控えた隣県の生徒の指導に行く予定が入っていた。和服に着替え、髪は美容院に行く前だったのでゴムで結わえた状態。まさか入院になるとは夢々思っていなかった。生徒たちには申し訳なかったが、仕方がない。姉の君子さんに準備を頼み、そのまま即入院となった。1993年、前原さん53歳のときだった。
急性骨髄性白血病――この病名は、肉親である姉にだけ伝えられた。
白血病のなかでも腫瘍の増殖速度が速いタイプで、治療は一刻を争う。1970年くらいまでは「不治の病」だったが、治療成績は向上し続け、今では一時的に良くなる「完全寛解率」は60~80パーセントにのぼる。告知も当たり前になっているが、前原さんが発病した13年前は今とは明らかに違った。
舞踊の世界でも「立役」と呼ぶ男役を演じてきたのが前原さん。「錦流」を一時は全国に約500名もの名取を抱える一派にまで育てた手腕をもち、一見気丈にも見えるが、もろさもあることを最もよく知るのが姉だった。君子さんは「絶対に本人には教えないで」と、時には医師に正面を切って意見したという。
白血病になった者しかわからないつらさ
病名を知らないまま、前原さんの闘病生活が始まった。
治療はまず、抗がん剤で骨髄のなかの白血病細胞をたたくことから始まった。正常な白血球の極端な減少で感染抵抗力が弱まるため、無菌室(クリーンルーム)での治療となる。部屋に入れるのは医療関係者と姉だけ。白衣を着て、消毒をしなければ入室できなかった。
「7カ月は姉以外の人にほとんど会っていません。もう今晩死ぬんやないやろうか、明日死ぬんやないやろうかの繰り返しです。夢も希望も無かったですね」
病室の鏡は、前原さんが見ないよう紙が貼られていた。それでも見たくなるのが人間心理。夜、紙を剥いでこっそり自分の顔を見た瞬間、全身が凍りついた。
「見たらいけんよって言われてましたが、どんなになってるかなって思うじゃないですか。鏡に映っていた顔はまっ青、髪の毛は全然ない、まつ毛も眉毛もない、何にもないのっぺらぼう。怖くてガタガタ震えました」
抗がん剤治療の副作用で高熱を発し、食事が運ばれる音を聞いただけで吐き気に襲われ、喉は激しい嘔吐で焼けただれるようになった。
病室の窓は、転落防止のため全開しない仕組みだったが、「なんべんも自殺しようと窓をこじ開けようとしました」
体調が悪いときではなく、考える余裕ができた体調のいいときに「死にたい」という気持ちが芽生える。
「ちょっと元気が良くなると、死にたい、となるんです。病気が治る治らないで悩むんじゃなく、治療そのものに堪えられないんです。口の中にできるのも口内炎なんてもんじゃないんです。鼻の中にもできるし、顔もすごい腫れて。テレビや映画の白血病患者は美女が登場しますけど、とんでもない。白血病のつらさは、なった者しかわかりません」
病名は、ある時点からうすうす勘付いていたが、聞きたくない、信じたくないという気持ちが強かったようだ。
「先生から白血病と言われないから、助かると信じてました。先生が言わないのだから白血病じゃない、助かるんだって持ちこたえたんです。3年とか1年しか生きらんとか言われたら、自分が病気を治すという気持ちになりません。私は絶対という言葉を使います。姉が隠してくれて絶対に良かったです」
退院後も1年間続いた通院治療

近所の人や親しい知人たちに囲まれての快気祝い(97年2月)
入院7カ月目で見える範囲の白血病は消え、8カ月で無事に退院となった。しかし、ほっとする間もなく寛解を維持するための「維持療法」が始まった。白血病のつらさは再発の恐怖に怯えながら、通院治療を続けなければならないところにもある。とくに退院後の1年間は、入院時と同じ強い抗がん剤を使う「強化療法」も体調を見ながら併せて行うことになる。
前原さんは毎日のように病院に通いながら、医師の教えはすべて守った。好物だった刺身も発病以来、1度も口にしていない。生水も飲まず、余ったおかずは食べないようすぐに捨てた。いざというときのために飛行機には乗らず、車の運転も止めてタクシーを利用した。病院に行く際にも必ずマスクをつけたため、「病院では『マスクの人』ってあだ名がついとるみたいです」
前原さんの場合、発病から約3年間髪の毛が生えなかった。いや正確に言うと、生えかかっても抗がん剤治療でまた抜けてしまったのだ。
周囲の冷酷な視線に苦しめられた
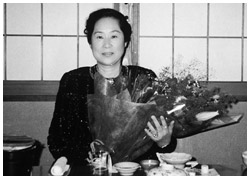
快気祝いをしてもらって
「体力がついて少し生えてきたら、また治療をして抜けるんです。やっぱり女ですから髪の毛は大切。近ごろは帽子とかカツラで髪の毛のない人をあまり見かけませんが、私は帽子を被っただけで痛かったんです。毛穴が全然無い人は、痛くて頭にタオルもかけられないんです」
この外見から、周囲の冷酷な視線にも苦しめられた。
道を歩いていると、髪の無い自分を指差して笑う中学生たちにも会った。何か冗談を言ったのか、先生らしき人もいっしょになって振り向いて笑った。
病院にも、人間性を疑うような人もいた。
「私が座ろうとすると、パッと逃げるように立って違うとこ行ったりしますからね。それこそ泣きの涙です」
親しくなった白血病患者との別れにも何度も遭遇した。
入院時には話す機会がほとんど無かったが、退院後の通院では次第に親しい間柄になる。
「あんたがあそこの部屋に入っとったんかね、全然見らんかったって待合室なんかで話すんです。でも、男の人は退院したらすぐ働きますでしょ。だから命を縮めてる気がするんです」
医師が1年くらいの安静をすすめても、一家の大黒柱にはそれが許されないことが多い。前原さんは、記者に対しても何度もこう繰り返した。
「先生が退院してええよと言っても、1年は絶対に安静にしとかんといけません。白血病は一時的に治った後の養生が大切なんです」
同じカテゴリーの最新記事
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って
- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる
- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん
- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫
- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発



