押し寄せる苦しみの大波にも、「前進、前進」の心
看護師・鈴木厚子さん
普通の生活に戻りたい

鈴木厚子さん
(すずき あつこ)
看護師
初めて鈴木厚子さんに出会ったのは、都心にも秋の気配が濃い10月下旬のことだった。
「がん患者のメンタルケアについて、体験談を聞かせて欲しい」
そんな突然の頼みを快く受け入れて、わざわざ池袋のホテルまで出向いて来てくれたのだった。
鈴木さんは、どこか少女のような雰囲気を残した女性だった。一見華奢だが、そこから発せられる声には独特の力がみなぎっているように感じられ、そのことに私は強い印象を受けた。
鈴木厚子さんは1961年生まれ。結婚して一男一女を育てるかたわら、看護師として医療の現場で働いてきた女性である。
その鈴木さんが、がんの発病を契機として、いかにがんと向き合ってきたか。その経緯を聞くうちに、私は鈴木さんの言葉の一つひとつが不思議な輝きを放っていることに驚かされた。この人の話をもっと聞いてみたい、と思わずにはいられなかった。
「がんになったのをきっかけに患者会を立ち上げたり、フルマラソンに挑戦したりする方たちを見ていると、本当に素晴らしいと思います。でも、私自身にはそんなパワーはない。気功を始めようとか、そういうことがやりたいわけではないんです。ただ、今までと同じように仕事をして家族の世話をして、元の生活に戻りたいだけなんですよ」
こんな自分の話で役に立つのか、と鈴木さんは言いたげだった。だが、だからこそ話を聞きたいのだ、と私は思った。鈴木さんの言葉に力を与えているものの正体が何か、無性に知りたくなったからだ。
脳転移。泣きました
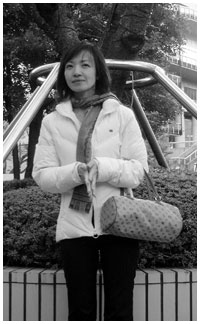
鈴木さんの平穏な日常が突然断ち切られたのは、2003年1月のことだった。職場の健康診断で、胸部レントゲンに異常が認められたのだ。
「診察室に呼ばれたとき、レントゲンの一部に赤く丸がしてあったんです。その瞬間、『何かとんでもないことが起こっているな』と思いました。『胸部レントゲンに異常があるからすぐにCTを撮りなさい』と先生に言われたとき、『ああ、がんだな』って」
すぐに呼吸器の専門病院を紹介された。持参したCTの画像を見せると、医師はこう言った。
「おそらく肺腺がんだと思います」。頭が真っ白になった。
鈴木さんはこれまで看護師として延べ10年間、現場で働いてきた。生死の実相を目の当たりにしてきただけに、「自分は大丈夫。告知を受けても動揺なんかしない」という自負もあった。
だが、入院手続きで書類に記入する段になって、受けた打撃の大きさを思い知った。手が震えて、字がどうしても書けなくなってしまったのだ。
「大丈夫だから、大丈夫だから」
呪文のように囁く夫の声を聞きながら、鈴木さんは放心状態だった。
「私が入院したら、子供のお弁当作りや洗濯はどうしようかなあ」
過酷な現実を直視するのを避けるかのように、そんな瑣末な心配ばかりが脳裏を去来したのを、鈴木さんは覚えている。
入院すると、数週間にわたって精密検査を受けた。診断結果は「4期の肺腺がん」。しかも「脳に転移が認められる」との医師の言葉に、鈴木さんは打ちのめされた。
「そのときは泣きましたね、もうダメかもしれないって。でも泣くだけ泣いたら、翌日にはケロッとしていました」
それは、告知と同時に、イレッサによる治療を医師から提案されたためだった。
「治療法について話し合ううちに、『もしかしたらイレッサが効くかもしれない』という気がしてきたんです。何か一つでも希望があれば、人間、立ち直れるんだなって思いましたね」
もっと謙虚に生きなさい
入院後、初めての外泊が許されたときのことだ。
鈴木さんは池袋の雑踏を抜け、電車に乗って家路についた。そのとき、不思議と周囲の人々の会話がひどく耳障りに感じられた。
「なんて無神経なのかしら、この人たちは自分がずっと生きられるとでも思っているんじゃないか……そんな風に感じてしまったんです。たぶん荒んでいたんでしょうね、私自身の心が」
自分自身がそうだったように、今この瞬間にも、秘かにがんを抱えながらそれに気づいていない人がいるかもしれない。医療に携わっていながら「自分だけは病気にならない」と自惚れていた、その傲慢さに臍をかむ思いだった。
「そのとき、神様にこう言われているような気がしたんです。『もっと謙虚に生きなさい』って」
鈴木さんの言葉を聞いて、私はこう思わずにはいられなかった。病気というものが神の与えたもうた試練だとするなら、鈴木さんに対して神はよほど多くのものを要求する決断を下したにちがいない。
なぜなら、彼女ほど真摯に患者の心に近づこうと務めてきた人も珍しいのではないか、そんな印象を私は受けていたからである。
誰にも人生のドラマがある

鈴木さんは1961年、青森県八戸市で生まれた。看護学校の受験を決めた理由は「仲のいい友達に誘われたから」。だから特に看護師になりたかったわけではないんです、と鈴木さんは苦笑する。
高校卒業後、全寮制の横浜赤十字看護専門学校に入学。アンリ・デュナン以来の赤十字の看護精神を受け継ぐ同校での3年間は、充実していたが厳しくもあった。
課題に負われる日々に音を上げたくなることもあったし、注射をするのが怖くて、看護師になるのを断念しようと思いつめたことさえあった。だが、実際に病棟勤務を始めると、鈴木さんは水を得た魚のように生き生きと働き始める。
「私は患者さんの話を聞くのが大好きだったんです。特にお年寄りは、戦争体験とか食料がない時代のこととか、私が絶対に体験できない話をして下さるんですね。それがすごく面白かったんです」
こんなこともあった。あるとき、今は板前をやっているという男性が注射のために服を脱ぐと、上半身に無数の切り傷があった。驚いている鈴木さんに、彼は誇らしげにこう言った。
「これかい? これは俺がヤクザだった頃に抗争で作った傷だよ。だから、ちっとやそっとの検査じゃ、俺ァ痛いなんて言わないのさ」
そんな話を、感嘆の思いで聞いたりもした。
「患者さんの苦労話は、皆さんが一番輝いていたときの記憶なんですね。そういう話を聞いていると、普通のお年寄りがとても素敵な人たちに思えてくるんです。楽しかったですよ、だから」
どんな患者にも人生のドラマがある。誰かと出会うたびに、まるで1冊の本を読むようにその人の人生が見えてくる――そんな鈴木さんの話を聞きながら、私はミヒャエル・エンデの作品『モモ』を思い出していた。
たしかモモは、人の話を聞くだけで相手を元気にすることができる女の子だった。目を輝かせて自分の思い出話を聞いてくれる鈴木さんを前に、どんなに多くの患者が心を癒されただろうか。そう思うと、私は胸の奥から熱いものがこみあげてくるのを覚えた。
同じカテゴリーの最新記事
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って
- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる
- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん
- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫
- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発



