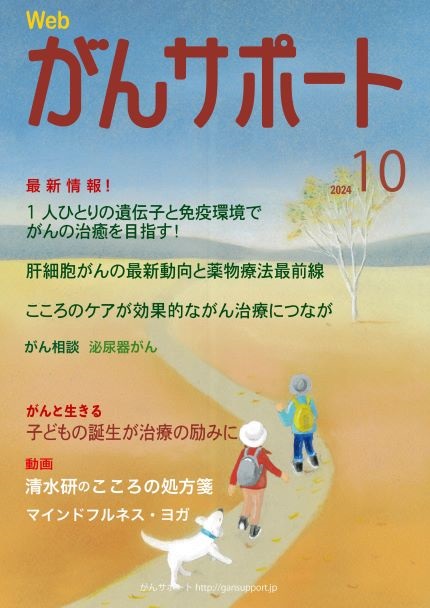絶望から立ち直った人工肛門のマラソンランナー
マラソンランナー、会社員・宮部信幸さん
人工肛門でフルマラソン

宮部信幸さん
(みやべ のぶゆき)
マラソンランナー、会社員
6月下旬の昼下がり、待ち合わせ場所の駅の改札口は蒸し暑かった。
そこへ宮部信幸さん(50歳)が、小さなリュックをかついで現れた。短く整えた髪、ラコステのスポーツシャツにスラックス、スニーカーというスタイルは、今にも走り出しそうな軽快さだ。日焼けした小柄な身体に、満面の笑顔がまぶしい。
7年前、直腸がんで人工肛門になった。ヘソの横に、便をためるための「パウチ」と呼ばれるビニール製の袋をつけている。そのままフルマラソンを完走する。
また、インターネット上では3年前、ホームページ「今日も元気でオストミー」を立ち上げ、人工肛門のケアに関する情報や自身の体験談を紹介している。
……と書くと、何だか“優秀な患者”という印象が強いが、宮部さんが「ケア」「マラソン」「仕事」のバランスをうまく取れるようになったのは、わずか2年ほど前からだ。
かつてはケアがうまくいかなかった。心を閉ざし、ジョギングをしながら涙を流したこともあったという。
どうやって笑顔を取り戻したのだろうか。
マラソンで自信をつける
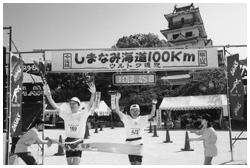
1981年2月。京都マラソンの開始を告げる号砲が、西京極陸上競技場の上空に響いた。
当時、28歳の宮部さんは、大勢のランナーとともにスタートを切った。初めてのフルマラソンだ。沿道に立つ観衆の声援を受けながら、ひた走る。折り返し地点付近で、テレビカメラを意識し、スピードを上げた。
ところが平安神宮の鳥居をくぐったとき、失格の白テープに行く手を阻まれた。この大会ではいくつかの “関所”があり、先頭走者から15~20分離れると失格になる。
「走らせろ! 何で止めるんや!」
宮部さんは大会役員に食ってかかった。ルールを知りつつも、走りたい一心でわけがわからなくなっていた。ふだんはウサギのようにおとなしい人が、「走り」にはチーターのような闘争心でいっぱいの人になる。
高卒で今の会社に入り、3年目から社内の野球クラブに参加した。体力づくりのために走っていたのが、後に社内に駅伝部ができたこともあって、走るほうがメインになった。25歳ごろから距離を延ばしていく。
仕事で辛い日も、走れば「今日も1日いい日だった」と思える。毎日走り続け、タイムを延ばすことが、いつしか自分に対する自信になっていたという。
京都マラソンの2週間後、篠山ABCマラソンを2時間45分台で完走した。その後も、社内の友人と一緒に、近畿を中心としたレースに次々と挑戦する。距離の短いものも含め、年に10大会以上走っていた。
がんになって真っ先に心に浮かんだのも、マラソンのことだった。
主治医もランナー
1997年8月、宮部さんは1週間続く便秘を抱えて受診した。2カ月前、父親が胃がんで手術していた。そのときの50歳代の主治医が、診察するなり表情を変えた。
「今日から入院してください」
不安を感じながら、着替えを取りに帰った。高齢の両親と3人暮らしだ。父親が退院後間もないこともあって、両親には「大丈夫やから」と詳しく話さずに入院した。
検査の結果、肛門付近に大きな腫瘍があり、人工肛門にしたほうがいいとわかる。
手術後、目覚めると、人工肛門にパウチが貼りつけられていた。人工肛門には、肛門にあるような筋肉や神経がない。便がいつ出るかわからないのでパウチが必要だ。
宮部さんはため息をついた。もうマラソンなどできないと思ったのだ。
主治医はジョギング好きで、フルマラソンも走っていた。朝夕に、糖尿病や高血圧の患者とともにウォーキングをしていた。宮部さんも術後1週間でその仲間に加わる。最初は5分しか歩けなかったものの、回復してくると、主治医とランニングをした。
ある日、初めて全力で1キロほど走れた。
「先生、走れるわ! うれしいわぁ」
「すごいなあ!」
主治医や入院仲間が笑顔で迎えた。別の日、主治医が病室にマラソン大会の申し込み用紙を「一緒に出ようや」と持って来た。冬に開かれる、10キロの大会だ。
「先生、僕、マラソンしていいんですか?」
「大丈夫やで」
宮部さんは希望をつないだ。
思うように仕事ができない
入院の2カ月後、職場に復帰した。もとの肛門に、神経痛のような痛みが続いていた。じわじわと締め付けられるように痛い。まっすぐに歩けず、カニ歩きになる。人工肛門から臭いが漏れそうな気がして電車やバスには乗れない。痛くて自転車のサドルに座れないので、立ちこぎをしたまま、職場まで8キロの道のりを通った。
宮部さんの仕事は機械加工だ。金属をスクリューやシャフトなどの部品に削る。大きな部品の場合、20キロもの鉄の塊をしゃがんで持ち上げ、機械の前に置かなくてはいけない。しゃがむたびに、うめき声が漏れる。パウチの辺りの不快感が気になる。
人工肛門のパウチは出社前に取り替え、職場でも2度替えた。人目を避けて、工場内の空き部屋に向かう。最初のころは使い捨てのパウチの汚れもきれいに水洗いしていたから、1度取り替えるのに、30~40分もかかった。下痢のときは袋を取ったとたんに、便が吹き出すことがある。汚れた下着を脱いでズボンをはき、早退したこともある。思うように仕事ができず、暗い表情でため息ばかりついていた。
それでも、走っている間は身体の辛さを忘れた。入院中に知り合ったランナーと、毎朝ジョギングをし、週末は2時間ほど走る。出血してパウチが赤く染まることもあったという。それでも術後3カ月で、福知山(フル)マラソンに出場した。
持参した一人用のテントでパウチの処理をして、着替える。ゴムを切ってだぶだぶにしたジャージをサスペンダーで吊り、上から大きめのTシャツを着た。
腹部を締めつけないように必死で考えたこのスタイルが今ではおかしい、と笑う。
「あのとき、会社の陸上部の先輩に『ど素人の格好やなぁ』と言われました(笑)」
3時間53分でフルマラソンを完走できた。テントに戻るとうれし涙が出たという。その後もハーフマラソンなどに出場した。 ところが、順調に思えた術後半年ごろ、人工肛門の周りがかぶれだした。
「洗腸」にとらわれていた孤独な日々
1998年1月、かぶれが始まった。処方された軟膏を塗っても、よくならない。悪化し、2カ月後にはパウチも貼れないほどになった。ただでさえ満足に仕事ができないのに、出社もできない。すがる思いで、別の病院の「ストーマ外来」を受診する。かぶれを見た看護師が声を上げた。
「こんなの最近、見たことないわ!」
原因はパウチの素材が肌に合わないためだった。製品を変えると、1週間で治った。
この外来で、人工肛門からぬるま湯を入れて「洗腸」する指導を初めて受けた。500~1000ccの湯を点滴の仕組みで入れ、たまっている便をすっきりと流し出す排便法だ。これをすれば1~2日、排便を気にせずに過ごせる。帰宅すると毎晩、トイレに約1時間籠もって、洗腸を続けた。
ところが腸が敏感なのか、ぬるま湯がうまく入らない。100ccも入れないうちに、すぐに湯が逆流して便が出てくる。平均数時間、最長でも24時間しか持たない。
気持ちがふさいでいく。職場で同僚が「どうや?」と声をかけてきても、「ほっといてくれ」と顔を背ける。「飲みに行こうや」と誘われても、黙って首を振る。職場の人間とほとんど口をきかず、家と会社を往復するだけの日々が半年以上続く。ついに絶望し、洗腸の道具を押し入れにしまった。
その年の忘年会シーズンになった。下痢を心配する自分には飲み会など無縁だと、宮部さんの気持ちは冷めていた。職場の納会には仕方なく顔を出す。乾杯の1杯は同僚がコップにビールを注いでくれたものの、その後はみんな気まずそうな顔で話しかけてこない。宮部さんも暗い表情で俯いていた。沈黙の時間がたまらず、年末の挨拶もろくにしないまま、席を立ってしまった。
帰り道、涙が止まらない。自分がイヤで、死んでしまいたかった。正月明けには、ストレスが原因らしきめまいにも襲われた。
当時の宮部さんにとって、ジョギングだけが自分を支える手段であり、精神安定剤だった。泣きながら無心で走り続けた。
同じカテゴリーの最新記事
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って
- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる
- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん
- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫
- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発
- 仕事優先で放射線治療+ホルモン併用療法を選ぶ 思い立ってPSA検査すると前立腺がん