絶望しながらも「何とかして生きていたい」と願う。そんな葛藤が続いています
詩人・福島登さん
癌抱の男

福島登さん
詩人
その日、春風の中、私は京都・四条大宮の駅前でジャーナリスト・柴野徹夫さんの車に拾ってもらった。黒っぽいセダンに乗り込みながら、初対面の挨拶を交わす。2回り離れた物書きの先輩が、取材の案内役を買って出てくれた。
柴野さんは2003年4月、詩人・福島登さん(73歳)の初めての詩集『すずかけの樹』(つむぎ出版)を世に送り出した。ハンドルを切りながら、柴野さんがバリトン歌手のような声でその経緯を話す。
「福島さんと30年ぶりに再会した2003年1月、すでに彼は肝臓がんの末期でした。弱々しい声で『よう来てくれたなぁ』と言った。50年以上書きためた原稿はどうしたの? と聞くと、押し入れで眠ったままだという。『あの労作を本にしないで死んじゃう気か、あなたは!』と僕は叫んでいました」
車は、伏見・醍醐寺に近い団地に向かっている。高層の集合住宅で、福島さんは妻・黎子さん(72歳)と暮らしていた。
10年前の1993年、福島さんは肝臓がんの摘出手術を受けた。以来、6回再発し、入退院を繰り返している。詩集には自身を「癌抱の男」と表現する詩がある。
重い引き戸を開けて声をかけたが、応答もなく気配もない。
黄ばんだガラスケースに、アンティークのような計器類が並んでいた。
「おこしやす……」
帰りかけたとき、何やらなまめかしい声が闇の奥から聞こえ、辺りの物を伝いながら、老女が現れた。
「一メートルのカネの物差しはありますか……」
「はいはい、ございます」
しっかりとした口調で、壁面の一隅を指した。
私は靴を脱いで板の間に上がり、油紙にくるまれている物差しを、長刀の鞘を払うように抜き出し、差し込むにぶい光にかざした。
墨で刻まれた精緻の目盛りと、区切りの朱を鏤めたこのやいばは、そのとき自らの重みに激しく身震いし、怪しい光を放つのだった。
白寿にもほど近いと思われる女性の、おぼつかない立ち居振る舞いと、還暦をはるかに過ぎた癌抱の男がひととき、老舗の梁の下で今生の見切り、この世の見納め、すさまじい道行きの趣。
「領収書をお願いします」
「はいはい、わかりました」
相方はふるえる手でしたため、我もまた小刻みにふるえて受け取り、見れば解読不能。
流れるままの一条のせせらぎであった。
〈福島登著『すずかけの樹』、「せせらぎ」より〉
臨場感あふれる、無駄のない描写に、古文を読んでいるような気になる。私は福島さんの世界に引き込まれ、「ギリギリのところで生きている緊張感」に息をのんだ。
ランボー詩集をポケットに

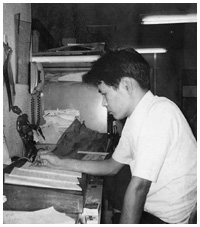
福島さんはその日、端正な顔を曇らせていた。目鼻立ちと広い額が人気俳優のキアヌ・リーブスにどこか似ている。控え目な人なのだろう。表情は穏やかだ。
が、詩集の出版で柴野さんに見せたという目の輝きは、どこへ行ってしまったのだろうか?
話が一段落すると、こう繰り返す。
「こんな話で記事になるのかなぁ……」
福島さんの心配は、長年、印刷・出版の現場で培った「作り手感覚」からきている。1995年に65歳で定年退職するまで、出版部を持つ印刷会社で41年間働いてきた。
満州事変が勃発した昭和6年(1931年)に、福島さんは生まれた。「戦時中の子」らしく、小・中学生のころの「死」のイメージは、神風特攻隊として敵艦もろとも自爆するというものだったという。
しかし軍国少年も、文学や映画に魅かれる気持ちは抑えきれなかった。学徒動員先の薬莢工場では、黒澤明監督の『姿三四郎』を観るため、壁を乗り越え抜け出した。工場長に説教されても懲りない。作業をさぼっては、織田作之助の作品を読みふける。
だから16歳で敗戦を迎えたとき、真っ先にクビになって、放り出された。ポケットにランボー詩集を入れて、闇市をうろついていたという。
「子ども心にも価値観が一変したんやね。制度も聖戦というのも全部ウソやったやないかと。闇市文学や世界の文学を片っ端から読み、『カサブランカ』などの映画を夢中で観た。自分でもわけのわからん文章を書いて、仲間が集まり、同人誌を作った」
20歳で肺結核を患ったのち、『洛北文学』という雑誌を手作りし、京大の前などの本屋に置かせてもらった。小説も書いた。
ガリ版で個人新聞も始めた。それが印刷会社の人の目に止まり、「社員」としてスカウトされた。24歳になっていた。
誰よりも早く出社し、デザインの仕事に取りかかる。薄暗い部屋の片隅で片膝を立てながら、黙々とガリを切る姿を、かつての同僚たちが覚えている。独特の技法・多色刷りの美しさは“伝説”になっている。
入社以来、無遅刻・無欠勤で深夜まで仕事に打ち込んだ。会社が印刷だけでなく企画・出版まで手がけるようになると、取材して原稿やコピーを書き、編集もした。
ふと気づくと夜が明け、大きな灰皿から吸い殻があふれていたこともざらだったという。その間もずっと、詩人として同人誌『階段』の活動を続けていた。
「書くことは自分では趣味じゃない(笑)。やむにやまれぬ生き方なんですね」
1991年、C型肝炎ウィルスに感染していることがわかった。インターフェロンの投与でウィルスは姿を消したものの、すでに肝臓にがんができていた。
1993年、63歳で福島さんは肝臓がんと胆嚢を摘出する手術を受けた。
がんが「臓腑と顔面」を叩きつぶす
以来、4年、3年、2年、6カ月……と徐々に期間を短くしながら、がんは再発した。そのたびに「*経皮的エタノール局注療法(PEIT)や「*経カテーテル肝動脈塞栓療法(TAE)などの治療でがんを叩く。
闘病への思いを次の作品で表現している。
応接コーナーに、白髪の老人が腰を掛けていた。
そばを通りかけたとき、私を見た。何か言おうとしたが、見知らぬ人だったので、私は無視した。
あとで対応していた同僚に、どういう人だったのか、と尋ねてみた。
私は自分の鈍感さを悔やんだ。
その人なら、まだ五十代。やり手の社長で、かつて私はその社のシンボル・マークをデザインした。彼はその頃、精悍な風貌で油ぎっていて、手首まで剛毛が生えていた。大声で傲慢に喋った。
彼を叩きのめしたものは、私がデザインした、あの諸刃の斧のようなものではないか、と思った。
切り株の無数の年輪の上に、北欧の樵が持つような巨大な斧が打ち込まれている造形だった。年輪は既成の権威とか伝統といったもので、新興の彼の事業は輝く鋼鉄の斧であった。
落ちぶれて、私に話しかけようとしたが、私は分からず通り過ぎた。
数年たって、私は大きな手術をし、入退院を繰り返した。久しぶりに職場を訪ねてみると、見知らぬ職員が幾人もおり、かつての同僚や部下たちも忙しそうに働いていた。応接コーナーに、ひとり腰掛けていると、冷徹な一撃で打ちのめされた人よりも、はるかに激しく、あの重い斧が、私の臓腑と顔面を叩きつぶしたことを知った。
〈作品『斧』より〉
度重なる治療によって、福島さんの肝臓は大きなダメージを受けた。血管造影をすると、肝臓内の血管があちこちで寸断されているという。では「顔面を叩きつぶした」とは、どんな意味か?
「映画などで『50年経ちました』と、役者がパッと老人のメーキャップで登場するでしょう? それと同じで、がんはものすごい力で風貌まで変えてしまった」
と言う。そんな心境をつづった詩もある。
―――どんなに格好悪くなっても生きていてください
かつてそう言ってくれたひとがいた
〈作品『恋』より〉
2002年には、PEITの副作用による敗血症で死の淵をさまよった。寝ても覚めても「幻覚」が現れたという。
幸い、抗生剤が効いて一命をとりとめた。
その年の暮れには、破裂寸前の食道静脈瘤を治療した。
*経皮的エタノール局注療法=超音波装置(エコー)を使って肝腫瘍を見ながら腫瘍に細い針を刺し、無水エタノールを注入する治療法
*経カテーテル肝動脈塞栓術=足の付け根から動脈に管を入れ、がんの部分に直接抗がん剤と血流を遮断する物質を注入する治療法
同じカテゴリーの最新記事
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って
- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる
- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん
- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫
- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発



