「いい加減な医者」はぶっつぶすつもりで活動しています
「癌と共に生きる会」会長・佐藤 均さん
「うまい」!? 抗がん剤治療
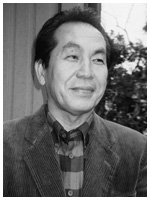
佐藤均さん
「癌と共に生きる会」会長
「医療では“舌の肥えた患者さん”は少ない」と、外科医が話すのを聞いたことがある。そのココロは、「同じ手術を2度受けるわけにいかないから」だ。
たしかに、医療の「良し悪し」を患者が評価するのは難しい。ところが、たまたま同じ治療で、「うまい」「まずい」の両方を味わった人がいる。
佐藤均さん(55歳)は、島根県出雲市に住む、フリーのテレビカメラマンだ。地元テレビと契約し、報道の最前線に立つ。
気のいい長男坊らしく穏やかな物腰だが、ふとした瞬間に見せる眼差しは鋭い。20数年前、居酒屋を経営していたアマチュアカメラマン時代に、腕を買われてプロになった。
約3年前、大腸がんを手術した。肝臓への転移を経て、肺に多発性の転移がある。佐藤さんは「うまい」抗がん剤治療を受けたのをきっかけに、がん医療を変える活動を地元で始めた。どんな経験をしたのか、ぜひ聞いてみたい。年の瀬が迫ったある日、私は大阪から高速バスで出雲に向かった。
息子さん一家と同居する大きな家で、佐藤さんはにこやかに語る。
「がんが自分の生き方まで変えちゃったんですよ(笑)」
点滴の針が抜けたら、トイレへ駆け込む
2001年4月、佐藤さんは島根医科大学病院でS字結腸がんの手術を受けた。主治医は、取材を通じて以前から知り合いの助教授だ。腕利きの外科医だと知っていたので、佐藤さんは信頼していた。
手術の結果、がんは腸の壁を突き破り、外側にもおよんでいた。
「先生、僕の再発率は?」
「50パーセントです。抗がん剤治療を18回受ければ、何とか大丈夫でしょう」
佐藤さんは「18回か」と腹をくくった。そして「まずい」抗がん剤治療が始まった。
抗がん剤・5-FU(750ミリグラム)に、*アイソボリンを加えた治療だ。副作用で食欲が落ち、9キロ痩せた。
退院後も2週間ごとに抗がん剤を打ち、ひどい吐き気に襲われるようになった。
病院に着くと、まずトイレのドアを開けておいて外来に向かった。点滴が続く30分間、ギリギリまで我慢し、針が抜けた瞬間、トイレに駆け込み、「がーっ」と吐いた。主治医は「白血病の治療などと比べると、大腸がんの5-FUは入門編。根性で乗り切りましょう」と言う。
治療日とその翌日は、吐き気で集中力がまったく出なかった。3日目、少し落ち着くと、約10キロのカメラをかついで仕事に出る。身体がふらつき、肩で息をしているような状態だ。ペアを組む記者は動きの少ない楽な仕事を回してくれた。ファインダーをのぞくとカメラマン根性が出て、やっとのことで仕事をこなしていたという。点滴後2週間経つと、身体が回復してくる。
「すると、追い討ちをかけるように、また点滴の日が来るわけですよ(笑)。脳が記憶しているのでしょうね。大学病院に向かう途中から気分が悪くなるんです。建物が見えるとひどくなり、病院の臭いをかぐともうたまらない。そこに点滴を打つわけです」
仕事を断らずに続けるだけで精一杯で、家族と話をする気にもなれなかった。かつて、カメラを肩に1日中走り回り、夜遅くまで飲み歩いていた佐藤さんとは別人のようだ。
受診日が近づくと無口になり、点滴後は体調を崩す。夫の苦悩を見守る妻・愛子さんも、心労でたびたび倒れ、寝込んだ。
佐藤さんがしみじみと語る。
「18回受ければ再発がないと思って、半年間がんばったんですからぁ。自分をほめてやりたいですよぉ」
ところが抗がん剤治療を終えて10カ月後、肝臓への転移が見つかる。つらい治療に耐えてがんと縁を切ったつもりだっただけに、ショックは大きかった。
それでも主治医から「1個の転移だから、完治する確率が50パーセントもある」と説明され、2度目の手術を受けた。
*アイソボリン=一般名レボホリナートカルシウム。抗がん剤が効きやすいよう、がん細胞の状態を整える薬
「こんなもんじゃ、効きやしませんよ」
術後のある日、佐藤さんは東京出張のために向かった出雲空港で、知り合いのがん患者と偶然出会った。その女性は「今から東京へA医師の治療を受けにいく」と言う。A医師は、診療の完全情報公開で知られ、外部の患者に対しても「がんの相談室」を開設している東京の専門医だ。
興味を持った佐藤さんはその日の仕事を取りやめて、早速その女性が入院する病院を見学した。自分でも調べてみて、その治療が「正しい」と思えた。「こんど再発・転移が見つかったら、絶対ここにセカンドオピニオンを聞きに来よう」と考えたという。
その機会は半年後に訪れた。2003年3月、また肝臓に転移が見つかったのだ。
すぐA医師の元に飛んでいき、セカンドオピニオンを求めた。再手術を受けるか、ラジオ波焼灼療法にするかで迷っていた。A医師は佐藤さんのデータを見るなり、こう言い放った。
「5-FUは750ミリグラムを18回投与しても、13.5グラムです。こんなもんじゃ、効きやしませんよ。こういうのを『アリバイ的治療』と言うんです」
佐藤さんは、あまりの衝撃で椅子から滑り落ちそうになった。主治医を信頼していたから、初めはA医師に腹が立った。
ところが1時間ほどじっくり話を聞くうち、A医師の意図するところが佐藤さんにもわかってきた。A医師は言った。
「最低でも5倍の抗がん剤を、半年から1年ぐらいやらないとダメですよ」
「そこまでおっしゃるなら、僕の治療を引き受けてください。お願いします」
「なぜ私が、あなたの治療を引き受けないといけないんですか?」
佐藤さんはまじまじとA医師の顔を見た。予期せぬ展開にまたしても動揺し、ただただ「お願いします」と繰り返す。すると、A医師はこう話した。
「日本の抗がん剤治療は、『外科手術のアフターサービス』でしかありません。患者ががんの手術で払ったお金は病院の収入になりますが、抗がん剤治療の場合、お金のほとんどは病院の会計を素通りして、製薬会社に直行します。そんな儲けのない治療をなぜ私がやらなくてはいけないんですか。
でもあなたがそんなに言うのなら、2カ月間ほど治療を引き受けましょう。ただし、私はタダ同然で診ますから、あなたは日本のがん医療を変えるために何かやってください。できなければ治療を打ち切ります」
また「診る条件」として、患者も自分の情報をきっちり把握し、医師とともに徹底した討論の上で治療を進めていくことなどを挙げた。佐藤さんはそれを承諾した。
「これまで90パーセントの人が、1~2カ月で治療打ち切りになったんですって。でも僕はわずかな望みに賭けました。死にたくなかったから」
「別世界」の抗がん剤治療

島根に帰ると、とりあえず近所の人たちに、日本のがん医療の問題点について話して回ることから始めた。日本には抗がん剤治療の専門医(腫瘍内科医)がほとんどいないと説明すると、みんなは「まさか!」と信じなかった。
3月下旬、大学病院で肝臓転移に対するラジオ波焼灼法を受けた後、佐藤さんは上京した。初めてA医師の治療を受けるためだ。
抗がん剤5-FU(500ミリグラム)にアイソボリンという組み合わせは同じだが、点滴のやり方(*クロノテラピー)が違う。夜間にするのだ。抗がん剤を効果的に使い、副作用を抑えるためで、吐き気止めには、ガスモチンとナゼアが使われた。
翌朝、佐藤さんは6時に目覚めた。気分はそう快だ。ベッドから恐る恐る起き上がると、病室を抜け出し、階段を小走りに駆け下りてみた。吐き気がまったくない。まるで「別世界」だった、という。
「島根に帰るとすぐ前の主治医に、『こんないい治療をしてください』と、治療の記録を見せに行ったほど。でも彼は関心のないそぶりでそれを見ようとはしなかった」
A医師の医療の進め方も、佐藤さんには新鮮だった。患者は病院のパソコンで自分の検査結果をチェックする。共有する情報をもとに、薬の量や治療方針を相談する。患者はテープレコーダーを持参して、医師の説明を録音し、繰り返し聞いて理解する。
「僕の場合、5-FUを750ミリグラム、1000ミリグラムと増量するときにも相談されました。OKを出すのは患者です」
吐き気止めの場合、幅を持たせて量が示される。副作用に注意しながら、患者は自分の適量を探っていく。医師と対等な関係だけに、患者も受身ではいられない。テープの準備を怠ろうものなら、その日の診察はたちまち終了だ。気の抜けない“真剣勝負”だったという。
*クロノテラピー=正常細胞が活動を低下させ、がん細胞の活動が活発化する夜間に抗がん剤治療を投与することによって、がん細胞に対する効果を高め、正常細胞に対するダメージを抑えて副作用を抑える治療法
同じカテゴリーの最新記事
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って
- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる
- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん
- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫
- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発



