患者と医療者が互いに興味を持てば医療現場は変わるはず
諦めずに患者の声を医療の側にフィードバックし続けたい・内田スミスあゆみさん

内田スミスあゆみさん
(会社役員)
うちだスミス あゆみ
1966年、静岡県生まれ。
国際基督教大学卒業。就職後に米国の大学院へ1年間公費留学。
その後、外資系企業に勤務していた1994年、小脳血管芽腫に起因する水頭症を発症。
2度の手術のあとにくも膜下出血をおこし、3度目の脳外科手術を受けた。
著書に、その間の闘病の記録をまとめた『東京タワーに灯がともる』(新風舎)がある。
現在は夫のデイビッド・スミスさんとともにコンピュータ・ソフトウエアの仕事をする傍ら、翻訳などの医療ボランティアもしている。昨年、長男を出産。
初めて人と人として話すことができた日
「初めて患者さんの声を聞きました。とても勉強になったので、医局でみんなに回して読ませています」
J医大のA教授が穏やかな笑みを浮かべながらそういったとき、内田スミスあゆみさんは心の中で、「書いてよかった」と、しみじみ思った。
内田さんは自らの闘病の記録を『東京タワーに灯がともる』(新風舎)という本にまとめ、1997年に出版した。冒頭の言葉は、内田さんの手術を執刀したA教授がこの本を読んでの感想だ。
「この感想をお聞きしたとき初めて先生を怖いと思わずに話ができましたし、初めて人と人として話すことができたと感じました。A先生はとてもやさしく、権威ぶるようなところのない方ですが、入院しているときはやはり私は先生にとって患者の一人でしたし、私という人間ではなく症例しか見ていただけてなかったと感じていたんです」
回診のときもいつも気後れして、医師には何も聞けないでいた。仕方ないので看護師に質問すると、「それは医師でないと答えられないので、先生に聞いてください」と言われるだけだった。
「自分は割と強い人間だと思っていたのですが、患者になるとものすごく弱くなってしまうんですね。健康なときは告知でもなんでも受けられると思いこんでいましたが、こんなに変わるものかしらと、自分でも驚くくらいでした」
医療の現場では、患者はどうしても弱い立場に立たされがちだ。だからつい“いい患者”を演じようとしたり、医師に対して言いたいことがあってもグッと飲み込んでしまったりする。しかし内田さんの場合はそういうことだけではない。闘病の過程で、医師に対して不信感を持たざるを得ないような経験を、いやというほどしてきたのである。
風邪がいきなり入院へ
1994年6月、内田さんは頭痛と熱に悩まされていた。勤め先で机に向かっていると、頭の中央に向かって切り裂くような痛みが走り、やがて悪寒がして高熱が出る。そんな症状がしばしば起きていたのだ。
激しい頭痛はその1年くらい前からときどきあった。だから会社の定期検診のときには医師に相談もしている。ストレスに起因する精神的なもの、というのがそのときの医師の答えだった。
けれども症状はだんだんひどくなり、しかも頻繁に起きるようになっていた。そのため内田さんは何回か病院を受診している。
「風邪でしょう」
どこの病院へいっても、返ってくる答えは同じだった。しかし風邪薬を服用しても一時的に熱が下がるだけで、しばらくするとまた症状がぶり返す。そのたびに内田さんはまた別の病院にいった。「前の病院でも風邪だと言われたが、全然よくならない」と訴えても、対応は変わらなかった。
「今、思えば同じ病院に通い詰めて、結果が出るまで何度も調べてもらえばよかったのでしょう。でも1度行った病院は、どうせまた風邪と言われるのだろうという気持ちになってしまうんですよ」
そうして3カ月が過ぎたある日の朝、内田さんは頭痛と熱に加え嘔吐もするようになっていた。そこで苦しい体を引きずるようにしてまた別の病院を訪れると、そこでようやく初めて検査を受けることになった。このとき受けたのは、尿検査、血液検査、甲状腺の検査、CT。3日後、検査結果を聞きに再び訪れると、CT画像を見ながら医師は「頭のなかに何かあるので、すぐにS大学病院の脳外科を受診するように」と言い、こう付け加えた。
「入院になるかもしれませんね」
どこへいっても「風邪」の一言ですまされていたのが、初めて検査を受けたらいきなり入院の可能性を示唆され、内田さんの心のなかでは困惑と同時に医師に対する不信感がふくらんでいった。
手術後の患者をゴルフに誘った医師がいた

入院中の内田さんの様子をお姉さんが描いたイラスト。
周りの字は手術後の筆談を切り貼りしたもの
9月、初めて訪れたS大学病院の脳外科では、その日のうちの入院と手術を言い渡された。何がなんだか分からないまま病室で入院手続き用の用紙に必要事項を記入していると、「ほう、字が書けるね」という声がした。気がつくといつの間にか4人の医師が並んでいた。そして病状についての説明。
「頭のなかに何かできているため髄液の流れが止まり、水頭症を起こしている。だからとりあえず溜まった髄液を取り出すための緊急手術が必要。とにかく今、こうして話をしているのが不思議なくらい深刻な状態です」というのが医師の説明だった。
このときはもう不信感を通り越し、内田さんは医師に対して敵意に近い感情を抱いていた。
「それまで風邪だと診断してきた先生たちはいったい何を診てきたんだろうという感じですし、手術が必要だという先生もちょっと極端すぎておかしいのではないかという気がしました。もう医者の誰が何をいっても信じられないという気持ちでした」
医師たちはここまで内田さんの不安を取り除こうという努力をしてこなかった。内田さんの心の声を聞こうという姿勢もほとんど見せていない。コミュニケーションがまったく成立していないのである。だから内田さんの心のなかでは病気に対する不安と医師に対する不信がどんどん蓄積されていったのだ。
「大丈夫だから、すべて大丈夫ですからね」
さすがにこれではまずいと思ったのだろうか、内田さんに病状の説明をした医師は病室を出ていく間際に一言、そう声をかけていった。
「私はずっとこの言葉を待っていたのです。この一言を聞いて、初めてこの先生にすべてを委ねようという気になりました」
幸い、手術はうまくいった。だがこのとき内田さんは医師に対する感情をさらに悪化させるような体験をした。それは手術が終わった直後のことだ。麻酔が覚め、朦朧としながらも覚醒していた内田さんの耳に、そばにいた医師たちのこんな会話が聞こえてきたのである。
「今週末のゴルフ、メンバーが一人足りないんだけど、どうしようか」
「そうだ、内田さん、ゴルフする? 明後日、一緒にいかない?」
説明会から外された患者の孤独
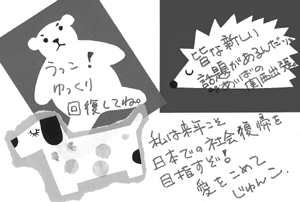
入院中の内田さんのもとには、
友人からの励ましの手紙がたくさん届いた
「怒りの感情はありませんでしたが、ものすごく悲しかったですね。この人たちにとって私の生命はとても軽いものなんだな、と感じたからです。きっと難しい手術を無事終えたことで、安心してつい軽口をきいたのでしょう。私の意識が戻っていることにも気がつかなかったのだと思います。でも患者を物体として見るか人間として見るかというのは人間性の問題ですからね。もう少し気をつけてもらいたいと思いました」
この後、内田さんはJ医大病院に転院する。親しくしていた従兄弟がJ医大病院に勤務していて、熱心に転院を勧めたからだ。
J医大病院に移ってからはまたいくつかの検査を受け、10月6日に水頭症の原因となった腫瘍を取り除く手術を行うことが告げられた。このとき主治医は、手術の前日に行う家族向けの説明会に内田さんも同席するかどうか尋ねた。これに対して内田さんははっきりと、同席することを伝えた。
だが、説明会に内田さんは最後まで呼ばれなかった。説明会が終わってからA教授らが病室に現れ、手術の説明をした。けれども説明会から外されたことによるショックが大きく、医師の説明はほとんど頭に入らなかった。
小脳血管芽腫、それが内田さんの病名だった。脳腫瘍の一種で、再発や転移することは少ないが、手術は難しく、このときの説明会では成功率が50パーセント以下であると家族に伝えられていた。内田さん自身が病名と手術の成功率を知るのは、手術が終わってからのことだ。
「今思うと、説明会から外されてかえってよかったという気がします。手術の前日に50パーセント以上は死ぬと言われたら、死刑宣告のようなものですよ。あのころは病院に対する不信感もあったので、そんなことを聞かされたらとても耐えられなかったと思います」
同じカテゴリーの最新記事
- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に
- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる
- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら
- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して
- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん
- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って
- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる
- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん
- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫
- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発



