終末期を自宅で過ごすがん患者さんや家族が直面する、さまざまな問題
医療者には患者さんの生活や人生も見てほしい

「在宅療養ボランティアさくら」代表の
中村克久さん
終末期を自宅で過ごしたい──。そう願うがん患者さんは多いが、医療と介護の連携の不十分さ、患者さんたちが抱える孤独など、さまざまな問題が立ちはだかり、実現を阻んでいる。そこで、終末期のがん患者さんや家族を支えるボランティアが、1つの提言を示してくれた。
自宅で最期を迎える人は1割強
あなたは、余命6カ月の末期がんと言われたとき、最期の場所として、どこを望みますか。
2008年に厚生労働省が実施した「終末期医療に関する調査」によると、自宅で療養し、必要になれば医療機関や緩和ケア病棟への入院を希望する人と、最期まで自宅で過ごして看取られたいと希望する人の合計は、約63パーセントを占めている。その一方で、約66パーセントの人が自宅で最期を迎えることは実現困難と考えている。「介護してくれる家族に負担がかかる」(約80パーセント)が最大の理由である。そして、実際に09年に全国で亡くなった方のうち、自宅で看取られた方は、約12パーセント。しかし、がん患者さんに限ると、約7パーセントしかなかった。
07年に施行された「がん対策基本法」により、国は早期からの緩和ケアの必要性を明言し、在宅での療養体制の整備の推進を掲げた。しかし実際には、在宅緩和ケアの現状はあまり改善しているようには見えない。現場では、どんな問題が起こっているのだろうか。
東京西部に位置する立川市。ここにある、在宅医療・在宅緩和ケア専門の立川在宅ケアクリニックでは、がん患者さんを主として常時、約110人の在宅緩和ケアに携わっている。
在宅緩和ケアと在宅看取りに徹する同クリニック院長の井尾和雄さんの理念に共鳴し、終末期のがん患者さんや家族の生活面でのサポートをすることを目的に、クリニック内で傾聴ボランティアとして活動しているのが、「在宅療養ボランティアさくら」である。代表を務めるのは中村克久さんだ。
ケアマネージャーができる医療と介護の連携

中村さんたちは、料理や掃除・洗濯などの簡単な家事援助のほか、患者さんやご家族の話し相手、介護にあたるご家族が銀行や美容院などに行く間の患者さんの見守りや留守番、草花の水やり、愛犬の散歩、薬の受け取り、車での送迎など、介護保険制度により派遣されるヘルパーではカバーしきれない雑用などを手伝っている。現在、主に約15名が活動中である。
活動をするなかで、現在の在宅緩和ケアにおけるさまざまな問題が見えてきたと中村さんは言う。問題は大きく2点に集約される。1つは、医療と介護の連携がうまくいっていないこと、もう1つは患者さんやそのご家族が抱える苦悩についてである。
医療と介護の連携に関連して、中村さんはケアマネージャー(介護支援専門員)の位置づけの重要性を強調する。
「ほとんど治療をすることのない終末期のがん患者さんとご家族にとっては、医療よりも生活全般のサポートのほうが重要度が高いのではないかと気づきました。そこで重要な役割を果たすのは、ケアマネージャーです」
患者さんが医療機関を退院し、自宅に帰される際には、ケアカンファレンスの実施が義務付けられている。本来なら、このケアカンファレンスはケアマネージャーを中心として、病院のソーシャルワーカー、担当の在宅医、訪問看護師などが一同に会して行われるべきなのだが、実際にはあまり行われていないという。病院の地域連携室が在宅医に電話をして「今度、こういう患者さんが退院するからよろしくね」とあいさつして終わりだというのだ。
患者さんの生活に関心が薄い勤務医や開業医
「いまだに日本では医療が中心で、医師が1番偉くて、看護師は右にならえ。ケアマネージャーなどの介護職は軽視されているように思えます。しかし、とくにがん患者さんの場合は、生活面のサポートをするケアマネージャーを中心としたケアカンファレンスをきちんと行い、医療と介護の連携を図りながら患者さんを看るべきと考えます」
うまくいっていない理由として中村さんが考えるのは、まず病院の主治医が忙しすぎるということ。そして、医療面については主治医から在宅医にしっかりバトンが渡されるが、患者さんの生活面や介護に関しては、医師たちの関心が薄いのではないかということである。
介護保険を利用するためには要介護度の認定を受けなければならない。現在、末期と診断されたがん患者さんの場合は、要介護2程度までは認定されるという。しかし、退院する患者さんが介護保険の申請をしないケースもある。そうなると、当然ケアマネージャーは介入しない。申請しない理由はさまざまだろうが、妻や娘が介護すればよい、他人の介入を受けたくないと考えるケースのほか、老々介護が増えてきた昨今では、制度自体を知らない、内容が理解できない、どうやって申請すればいいかわからないという高齢者も多いだろう。いずれにしろ、そうすると介護する家族の負担がぐっと大きくなってしまう。
「病院の勤務医は1~2年で転勤することが多く、地元への関心が薄い。これはひいては、患者さんの生活に対する関心が薄いといえます。一方、開業医の先生方も介護に対する関心が比較的薄く、知識もあまりないように思います。診察時に、患者さんやご家族に『介護保険の申請をしたらどうですか』『包括支援センターに相談してみてはいかがですか』と一言添えてもらえれば、ケアマネージャーにつながるかもしれないのに、そこまで踏み込まない。総じて、医師たちは患者さんの人生を見ていないように思います」と中村さんの言葉は手厳しい。
いよいよ末期になるまで患者さんを手放さない病院
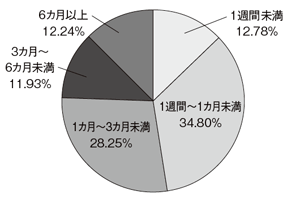
医療と在宅ケアとの連携という意味では、病院が患者さんをなかなか手放さないという問題があるという。立川ケアクリニックの場合、在宅療養を始めて1カ月未満で亡くなる患者さんが約48パーセントもいる。余命が3~6カ月と思われるにもかかわらず、緩和ケア病棟、在宅緩和ケアの紹介がないまま治療が続けられ、いよいよ手立てがなくなったら在宅医へ紹介される患者さんが多いのだ。
「これでは、自宅に死にに帰らせるようなものです。新薬を試したり、地方の小さな病院では経営を考えて、次の患者さんが入院するまで空きベッドをつくらないようにしているケースもあるようです。また、患者さんや家族側も『自宅に帰ったら、もう治療はできない。でも、病院にいて治療すれば、もう少しよくなるかもしれない』と、はかない期待を抱いてしまうのです」と中村さんは説明する。もっと元気なうちに帰宅できれば、最期までの時間をもう少し大切に過ごせるのではないだろうか。
中村さんが挙げる、もう1つの問題点が、患者さんと家族の抱える苦悩である。
土地柄もあるのかもしれないが、患者さん家族の特徴として、地方に住む1人暮らしの親ががんになり、結婚して立川市に住む娘さんが親を呼び寄せるケースが多いという。娘さん夫婦は共働きしていることが多く、家族が出かけた後、親御さんは知り合いのいない土地で、家に1人残されてしまう。午後になって小・中・高校生の孫たちが帰宅しても、ある日突然田舎からやってきた祖父母には親しみがないため、「おじいちゃん、ただいま」となつくことは難しく、患者さんはますます孤独になる。
また、多少動ける患者さんでも、方言が強いと周囲に溶け込めないため外出したがらず、孤独になってしまう場合も多いという。
患者さんを支える家族の問題としては、前述したような老々介護の問題や、介護の負担が挙げられる。介護保険により派遣されるヘルパーは、できる仕事にさまざまな制限があるため、近所の薬局に薬1つ取りに行ってもらうこともできない。家族は銀行にも美容院にも行けないまま、介護と家事と雑用に追われ、疲弊していくのである。
地域力・市民力・ボランティアの活用を!

これらの問題を解決する1つの方法として中村さんが提案するのは、知人・友人を含めた地域力・市民力の活用だ。「ボランティアさくら」が行っている活動は、その実践ともいえる。
「これからもっとがん患者さんは増えていくのですから、民生委員などをうまく活用しながら行政を巻き込んで、地域皆で支えていかないと支えきれないでしょう。強い方言のため、新しい土地になじめない患者さんに対しても、包括支援センターを通して市の県人会でその地方の出身者を探し出せたら、患者さんを孤独から救えるかもしれません。また、医療機関の医師、在宅医、開業医の先生方にはネットワークをつくってほしい。1人の医師だけががんばっても無理ですから。そして、私たちのようなボランティアを、患者さんを支える活動にもっと組み込んでほしいですね」
中村さんが出会った終末期のがん患者さんたちは、皆、「家に戻ってよかった」と口をそろえるという。十分に闘ってきた患者さんたちを自宅で安らかに看取れる社会づくり。がん患者さんが増え続ける今、その実現は、待ったなしの急務である。
在宅療養ボランティアさくら
〒190-0002 東京都立川市幸町5-71-16 コンフォートフラッツⅢ 1階 立川在宅ケアクリニック内
TEL : 080-1163-5281
ホームページ:http://www.tzc-clinic.com/homecare%20network.html



