最期のひとときを自分らしく生き抜くために、在宅ホスピスのすばらしさを伝えたい
在宅ホスピス――がん患者やその家族なら、誰もが聞き覚えのある言葉だろう。
人生最期のひと時だからこそ、我が家で精いっぱい、自分らしく生き抜きたい――。
自分らしく生きるための在宅医療

そんながん患者や家族の願いを実現するための医療活動だ。その在宅ホスピスを望む人たちを対象に、支援活動に取り組み続けている藤田敦子さんは言う。
「ホスピスというと死ぬための場所というイメージがあるかもしれません。しかし在宅ホスピスはそれとはまったく違っています。我が家というのは誰にとっても、その人の暮らしそのものを意味しています。そこで最期まで自分の人生を生き抜くことで本人はもちろん、家族も納得して死を迎えることができるのではないでしょうか。在宅ホスピスとは、患者が自分らしく生きることを支援するための医療活動なのです」
現在では、藤田さんの活動は患者やその家族の不安に答える電話相談から、在宅医療の専門家を招いてのフォーラム、さらには自治体と連携してのガイドブックの刊行など、広範囲に及ぶ。来年7月には、千葉幕張メッセで「日本ホスピス・在宅ケア研究会」の全国大会を主催する大仕事も待ち受けている。しかし、ここまでに至る道程は決して平坦なものではなかった。
夫を自宅で看取れなかったことが活動の原点
藤田さんのご主人に直腸がんが発見されたのは98年8月のことだった。1カ月後、がん専門病院で手術が行われた時には、肝臓への転移も明らかになっていた。その時点で藤田さんは余命1年以内と主治医から告げられていた。
その後、自宅に帰って通院による抗がん剤治療が開始される。しかし2カ月後、痛烈な下腹部の痛みに襲われる。腹膜への転移が原因だった。同じがんはさらに骨にも転移、そのため藤田さんのご主人は、別の病院で痛みを取り除く緩和ケアを受けることになる。そうした入院治療の間にご主人は何度か、病院の外泊許可を得て自宅に帰っている。藤田さんはそのときのご主人の姿が今も鮮明に脳裏に焼きつているという。
「38度~39度の高熱があったにもかかわらず、友人の電話を受けたり、片づけをしたりと自分の暮らしを楽しんでいた。ダイニングで『やっぱり家はいいなあ』と話していたときの生き生きとした表情は今も忘れることができません」
最期のひと時は住み慣れた我が家で過ごさせてあげたい――そう思った藤田さんは、病院に泊まりこみながら、在宅ホスピス医を探して病院から電話帳を片手に、役所や医療機関に電話をかけ続けた。しかし藤田さんの願いはかなわず、ご主人は病院で息を引き取ることになる。このときの無念の思いが、その後の活動につながっていると藤田さんはいう。
ご主人を亡くした後、自らの癒しと在宅ケアの大切さを訴えたいという思いから、藤田さんは患者会などの集まりに積極的に参加する。そうして、そこで在宅ケアに熱心だった服部義博医師と意気投合し、在宅ケア専門の診療所、さらに患者や家族を支援するNPОの立ち上げを企画した。診療所では藤田さんは患者と医療機関をつなぐコーディネーターとして働くはずだった。
状況が暗転したのはその直後のことだった。皮肉なことにがん患者の支援を進めていた服部医師自身ががんに見舞われたのだ。進行の早いスキルス性胃がんは肝臓にまで達しており2カ月後、服部医師は不帰の客となる。そうして藤田さんは再び絶望の淵に追いやられる。

しかし、藤田さんは果敢にも再度の失意から立ち上がる。やはり患者会などの活動を通して知りあった千葉大学の広井良典教授の協力を得て01年6月から、大学の一室で在宅ケアを求める人たちとの電話相談を開始、さらにフォーラムの開催などで同志を募り、同じ年の12月にはNPО法人の認可も獲得する。 そうして04年には、千葉県と協力して「在宅ホスピスケアガイド」を刊行するなど、藤田さんの活動はさらに大きく広がっている。
藤田さんはこうした自らの活動は亡くなったご主人の言葉に支えられているという。
「主人が病いに倒れるまでは、新幹線にも1人では乗れない専業主婦だった。それが自分でも驚くほどたくましくなれたのは、主人の『家で過ごしたい』という思いを実現できなかったことがバネになっているのでしょう。自分にできなかったからこそ、同じ願いを持つ人を支援したいと思っているんです」
医療者の認識を高めたい

千葉県第2回在宅がん緩和ケアフォーラム
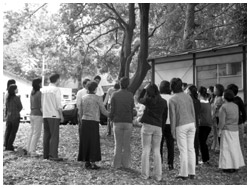
千葉県在宅緩和ケア こころのケアボランティア養成研修の風景
かつての日本ではほとんどの人たちが自宅で最期の時を迎えていた。しかし時代が変わり、現在ではがん患者の90パーセントが病院で息を引き取っている。
そのなかの少なからぬ人たちやその家族が、その人のホームグラウンドである我が家に「帰りたい」、「帰らせてあげたい」と願っているはずだ。しかし、そうした願いを実現するには、まだまだ超えなければならないハードルがあると藤田さんはいう。
電話相談を始めてから現在に至るまでの間に徐々にではあるが、患者や家族の間での在宅ホスピスに対する理解が広がっており、ケアを行う医師たちも増えている。しかし病院での医師たちの認識が不足しているのではないかと藤田さんはこう語る。
「在院日数制限などの問題から、患者が帰宅を余儀なくされることも少なくありません。そのとき家族がせっかく在宅ケアを考えていても、医師の『たいへんですよ』というひとことで家族は気持ちが揺らぎます。実際には在宅での緩和ケアを手がけている医師らに協力してもらえば、何とかやり抜けるのに、医師の言葉で在宅ケアを諦める人たちも少なくないんです」
また緩和ケアに対する医師の理解の欠如についても、藤田さんは問題を提起する。
「私の主人が痛みにあえいでいるときも検査で原因がわかるまではと、症状緩和の処置をしてもらえなかった。あまりの激痛に耐え切れず病院を訪ねて、ようやくモルヒネを処方してもらうことができました。とにかく痛みを抑えたい。そうして普通に暮らしていたい。医師のなかにはそんな患者の切ない思いを理解してもらえない人もいるんです。結局のところ、彼らは病院のベッドに横たわっている患者の姿しか見ていない。我が家でゆったりとくつろいでいる患者の姿を想像できないのではないでしょうか」
当然ながら、藤田さんの活動にはそうした医療者に対する働きかけも含まれる。
自宅で実父を支えぬく

患者さんから相談に応じる藤田さん
活動を始めてから6年、藤田さんは、その間にいくつもの忘れがたい出会いを経験している。その1つが末期の大腸がん患者だった30代の女性、MOMOさんとの出会いだ。
余命がいくばくもないと知りながら、MOMOさんは恋人の「相方」に支えられ、緩和ケアを受けながら闊達な日々を送り続けたという。
「新しい水着を買って、『相方』との旅行を計画するなど、最後まで自分の生活を楽しみ、ブログを通して同じがん患者を励まし続けていた。在宅ケアが苦しくなったら病院で治療を受ける。MОMОさんの生き方は、末期がん患者の1つの理想系ではないかとも思っています」
と、藤田さんは語る。
今年2月、そうした藤田さんの在宅ケアに対する思いが実を結ぶ機会が訪れた。末期の大腸がんだった実父が腸閉塞を起こし病院に運ばれた。
「病院の医師からはこの状態では、在宅は不可能と伝えられました。しかし在宅ホスピス医師に協力してもらい、母と2人、ケアをやり抜きました。自宅での父はとてもリラックスしており、病院では聞けないことも先生にたずねていました。最後の表情は穏やかそのもの。その姿を見て私も納得して父を看取ることができました」
そう話す藤田さんの表情は、涙をにじませていたそれまでとは一変、口もとに笑みがうかんだ。
本人はもちろん、家族にとっても患者が最後のひと時をどう生きるかということは重要そのものだ。かけがえのない人生の終幕を充実させることの大切さを伝えるために、藤田さんの奮闘は続く。
NPО法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア
在宅ホスピス電話相談
043-290-3029(火曜日・金曜日13時~17時)



