精神腫瘍医・清水 研のレジリエンス処方箋
第2回 がんを告知されたとき ――つらい気持ちとの向き合い方
がん告知後に患者さんがたどる心のプロセス

がんを告知されると、患者さんの心はどのように変わっていくのでしょうか。
告知の直後、患者さんはショックのあまり頭の中が真っ白になるとよく聞きます。
「目の前の医師の説明が自分のこととは思えず、まるでドラマを見ているような感覚だった」「その後の記憶が飛んでしまい、どうやって帰宅したか覚えていない」、こうした状態になることは、珍しいことではありません。
人は想定をはるかに超える衝撃的な出来事に出合うと、心の機能がバラバラになってしまい、現実感がなくなって無感覚に陥ります。これを医学的に「乖離(かいり)状態」といいます。ある出来事の記憶がすっぽり抜け落ちてしまったり、いつの間にか自分の知らない場所に来ていたり、がんの告知に限らず、心のショックが大きかった場合には、さまざまな症状が現れます。乖離状態は、現実を一度に全部受け止めると心が壊れてしまうので、心理的に距離をおいてダメージを遠ざけようとする、一種の防御反応と考えられています。
そして、告知の次の日もしくは数日が過ぎ、乖離状態を抜けて「自分はがんになったんだ」という事実を認識すると、今度は怒りや絶望感が襲ってきます。
例えば、50代の男性だったら、「まだ高齢者ではないし、見た目も元気だ。たばこも吸わず、暴飲暴食もせず、健康には気をつかってきた。悪いことは何もせず、誠実に生きてきた。それなのに、なぜ自分ががんになるなんておかしい。納得がいかない」という思いが頭に浮かぶでしょう。激しい怒りを抑えきれず、叫んだり、物に当たったり、家族に八つ当たりをすることもあるかもしれません。
怒りという感情は、「不公平だ」「理不尽だ」と感じる出来事があると生じます。この怒りの感情は、抑え込まずに表に出すことが大切です。職場で理不尽な出来事があったとき、誰かに話すと気持ちが落ち着いたという経験は、だれにでもあるでしょう。怒りの感情にふたをすると、心はどんどん苦しくなります。怒りの感情を出すことも自分を守るために必要なのです。
怒りの感情から悲しみの感情へ
やがて怒りの感情が影をひそめると、次は悲しみの感情がやってきます。
「もしかしたら、子どもの成長を見られないかもしれない」「仕事で忙しい日々だったので、老後は好きなことをしてのんびり暮らしたいと思っていたのに、そんな生活は夢なのか……」などの悔しさが襲ってくるでしょう。
それまで描いてきた希望に満ちた未来をあきらめなければならないことを考えると、涙があふれてくるのは自然なことです。悲しみは「自分にとって大切なものを失った」ときに生じる感情です。
怒りの感情と同じように、悲しみの感情も抑え込むのをやめましょう。
悲しいときは、しっかりと悲しむことが大切です。なぜなら、悲しみは心を癒(いや)す働きがあるからです。悲しい映画を見て思いきり泣いたら、少し気持ちがリラックスできたという経験はありませんか。最近は「涙活(るいかつ)」といって、意識的に泣くことでストレス解消をはかる活動もあります。涙を流すことにより、精神的な緊張や興奮が緩和して、落ち着きを取り戻すことができるのです。
悲しくて苦しい気持ちでいっぱいなのに、「こんなことはたいしたことじゃない」と自分に言い聞かせ、表面的には平静を装う人もいます。比較的男性に多いのですが、泣いてはいけない、弱みを見せてはいけないと思って生きてきた人は、負の感情をあらわにすることに抵抗があるようです。
でも、つらい気持ちを押し込めても、それはなくなるわけではなく、心の奥底でくすぶり続けます。泣きたいときは泣いて、心を開放させてあげることが必要なのです。できれば1人きりで泣くよりも、信頼できる人の前で泣けるほうがいい。悲しみを自分自身で認めて、傷ついている自分の気持ちをありのままに話せれば、心の落ち着きを取り戻す手助けになってくれます。
深い悲しみが長く続くときは受診を
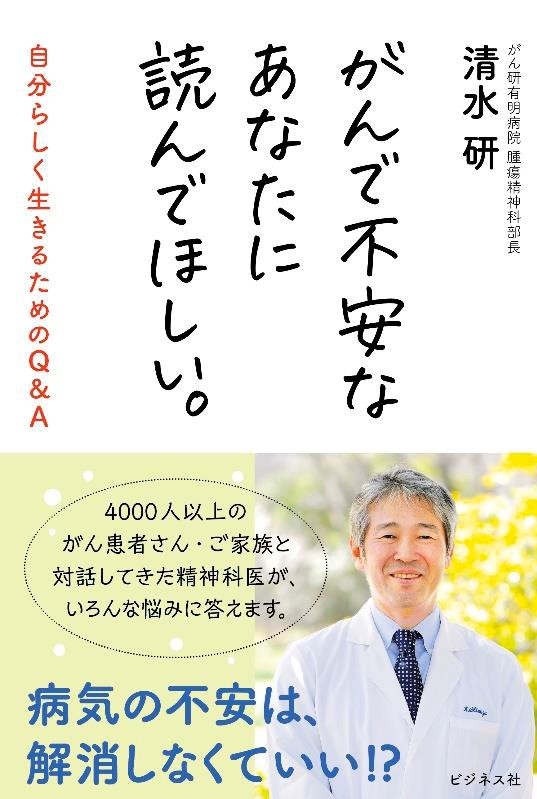
がんの告知を受けた患者さんは、時間の経過とともに、少しずつ普段の自分を取り戻していきます。
怒り、悲しむという感情を経て、「この事実は変えられないんだ」というあきらめに近い感覚が生まれてきます。それと同時に「健康な体には戻れないけれど、すべてを失ったわけではない」と、その後の生き方を新たに考え始めるようになります。怒りや悲しみが、徐々に新しい人生を考える方向にシフトしていくわけです。突然切り替わるのではなく、ゆっくりとグラデーションのように移っていく感じです。
つらい気持ちがどのくらい続くかは、患者さんの性格や何を失ったと感じているかによって異なり、人それぞれです。悲しみの感情が長引いても、自分を弱いと思う必要はありません。おそらく感情が豊かで深く、こまやかな方なのでしょう。他人の気持ちを思いやれる、心遣いができる方でもあります。自分を責めたりしないでください。
また、気持ちの回復は必ずしも順番どおりではなく、1日の間でも変化します。このような反応は、人が生きていくために必要なプロセスなのです。
ただ、1つ注意していただきたいことがあります。がんという病気は否が応でも人に「死」を意識させ、さまざまなストレスをもたらします。がん告知後の1年以内の自殺率は、一般人口の24倍というデータがあります。また、がん告知後にうつ状態になる人の割合は5人に1人といわれています。ですから、次のような兆候が見られたら、精神的なピンチに陥っている可能性があります。
・1日のうち、半分以上の時間を気持ちがふさぎ込んだ状態で過ごしている
・今まで楽しみにしていたこと(例えば、スポーツ観戦、映画鑑賞、友人とのおしゃべり、ドラマの視聴など)に興味を持たなくなった
この2つのどちらか(あるいは両方)の状態が2週間以上続いた場合は、うつ病の可能性があるので、精神腫瘍医や心療内科医などの専門医に相談したほうがよいでしょう。夜眠れない、食欲がないなどの症状があるときも、しばらく続くようなら受診してください。
悲しみの感情は、必要以上にエネルギーを消耗させます。心が疲れ切ってしまう前に専門医の扉をたたいてください。
同じカテゴリーの最新記事
- 実例紹介シリーズ第12回 友だちが黙って入院して娘がショックを受けている
- 実例紹介シリーズ第11回 治療中の3歳児に、絵やメッセージを渡したいのだが
- 実例紹介シリーズ第10回 34歳、独身で乳がん。生きがいが見つかりません
- 実例紹介シリーズ第9回 ホルモン療法中止して子どもが欲しいのに、夫が反対しています
- 実例紹介シリーズ第8回 進行がんで療養中。どう子どもと向き合っていけばいいのでしょうか
- 実例紹介シリーズ第7回 手術後遺症の勃起障害を妻に伝えることができません……
- 実例紹介シリーズ第6回 認知症患者の治療の意思決定はどのように?
- 実例紹介シリーズ第5回 医療過誤を疑い、いつまでも苦しい
- 実例紹介シリーズ第4回 再発した妻が治療を拒否
- 実例紹介シリーズ第3回 セカンドオピニオンを主治医に言い出しにくい



