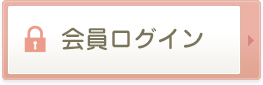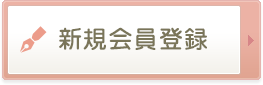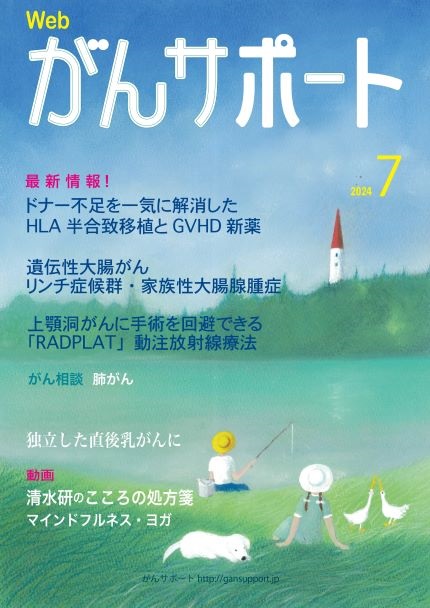精神腫瘍医・清水 研のレジリエンス処方箋
実例紹介シリーズ第6回 認知症患者の治療の意思決定はどのように?
Q 認知症患者の治療の意思決定はどのように?
87歳の父が、肝がんの診断を受けました。父は施設に入所していますが、認知症と診断されています。病気について伝えましたら、そのときは自分ががんになったことに対して大変なことになったと理解しましたが、翌日になるとすっかり忘れている状態です。食欲と認知度は落ちているように思います。
施設長は内科医のようですが、病院で手術などせず、施設での看取りを勧めています。どうするかについてきょうだい3人と母で相談しています。しかし、病院で手術を含めたがん治療をしっかりするべきという妹と弟の意見と、年齢と認知症の進行具合を考えると、手術は行わないで緩和ケアに専念したほうがいいという私の意見に割れました。母は迷っています。その後、何度か話し合っても平行線のままで、結論が出ません。診断した医師は、そちらで決めてくださいという態度です。どのように解決すればいいか困っています。
(60代 女性)
A 何よりもまず、本人の意向を大切に
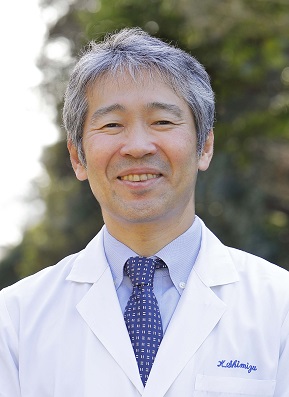
このご相談を読んだとき、まずご家族みなさまの、お父様のことを想う気持ちの強さを感じました。お父様に幸せであってほしいという願いが強いからこそ、それぞれの方の意見が強く、平行線なのだろうと思います。
このような場合、認知症患者さんの意思決定の原則をご家族で共有していただき、それに沿って考えていただけるとよいのかもしれません。
その原則とは、「患者さんの意思をできる限りくみ取るようにし、最期までその人らしい生き方ができるように支援していく」というものです。
ご相談者さんは、家族でお父さんの今後の治療についての意見が割れて困っているとのことですが、「私は少しでも長く生きて欲しいから、手術をしたほうがいい」、「私は苦しませたくないから、緩和ケアに専念したほうがいい」などと、家族の思いを先に立たせるのではなく、「お父さんはどうしたいのか」という視点で考えることが大切だと思います。
おかれた状況をきちんと理解して、自分はこうしたいという決定ができる能力を、「意思決定能力」と言いますが、多くの場合、認知症だからといって意思決定能力がないわけではありません。一部欠如していることは多いとは思いますが、部分的に意思決定能力があるのです。ですから一見、本人には判断できそうもないことでも、家族や医療者がサポートしながら、本人の意思決定能力が最大限発揮できるようにすることが原則です。
込み入った話は理解できなくても、シンプルな質問なら回答できるかもしれません。
例えば、「肝臓にがんができているから、大変だけど治すために手術をする? それとも手術はしないで、薬でつらい症状だけをとるようにする?」と聞いて、「つらい思いはしなくないな」と答えたら、それが本人の意思表示なわけです。もちろん、状況を詳細に理解できているわけではないので、細部については判断できないかもしれませんが、「つらい思いをしてまで長生きを目指したいわけではなく、なるべく苦しまずに過ごしたい」という希望を持っていることは推測できます。
また、お父さんの価値観や、認知症になる前に行っていた会話などから、「お父さんならきっとこの治療法にするだろう」と、家族が推察することもできるかもしれません。
繰り返しになりますが、ご家族の価値観は置いておいて、ご本人の立場に立って、何を望んでいるかを考えるという認知症患者の意思決定の原則から離れないように、家族みんなで考えていっていただくことが大切なのです。
やりきれない気持ちに寄り添って話し合いを
次に、それでもごきょうだいで意見が割れてしまう場合、どうしたらよいのでしょうか。
意見が異なる各論について議論する前に、きょうだいで共有できること、つまり「みな父のことを想って、父にとって最善の判断をしたい」という目的は一緒だなということを、折に触れて共有したらよいでしょう。このことに限りませんが、意見が割れて、ともすれば対立構図になりがちな場合、目指すゴールは一緒であることを確認することが大切です。
また、ご家族が積極的治療以外は考えられないという場合は、「その人を失うことを受け入れられない」という気持ちが背景にあることが多いです。また、「父に自分が何かしなければ」という無力感の裏返しから、「できることは何でもやってほしい」という意向が表明されることもあります。
もしかしたら相談者さんのごきょうだいは、お父さんががんになったという事実と向き合えず、焦りや不安から緩和ケアに専念することに強く反対しているのかもしれません。そうであれば、まずごきょうだいのやりきれない気持ちを汲むことが大切ではないでしょうか。
例えば、「お父さんが、がんになるなんて思わなかったね。私だって同じよ。お父さんには長生きして欲しい」という具合に気持ちを一度汲んでみると、ごきょうだいも自分のやりきれなさを話すかもしれません。そうすれば、わかり合えることもあるかもしれません。
ご家族の足並みがそろったら、施設長が緩和ケアを勧める理由をもう1度聞いたり、生存期間だけでなく、術後に起こり得る障害についても確認したり、手術のメリットとデメリットをきちんと確認できるとよいと思います。治療法の選択で困ったときは、セカンドオピニオンを受けるのも得策です。
家族間でいざというときのことを共有しておく
近年、「終活」という言葉が注目されるようになり、自分が亡くなるときの準備をしておこうという機運が高まっているようです。元気なときに意思表示をしておけば、自分が望まない医療を受けるリスクは下がりますし、家族を悩ませることも少なくなるでしょう。
厚生労働省はアドバンス・ケア・プランニング(ACP・愛称「人生会議」)を提唱しています。これは、患者さんが主治医や医療チームと自分の価値観についてじっくり話し合い、自分が判断できなくなったときには、ACPをもとに判断して欲しいという希望を共有するというものです。家族間でも、いざというときのことを日ごろから話し合っておくことが必要だと思います。
ただ、「いざというときに、こういう選択をしたい」という意向は、状況によって移り変わっていくことも多いです。ですから、一度の意思表示を最終決定とするのではなく、折に触れて話せるといいです。まさに決めなければいけないときが来た際も、「昔はこういう風に言っていたけど、その気持ちは変わらない?」という具合に、今あらためてどう思っているのか、話し合いたいところです。
とはいえ、ACPはご本人にとってもご家族にとっても、骨が折れる問題について考えなければいけないという側面も持ちます。自分たちはとても大変なことと向き合っているんだということを認め、お互いをねぎらう気持ちを持てるとよいですね。
同じカテゴリーの最新記事
- 実例紹介シリーズ第11回 治療中の3歳児に、絵やメッセージを渡したいのだが
- 実例紹介シリーズ第12回 友だちが黙って入院して娘がショックを受けている
- 実例紹介シリーズ第10回 34歳、独身で乳がん。生きがいが見つかりません
- 実例紹介シリーズ第9回 ホルモン療法中止して子どもが欲しいのに、夫が反対しています
- 実例紹介シリーズ第8回 進行がんで療養中。どう子どもと向き合っていけばいいのでしょうか
- 実例紹介シリーズ第7回 手術後遺症の勃起障害を妻に伝えることができません……
- 実例紹介シリーズ第5回 医療過誤を疑い、いつまでも苦しい
- 実例紹介シリーズ第4回 再発した妻が治療を拒否
- 実例紹介シリーズ第3回 セカンドオピニオンを主治医に言い出しにくい