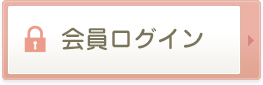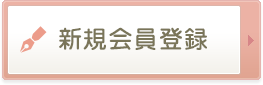大型新薬の登場から1年。再発・難治の骨髄腫でも大幅改善した例が続出
大きく前進する多発性骨髄腫の薬物療法
 多発性骨髄腫の豊富な
多発性骨髄腫の豊富な治療経験を持っている
西脇嘉一さん
昨年、治療効果が大きく、副作用も少ないといわれる大型新薬、レブラミドが承認されたことで、多発性骨髄腫の薬物療法は大きく前進した。
レブラミドの発売から1年経ち、医療の第一線からは目ざましい成果が報告されつつある。
進行してから診断される例が多い
多発性骨髄腫は、血液のがんとしては白血病に次いで2番目に多い病気だ。50代以上になると発症率が跳ね上がることでも知られ、日本の推定患者数は現在約1万人といわれている。
「高齢化などを背景に患者数は年々増えているようです。当院でも、多発性骨髄腫の患者さんが多く受診されるようになりましたね」
こう説明するのは、東京慈恵会医科大学講師で同付属柏病院腫瘍・血液内科診療部長の西脇嘉一さん。多発性骨髄腫の豊富な治療経験を持っている。
骨の中の骨髄では、造血幹細胞という血液のもとになる細胞が形を変えながら分裂を繰り返し(これを分化という)、さまざまな白血球や赤血球、血小板になる。ところが、白血球の中の形質細胞(リンパ球の1種)ががん化してしまうのが多発性骨髄腫だ。
がん化した形質細胞は骨髄腫細胞と呼ばれる。骨髄腫細胞は骨髄中で無秩序に増えていき、正常な血球ができるのを妨げたり、骨を破壊したりする。その結果、赤血球が減って貧血を起こしたり、白血球が減って感染症にかかりやすくなったりする。あるいはちょっとした弾みで簡単に骨折するようになる。進行すると、全身の骨髄で骨髄腫細胞が増殖して、体じゅうの骨が痛み、血液中にも骨髄腫細胞が溢れるようになる。
また、正常な形質細胞は、病原菌などの有害な異物を攻撃するための「抗体」というたんぱく質を作るが、骨髄腫細胞は役に立たない抗体(Mたんぱく)を大量に作ってしまう。
「Mたんぱくが増えると、血流を悪化させたり、腎臓などに沈着して障害を与えたりします。そのため、腎不全などを招くのです」
多発性骨髄腫は、自覚症状が出てもほかの病気と見分けがつきにくく、進行してから診断される例が後を絶たない。
「目立つのは最初、腰痛や貧血を訴え、くわしく調べたところ、多発性骨髄腫とわかるケースです。もっとも、ほかの病気で血液検査や尿検査などを受け、それがきっかけで早く見つかる患者さんも少なくありません」
症状がなければ治療しなくてよい
現在、多発性骨髄腫は進行度に応じて、主にMGUS、無症候性骨髄腫、症候性骨髄腫に分類される。症状のないMGUSと症状がほとんど現れない無症候性骨髄腫は、多発性骨髄腫とわかっても治療の対象でなく、経過観察となる。
「とくに若い患者さんは、がんなのに治療しないというと驚かれます。しかし、この病気はやみくもに治療をすればいいというわけではありません。たとえば、薬物療法は治療効果という利益と同時に、副作用などの不利益も大きいのです。医師はそのバランスを考えて、治療開始の時期を判断します」
病気が進行して症状が出てくると、治療が開始される。大きく分けると、65歳以下で重い合併症や臓器障害がない場合は大量化学療法+自家末梢血幹細胞移植、それ以外の場合は標準化学療法が勧められる。
大量化学療法+自家末梢血幹細胞移植は、まず大量の抗がん剤を投与して全身の骨髄腫細胞をできる限り死滅させる。そのあとで、あらかじめ採取しておいた患者さん自身の正常な造血幹細胞を、患者さんの体内に戻すのである。
「この治療法は効果が大きく、多発性骨髄腫を長期にわたり病状安定させることができる治療法といっていいでしょう。しかし、多発性骨髄腫は高齢の患者さんが多いため、適応が一部に限られてしまう問題があります」
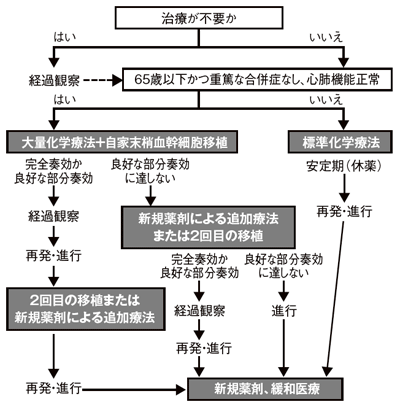
新薬が続々登場し治療環境が一変
大半の患者さんは標準化学療法を受けることになる。
従来の標準化学療法は効き目が弱く、多発性骨髄腫が難治といわれる大きな原因だった。
「私が多発性骨髄腫の治療に携わるようになった25年ほど前、主な化学療法といえば、MP療法(メルファラン+プレドニゾロン)くらいしかありませんでした。その後、VAD療法(ビンクリスチン+ドキソルビシン+デキサメタゾン)なども登場したのですが、治療成績は低迷していました。ところが、2006年にベルケイド(*)、08年にサレドが相次いで承認され、多発性骨髄腫の治療環境は一変したのです」
ベルケイドは細胞内のたんぱく質を分解する装置に働きかけ、その機能を阻害することで多発性骨髄腫に対して優れた効果を示す。サレドは一般名をサリドマイドという。かつて胎児への催奇形性(奇形を引き起こす性質)があるとして使用できなくなったが、がんに栄養を送る血管ができないようにするといった働きが再評価され、多発性骨髄腫の治療にも活用されている。
さらに、2010年7月には、多発性骨髄腫の治療薬として「レブラミド(*)」も承認された。
「レブラミドは免疫調節薬と呼ばれ、骨髄腫細胞を自滅させたり、サイトカイン(生理活性物質)の産生を調整して免疫細胞を活性化したりする多彩な薬理作用を持ち、安定的に多発性骨髄腫の進行を抑えると考えられています。サリドマイドと構造が似ていますが、別の物質です」
*ベルケイド=一般名ボルテゾミブ
*レブラミド=一般名レナリドミド
無増悪生存期間が3倍近く延びた
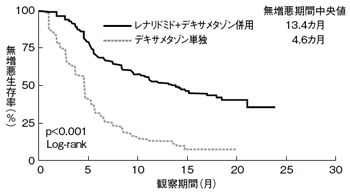
[レナリドミドの効果(奏効率)]
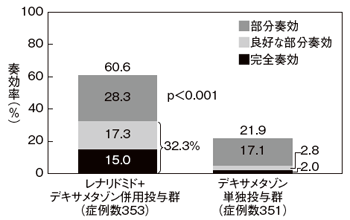
再発・難治性の多発性骨髄腫患者さん約700人を対象とした、レブラミドの海外第3相臨床試験の結果が出ている。
半数ずつをデキサメタゾン(ステロイド剤の1つ。日本での商品名はレナデックス)単独投与群、レブラミド+デキサメタゾン併用投与群に分けたところ、無増悪生存期間中央値(病気が進行せずに生存した期間の中央値)では、デキサメタゾン単独投与群の4.6カ月に対し、レブラミド+デキサメタゾン併用投与群は13.4カ月と3倍近く延びた。奏効率ではデキサメタゾン単独投与群の21.9パーセントに対し、レブラミド+デキサメタゾン併用投与群は60.6パーセントだった。
ベルケイドもサレドもレブラミドも、今は再発、あるいは難治性(初回治療が無効)の多発性骨髄腫の治療にしか承認されていない。しかし、3つの新薬が出揃ったことで、多発性骨髄腫の治療法は大きく前進したと西脇さんは語る。
「多発性骨髄腫は今のところ、残念ながら治癒は難しい病気です。しかし、QOL(生活の質)を大事にして、日常生活を元気に送れるよう治療をしていくことが重要です。自家移植できない場合は薬物療法を駆使して、最初の手が使えなくなったら、また次の手といった具合に病気の進行を抑え、生存期間を延ばすことがカギになります。その意味では、今までに比べて格段に効果の大きい武器が3つも手に入ったわけですから、治療成績はどんどん伸びることが期待できます」
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 「過剰検査・過剰治療の抑制」と「薬物療法の進歩」 甲状腺がん治療で知っておきたい2つのこと