豊富な知識と知恵で、痛みに耐える患者さんの心を開く凄腕緩和ケア医
体と心の痛みを緩和して、患者さんの命に寄り添う
余宮きのみ 埼玉県立がんセンター緩和ケア科科長
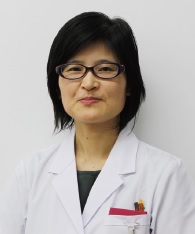
緩和医療は、教科書通りでは通用しないところが難しい。その中で、埼玉県立がんセンター緩和ケア科科長の余宮きのみさんは、症状の緩和だけではなく、患者さんにいかに満足して残された日々を過ごしてもらうか、患者さんの充足感を求めて医療技術を磨き、患者さんの心に寄り添う感性を磨いてきた。
よみや きのみ 1991年日本医科大学卒業。緩和ケア医を目指し、内科、神経内科、リハビリテーション科で研鑽を積む。2000年より埼玉県立がんセンター緩和ケア科。2009年より埼玉県立がんセンター緩和ケア科科長、現在に至る。専門は緩和ケア、がん諸症状緩和とくに神経障害性疼痛緩和、がん終末期のリハビリテーションと多岐にわたって患者さんの診療にあたっている
患者さんの心が和らぐ診察
埼玉県立がんセンター緩和ケア科は、緩和ケア病棟の入院患者さんをケアする病棟チームと一般病棟の患者さんや外来患者さんを担当する緩和ケアチームから構成されている。ドクターは合わせて6人。それを束ねているのが、余宮きのみさんだ。
朝、緩和ケア病棟のカンファレンスの後、余宮さんが向かったのは一般病棟。緩和ケアの依頼を受けた患者さんと初めての面談を行い、乳がんが転移した患者さんの様子をみる。

コルセットをした患者さんに「洗面の時、体を曲げると背中が痛くないですか」と余宮さんが尋ねると、やはり痛むという。そこで余宮さんは、薬を増やして痛みを軽減することも可能だが、痛みを指標として体勢に気をつけることもできると語る。こういう時、余宮さんは型通りの治療法を患者さんに押しつけない。結局、痛みはつらいからという患者さんの選択で、夜に投与していた痛み止めの薬剤を、昼間起きて行動する時間帯に投与することにした。
10時からは外来診療。夫に付き添われて車イスで受診したのは、子宮頸がん患者さんのAさんだ。年初に激しい痛みと食欲の低下で緊急受診。がんは肝臓にも広がり、黄疸が出ていた。それでも、「入院は気を使うから嫌」とかたくなに拒んできた。
その意志を余宮さんは尊重している。だが、今日は事態が急変していた。症状の悪化に加え、朝、玄関で足の激痛に襲われたという。骨折していた。
「転移で足の骨が弱くなっていたのかもしれないですね」。余宮さんは、事前に骨転移をキャッチできなかったことに胸を痛めていた。医療にも不可抗力はある。それでも、こんな風に言ってくれる医師はそういないのが今の治療現場である。
次の患者さんは、妹に付き添われて車イスで受診したBさん。一見、元気そうだが、乳がんが肺に転移し、呼吸困難と痛みがある。だが、薬に対する忌避感が強い。やっと決断して年末から抗がん薬治療を開始したが、呼吸困難は悪化するばかりだ。
「つらさを0~10までで表すと、今はどのくらい?」。余宮さんは、よく苦痛の程度を数値で評価するツール(*NRS)を開いて患者さんに評価してもらう。治療効果や患者さんの要望を把握しやすいからだ。
Bさんの場合、その数値は車イスに乗っていれば2、話すと4、大きな動きをすると7~8にまで苦痛は増大。「朝着替えをすると、パニックになるほど苦しくて」
普通ならば、即座に薬の増量を勧めるところだが、彼女の性格を知っている余宮さんは、「薬を増やすか、朝まで効くように夜だけ長時間作用型に変えてもいいですね」と、2案を提示する。それでも不安で、Bさんは決めかねている。
すると、余宮さんは「待って、じゃあBさんの気持ちになって、もう一度考えてみるわね」と思考を巡らす。そして、今の薬を減らして、夜だけ長時間作用型の薬を少量上乗せする、という折衷案を提示した。
*NRS=痛みを0から10の11段階に分け、痛みが全くないのを0、考えられる中で最悪の痛みを10として、痛みの点数を問う評価法。Numerical Rating Scaleの略
患者さんの思いを受け止める間口を開けておく

結局、Bさんは長時間作用型に変えると決断したが、この30~40分の間余宮さんがBさんの判断をせかしたり、答えを強要することは全くない。それどころか、常に「他に心配なことはない?」と間口を開けておく。その中で、Bさんは実は粉薬が苦手なことがわかり、薬はシロップに変更された。
時間にゆとりがあるわけではないが、患者さんの迷いを封じるようなことは絶対にしない。
初診で妻子とともに訪れた肺がん患者のCさんには、今の気持ち、これからどうしたいか、家族の不安は何かを尋ねて1つずつ問題を整理していく。食欲がないのを心配する家族には、肝臓が腫れて胃の容量も少なくなっていること、がんが脳に作用して食欲を低下させていることを説明。食欲を改善する薬があることを話した上で、こう諭した。
「食べられないことに焦りや不安を感じての食事が、患者さんにはストレスになるのです。今は栄養のバランスや量にこだわらず、楽しく食事をするのが一番大切です」
元気になって欲しい一心で、つい家族は患者さんに食事を強要してしまうことがある。それが患者さんのストレスになることに、家族は深く納得した様子だった。患者さん本人は静かにうなずいていた。
こうした時間のやりとりの中で、余宮さんは患者さんや家族の信頼を得ていく。それが、緩和ケア医の手腕でもあるのだ。



