放射線科の持つ緩和ケア的要素を理解してもらいたい
他科とスクラムを組み、最良の治療を届けるための努力を惜しまない
萬 篤憲
独立行政法人国立病院機構東京医療センター放射線科医長

前立腺がんに対する小線源療法の総本山とも称される国立病院機構東京医療センター。その黎明期から治療に携わってきたのが、放射線科医長の萬篤憲さんだ。放射線治療に関しては、マスコミの影響もあり、どうしても最先端の治療法や医療機器に目が行きがちだが、緩和ケアにも力を入れている萬さんは、放射線科や放射線科医がもつ本質的な要素にもっと目を向けて欲しいと訴える。
よろず あつのり 1960年東京生まれ。1985年慶應義塾大学医学部卒。都立広尾病院、国立病院機構東京第二病院(現国立病院機構東京医療センター)を経て、1999年英国クリスティー病院臨床腫瘍科留学。2001年東京医療センター放射線科医長に着任。現在に至る。日本医学放射線学会放射線治療専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医。専門分野は放射線治療、臨床腫瘍学、小線源治療、緩和医療
小線源療法のパイオニア的施設
国立病院機構東京医療センター放射線科。全国屈指の放射線治療数を誇り、中でも前立腺がんに対する小線源療法のパイオニア的施設だ。
小線源療法とは、体の外から照射する通常の放射線治療と異なり、放射線源を直接患部へ埋め込む内照射と言われる方法だ。病巣の形状をコンピュータで確認しながら治療計画を立てて、病巣へ向けて長い針を刺し、ヨウ素125という放射線源を密封したシード(カプセル)を埋め込んでいく。
もともと子宮頸がんや口腔がんに対する根治治療として発達してきたが、同センターはこの治療を前立腺がんに対して全国に先駆け2003年に開始した。
そんな放射線科で、約四半世紀にわたって診療にあたり、放射線治療の進化をその最前線でつぶさに見てきたのが、同科医長の萬篤憲さんだ。
放射線治療の進歩に隔世の感
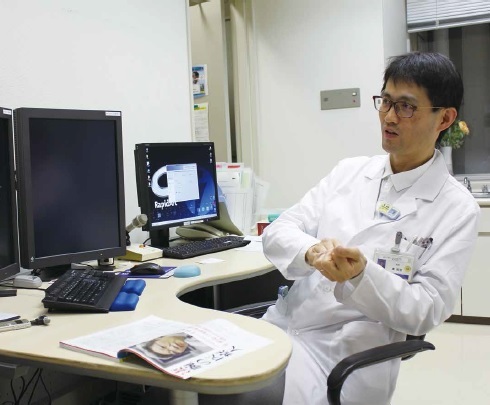
萬さんが同科に着任した1991年当時、放射線治療は、手術後に再発した患者さんや、切除不能の進行がんの患者さんに対する、疼痛などの症状を抑えるための緩和的な治療としての役割も担っていた。
「私が当科に来た90年代と2000年代以降では、同じ放射線治療でもだいぶ進歩しました。今考えると、隔世の感があります。この間、放射線治療の主力は、症状を抑える治療から、治すための治療へと変わっていきました」
放射線治療といえば、今や、手術、化学療法とともに
がんの3大治療と言われるようになったが、萬さんが同科に着任してからの約10年間は、各科から送られてくるつらい状況の患者さんの診療と治療に従事するほうが主だった。
「その当時は、まさに放射線科は緩和ケアの役割を担っていました。各科での治療が厳しくなった患者さんが日々訪れていました。そんなつらい思いを抱えてやってくる患者さんの話をじっくり聞くことも私たちの仕事でした。当時、年間の患者数も約200人と、今の3分の1以下でしたので、1時間でも2時間でも患者さんの話を聞くことが普通でした。夜中、病室へ行って話を聞くようなことも珍しくありませんでした」
〝治す〟よりも〝癒す〟治療を目指す
萬さん自身、もともと緩和医療に興味があったが、最初から放射線治療医を目指したわけではなかったという。
「学生の頃は、本や映画やテレビの影響で、無医村とか田舎で働くお医者さんに憧れていたんです。それで最初は外科を目指しました。それは大きな手術がしたいとかそういうことではなくて、外科を学んでメスが使えれば、そういうところでも何とか医師としてやっていけるだろうという単純な考えでした」
そんな折、医学部の卒業を間近に控えた頃、祖母が食道がんで術後すぐに亡くなってしまう。さらにその後、研修医の時に、父親の口腔がんが再発してしまった。肉親2人の闘病生活の悲惨な状況を続けて目の当たりにした。
「父親は、手術をしても治らず、中性子を照射する特殊な治療なども行いましたが、最後は自宅で、モルヒネで痛みを取りながら亡くなりました。だから医師のくせに医療は大嫌いだったんです。治る望みがないのに、治療で苛めるようなやり方は好ましくないと感じていました。そして、〝治す〟よりも〝癒す〟治療を目指すことを考えたのです」
この家族の看取りを通じて、緩和ケア医療への思いはさらに強くなった。
ところが、外科の研修医として1年経った頃、自身が肝炎により倒れてしまう。肝がんの患者さんに注射をするときに、肝炎ウイルスに感染してしまったようだった。
「そのときは、いずれ肝硬変になって、40代ぐらいで肝がんで死ぬのかなと思っていました」
療養で2年ほど棒に振った後、再び医師の仕事に戻れることになるが、外科への復帰は無理だと悟る。
「いろいろ考えた末の結論でした。外科にいた頃から、夜中に病棟を回って注射をしに行くときに、告知もされずにつらい思いをしている患者さんたちの話をよく聞いたりしていたこともあって、その頃は緩和ケアに舵をきろうと思いました。無理な心肺蘇生も平気でやられていた時代でしたが、こんなことはなるべくやってあげたくないと思っていましたので、新しい道を模索するつもりでいました」



