副作用は少なく、腫瘍縮小効果は大きい
局所を集中的に攻める新しい化学療法「抗がん剤灌流療法」
 数々の抗がん剤灌流療法を
数々の抗がん剤灌流療法を開発した
村田智さん
さまざまな工夫が重ねられてきた動注化学療法だが、また新たな治療法が生まれた。骨盤内に出入りする血流を遮断するという画期的な方法により、骨盤内臓器(直腸、子宮、卵巣、膀胱など)にできたがんの完治を目指している。
血中濃度が高いほど抗がん剤はよく効く
がんの化学療法では、体内に投与された抗がん剤が血流に乗って運ばれていき、がんが抗がん剤にさらされることで効果を発揮する。そして、がんに対する抗腫瘍効果は、抗がん剤の血中濃度に比例する。血中濃度が高ければ高いほど、治療効果も高まるわけだ。これが抗がん剤による治療の基本である。
しかし、いくらでも血中濃度を上げられるかというと、そうはいかない。日本医科大学放射線医学准教授の村田智さんは、次のように説明する。
「抗がん剤を点滴などで投与する全身化学療法では、抗がん剤が全身に回るので、血中濃度が高いほど副作用が強く出ます。そのため、上げられる濃度に限界があり、治療効果もそれに見合った程度になります」
そこで、「動注化学療法」という方法が考え出された。がんにつながる動脈に、直接抗がん剤を注入する方法である。全身化学療法に比べると、部分的に抗がん剤の血中濃度を高くすることができる。肝臓がんなどでよく行われている治療だ。
「この治療が効果的なのは、注入した抗がん剤が高濃度でがんに到達するからです。ただ、抗がん剤は結局全身に流れていくので、投与できる抗がん剤の量は増やせません。全身化学療法より合理的な治療ですが、効果はやはり限定的なのです」
そこで考案されたのが、動注化学療法の発展形ともいえる治療法だった。
骨盤内で血液を循環させ高濃度状態を作り出す
この新しい治療法が「抗がん剤灌流療法」である。
「50年ほど前、脚にできた肉腫の治療として、脚の動脈に抗がん剤を注入し、静脈から吸引して、主に脚に高濃度の抗がん剤を循環させる治療が考え出されました。その後、骨盤内で循環させる方法が開発され、骨盤内臓器のがんの治療として、欧米では実用化していました」
こうして始まった骨盤内灌流療法だが、たいした効果はなかったという。理由は、注入した抗がん剤が骨盤内からどんどん漏れ出てしまうためだった。「骨盤内にはバイパスの役割を果たす側副血行路が発達しているので、そこを通って出てしまうのです。10分後には抗がん剤の50パーセントが骨盤外に漏れ出し、30分もすると、大部分が全身に回っていました。これでは、抗がん剤の投与量を増やすこともできません」
この欠点を克服した方法が日本医大で開発された。それが日本医科大学式閉鎖循環下骨盤内灌流療法(*)(以下、日医式骨盤内抗がん剤灌流療法)である。
*日本医科大学式閉鎖循環下骨盤内灌流療法=NIPP(Negative-balanced Isolated Pelvic Perfusion)
抗がん剤の血中濃度は全身化学療法の25~30倍
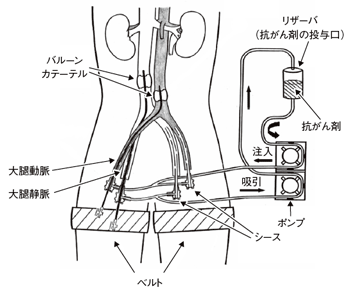
日医式骨盤内抗がん剤灌流療法の治療方法を簡単に説明しておこう。
まず、左右の脚の付け根にある動脈と静脈に、シースという管を計4本入れる。このうち片側の2本からバルーンカテーテル(先端に風船のように膨らむ部分がある細い管)を入れ、腹部の大動脈と大静脈まで送り込む。次に、大腿部をベルトで強く締めて脚への血流を遮断し、大動脈と大静脈のバルーンを膨らませて血流を遮断する。
このように、骨盤内に入ってくる血流と出ていく血流を止めてから、抗がん剤を注入する。ポンプを使って左右の大腿動脈に注入し、もう1つのポンプで大腿静脈から抗がん剤を吸引して、血液を循環させるのだ。
日医式骨盤内抗がん剤灌流療法では、抗がん剤が骨盤外に漏れ出しにくい。治療では30分間循環させるのだが、その間に漏れ出す抗がん剤は、わずか15パーセントである。
「動脈に注入する量より、静脈から吸引する量をわずかに多くしています。たとえば、1分間に300ミリリットル入れ、320ミリリットル吸引するといった具合です。こうすることで、血液は側副血行路に入っていけず、骨盤内で循環します」
骨盤内から漏れ出さなければ、高い血中濃度が維持されることになる。また、日医式骨盤内抗がん剤灌流療法では、治療後に骨盤内の血液の人工透析を行い、抗がん剤を除去する。そのため、全身的な副作用を心配せず、大量の抗がん剤を投与できる。
「全身化学療法で投与できる最大量の2倍程度まで投与できます。その量を主に骨盤内だけで循環させるので、血中濃度は通常の全身化学療法の25~30倍にもなります」
この高い血中濃度が、優れた治療効果を生み出すことになる。
高い血中濃度によりどんながんも縮小する
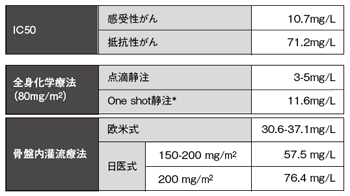
- IC50は、腫瘍を50パーセントに縮小させるのに、どれくらいの濃度の抗がん剤が必要かを示す。抗がん剤がよく効く感受性がんでは、10.7mg/Lの濃度で腫瘍の50パーセントが縮小する。しかし、すでに化学療法を受け、抗がん剤が効かなくなった抵抗性がんでは、71.2mg/Lまで濃度を上げなければならない
- 点滴による全身化学療法では、血中濃度は3~5mg/Lにしかならず、がんを縮小させる濃度には程遠い
- 日医式骨盤内抗がん剤灌流療法で投与量を200mg(体表面積1㎡当たり)まで増やすと、血中濃度は76.4mg/Lになる。これは抵抗性がんのIC50も超えている
[表4 直腸がん術後に再発した手術不能な患者さんの生存率]
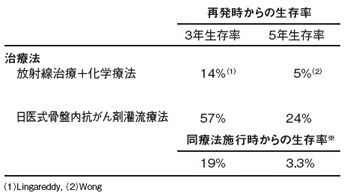
表2は、消化管がんに対するシスプラチン(*)(一般名)の血中濃度と効果や副作用との関係を示したものだ。
IC50は、50パーセントの腫瘍をやっつけるのに、どれくらいの濃度の抗がん剤が必要かを示している。抗がん剤がよく効く感受性がんでは、10.7(ミリグラム/リットル=以下同)の濃度で、腫瘍の50パーセントが縮小するという意味だ。しかし、すでに化学療法を受け、抗がん剤が効かなくなった抵抗性(*)がんでは、腫瘍を半分にするためには、71.2まで濃度を上げなければならない。
点滴による全身化学療法では、血中濃度は3~5にしかならない。がんを縮小させる濃度には程遠いわけだ。いくら治療をしてもまったく効かず、体を壊すだけである。欧米式の骨盤内灌流療法だと、感受性がんの治療には十分な濃度になるが、抵抗性がんの治療には不十分である。
これに対し、日医式骨盤内抗がん剤灌流療法で投与量を200ミリグラム(体表面積1平方メートル当たり=以下同)まで増やすと、血中濃度は76.4になる。これは抵抗性がんのIC50も超えている。このデータから、抵抗性のがんに対しても、日医式骨盤内抗がん剤灌流療法は十分に効果的であることがわかる。
「日医式骨盤内抗がん剤灌流療法では、手術できないと診断されたがんでも、それが骨盤内にとどまっていれば、完治させることが可能です。治しやすいのは、子宮頸がんの95パーセントを占めている扁平上皮がんや、膀胱がん。治療が難しいのは、徹底的に全身化学療法を行って抵抗性になった直ちょくちょう腸がんです。しかし、直腸がんでも、がんが消え、5年以上もその状態が続いている人もいます」
日医式骨盤内抗がん剤灌流療法で使われる抗がん剤はシスプラチンが中心だが、がんの種類によって、ほかの抗がん剤も使われるという。直腸がんにはシスプラチンと5-FU(*)の併用。膀胱がんにはシスプラチン単剤だが、前日にジェムザール(*)を投与する。婦人科がんの腺がんには、シスプラチンとタキソテール(*)の併用。婦人科がんの扁平上皮がんには、シスプラチン単剤が使われる。また、前治療が行われている場合、これまでに使われていない抗がん剤が使用されることもある。
(50歳代・女性・ステージ4a)
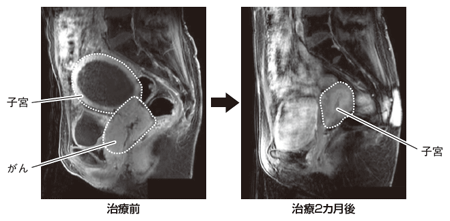
(50歳代・男性)
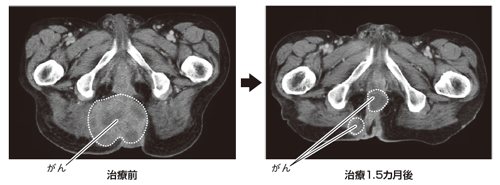
*シスプラチン=商品名ブリプラチン、ランダ
*One shot静注=1回のみの薬液投与による静脈内注射
*抵抗性=治療の効果がなくなること
*5-FU=一般名フルオロウラシル
*ジェムザール=一般名ゲムシタビン
*タキソテール=一般名ドセタキセル
同じカテゴリーの最新記事
- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!
- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん
- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん
- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬
- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識
- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する
- 「過剰検査・過剰治療の抑制」と「薬物療法の進歩」 甲状腺がん治療で知っておきたい2つのこと



