
免疫力を高めるガゴメ昆布「フコイダン」
2015年9月
タカラバイオ研究チームリーダーの大野木 宏さんフコイダンは昆布、ワカメ、モズクなどの海藻のネバリのもとになっている高分子の多糖類で、食物繊維の一種である。1995年にタカラバイオが世界で初めてその化学構造と機能性の解明に成功した。同社は、ガゴメ昆布に含まれるフコイダンにがん細胞の増殖を抑制する作用やウイルス感染を抑制する作用、免疫力を高める作用などがあることを明らかにし、ガゴメ昆布「フコイダン」を...

2015年9月
タカラバイオ研究チームリーダーの大野木 宏さんフコイダンは昆布、ワカメ、モズクなどの海藻のネバリのもとになっている高分子の多糖類で、食物繊維の一種である。1995年にタカラバイオが世界で初めてその化学構造と機能性の解明に成功した。同社は、ガゴメ昆布に含まれるフコイダンにがん細胞の増殖を抑制する作用やウイルス感染を抑制する作用、免疫力を高める作用などがあることを明らかにし、ガゴメ昆布「フコイダン」を...

2015年9月
「明るい〝看取り〟ができるようサポートしていきたい」と語る五島正裕さんホームケアクリニックこうべ 〒650-0027 神戸市中央区中町通2丁目3-2 三共神戸ツインビル8FTEL:078-371-3902 FAX:078-371-3903URL:homecare-kobe.com/ クリニックの名称には院長の名前が入っていることが多い。「ホームケアクリニックこうべ」の院長・五島正裕さんがあえてそ...
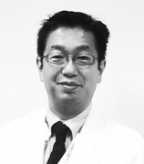
2015年9月
「患者さんが自ら副作用をコントロールする方法を身につけていただければと思います」と話す加藤晃史さん EGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんの治療には、イレッサ、タルセバに加え、第2世代のジオトリフも使われるようになった。ジオトリフの副作用には下痢、口腔粘膜炎(口内炎)、皮膚症状などがあげられる。そこで、副作用対策の情報提供を積極的に行っている専門医に、下痢対策を中心に伺った。...

2015年9月
やまだ みつぎ 千葉県がんセンター看護局通院化学療法室看護師長。2006年日本看護協会がん化学療法看護認定看護師認定。11年聖隷クリストファー大学大学院博士前期課程修了(看護学修士)。同年、がん看護専門看護師認定。13年より現職。日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、日本看護研究学会所属 吐き気や感染症に比べたら、皮膚の症状なんてまだマシ……仕方がない。そう言い聞かせて、つらい症状を我慢してはいませ...
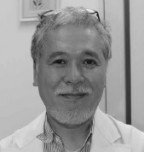
2015年8月
「患者さんの人生の歩みを知って、その上で一緒に考えたケアを行っていきたい」と語る鈴木さん鈴木内科医院 〒143-0023 東京都大田区山王3-29-1TEL:03-3772-1853 FAX:03-5743-3656URL:www.myclinic.ne.jp/clinic_s/pc/index.html 鈴木内科医院(東京都大田区)は、院長である鈴木央(ひろし)さんの父、荘...

2015年8月
やまだ みつぎ 千葉県がんセンター看護局通院化学療法室看護師長。2006年日本看護協会がん化学療法看護認定看護師認定。11年聖隷クリストファー大学大学院博士前期課程修了(看護学修士)。同年、がん看護専門看護師認定。13年より現職。日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、日本看護研究学会所属 感染を怖れるあまり、やりたいことを諦めて、家に閉じこもっていませんか? 抗がん薬治療で抵抗力が落ちる時期は、おお...

2015年8月
「患者さんが今まで通りの生活が送れるよう、サポートすることが大切だと思っています」と話す久保田 彰さん 手術がメインだった従来の治療から、化学療法と放射線治療を組み合わることで「切らない治療」が可能になった頭頸部がん。近年注目されている化学療法と放射線同時併用療法で起こりうる副作用とその対策には、どのようなものがあるのだろうか。 頭頸部がんは切らない治療をする方向へ 図1 頭頸部がんの種類 頭頸部...

2015年8月
「提供した情報を、患者さん自身が理解し、納得できることが、〝患者の力〟 を引き出す第一歩になります」と語る後藤志保さん 放射線治療は通院で治療を受ける患者さんが多い。そのため、副作用対策はセルフケアに頼らざるを得ない。いつ頃、どのような症状が現れてくるのかを前もって知らせ、適切に対応できるようにすることが大切だ。「患者の力」を最大限に引き出すセルフケア支援が、治療中のQOL(生活の質)維持に役立っ...

2015年8月
山内英子 聖路加国際病院ブレストセンター長/乳腺外科部長聖路加国際病院ブレストセンター長/乳腺外科部長の山内英子さんがんは「不治の病」のイメージが強いが、治療法などの進歩により、治療後もケアをしながらずっと付き合っていく「慢性疾患」と捉えるべきケースが増えている。若い患者さんや早期発見の多い乳がんはとくにその要素が強い。このようなケースを嚆矢として「がんの治療を終えてからの人生をどう充実させるか」...
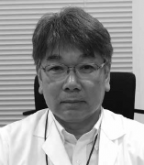
2015年8月
「放射線治療だけでなく、その周辺技術の開発も進んでいます」と語る秋元哲夫さん 放射線治療では従来から行われてきたX線、ガンマ線治療に加え、より集中性を高めてがん組織を叩くことができる陽子線、重粒子線などによる粒子線治療も行われるようになった。また従来に比べ、腫瘍周辺の正常細胞や重要臓器への照射をできるだけ減らし、なおかつ腫瘍に高線量の放射線を照射する技術も開発されている。そこで国立がん研究センター...