
新たな分子標的薬の登場で、劇的な効果がみられる人も 選択肢が増えてきた!! 非小細胞肺がんの最新化学療法
2010年1月
国立病院機構沖縄病院 副院長の 久場睦夫さん 肺がん全体の約8割を占める非小細胞肺がん。その非小細胞肺がんの治療において、化学療法は重要な位置を占めている。 とくに最近では、イレッサ、タルセバなど新たな分子標的薬の登場で、患者さんにはさまざまな選択肢が出てき始めた――。 肺がんの多くは化学療法が必要 [非小細胞肺がんに対する治療方針] 治療方針 1A期 手術 1B期 ...
肺がん

2010年1月
国立病院機構沖縄病院 副院長の 久場睦夫さん 肺がん全体の約8割を占める非小細胞肺がん。その非小細胞肺がんの治療において、化学療法は重要な位置を占めている。 とくに最近では、イレッサ、タルセバなど新たな分子標的薬の登場で、患者さんにはさまざまな選択肢が出てき始めた――。 肺がんの多くは化学療法が必要 [非小細胞肺がんに対する治療方針] 治療方針 1A期 手術 1B期 ...
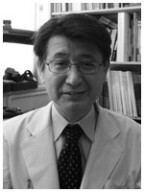
2009年12月
東京女子医科大学医学部 第1外科学講座・ 呼吸器外科主任教授の 大貫恭正さん 肺腫瘍を胸腔鏡下で最小限に切除する。そんな高度な手術が、可能になった。3次元のCG(コンピュータグラフィック)画像の開発により、病巣部を血管や気管支が取り巻いている様子を立体的に掌握できるようになったからだ。 3次元による画像で血管や気管支の位置を確認しながら胸腔鏡下手術を行う 手術開始から2時間半を経過し...

2009年11月
神奈川県立がんセンター 呼吸器外科医長の 坪井正博さん 肺がん手術でがん細胞をきれいに切除できても微小転移が起きている可能性がある。この微小転移が徐々に大きくなって再発につながることがあるので、再発予防のための術後補助化学療法としてUFTを服用することで2~3センチの腫瘍径の患者さんに有効であることが、神奈川県立がんセンター呼吸器外科の坪井正博さんらの無作為化比較試験の結果、明らかになった。 補...
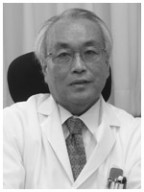
2009年7月
国立がん研究センター中央病院 肺内科医長の 久保田馨さん 他のがんと異なり、どの組織ががんになったかによって、いくつかのタイプに分けられる肺がん。 当然タイプによってがんの性質も違い、治療法も異なってくる。 今、その肺がんの組織型によって、どの抗がん剤がより効果を示すのかがわかってきた――。 手術不能でも組織型別の化学療法で成績アップ 肺がんは早期発見が難しく、手術不能の段階で見つかることが多い...

2009年1月
岡山大学医学部 放射線科教授の 金澤右さん ラジオ波治療は、体に対する侵襲が少なく、臓器の損傷を最低限にとどめて繰り返し治療ができるのが大きな利点。すでに早期の肝がんでは標準治療の1つとして認められていますが、最近では他のがんでも有望な局所治療法として期待されています。 中でも、早くから肺がん治療への応用を研究してきたのが、岡山大学医学部放射線科教授の金澤右さんです。世界でも最多の治療例を持...

2008年12月
福岡大学医学部呼吸器・ 乳腺内分泌・小児外科教授・ 診療部長の岩崎昭憲さん 内視鏡下外科手術は、一般の手術に比べて傷が小さく、体への負担も少ないことから、最近はさまざまながん治療に利用されています。肺がんでも、早期がんを対象に胸腔鏡下の手術が普及しつつあります。 しかし、内視鏡下外科手術には手術を行う医師の技術格差も大きいと言われます。早くから胸腔鏡下の肺がん手術に取り組み、安全性の向上に貢献し...

2008年8月
埼玉県立がんセンター 呼吸器科部長の 酒井洋さん 2008年の米国臨床腫瘍学会(ASCO)では、肺がん領域においてもいくつかの注目すべき発表があった。なかでも日本の患者さんにとって関心が高いと思われるのは、全身状態不良の非小細胞肺がんでも、EGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子変異があればイレッサ(一般名ゲフィチニブ)がファーストライン(1次治療)で有効という日本の研究グループの報告である。また、...
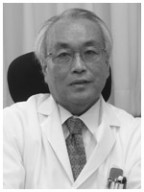
2008年7月
国立がん研究センター東病院 呼吸器科医長の 久保田馨さん 肺がんの8割以上を占める非小細胞肺がんの治療が大きく変わってきている。術後の化学療法(補助療法)の有効性が明らかになる一方、進行がんでも化学療法によって生存期間の延長が認められるようになり、内科治療での根治が期待できるケースも出てきた。効き方に違いがあるさまざまな薬が登場しており、近い将来がんのタイプ別に、より効果的で安全性の高い薬を選ぶ時...

2008年7月
国立がん研究センター中央病院 総合病棟部長の 田村友秀さん 小細胞肺がんは進行が早く、他の臓器に広がると治療に難渋するたちの悪いがんとされてきた。 けれども、初回治療によく反応し、化学療法や放射線療法が効き、多くの患者さんに延命効果が期待できるがんでもある。 進行が早く広がりやすいが、治療効果も高いがん 胸部を写したレントゲン写真。←の部分が小細胞がん 「小細胞肺がん」は肺がんの10...

2008年7月
北里大学 呼吸器外科名誉教授の 吉村博邦さん 肺がんは、がんの中でも難治がんといわれ、1955年以降肺がん死は増えつづけています。 しかし、一方で新たな治療薬が開発され、治療法も進歩しています。これを科学的に評価する大規模臨床試験も次々に行われています。 こうした結果を元に、『EBMの手法による肺癌診療ガイドライン2005年版』が作成されました。このガイドラインにもとづき、北里大学医学部...