
神宮寺 「いのちの現場」に身を置く住職が目指す、温泉場でのホスピス運営
2007年3月
世界で見てきたホスピタリティを生まれ故郷にフィードバック 山門が365日閉じられることがない 古刹・神宮寺 自分らしさを保ったまま生きていくことは、大病に罹患した人にとって重要なテーマである。 そんななか世間の耳目を集めているのが、生老病死を支える「コミュニティケア」だ。 長野県松本市にある神宮寺の高橋卓志住職は、生まれ故郷の温泉街にホスピスを作ろうと、奮闘する日々を送っている。 「もてなし...

2007年3月
世界で見てきたホスピタリティを生まれ故郷にフィードバック 山門が365日閉じられることがない 古刹・神宮寺 自分らしさを保ったまま生きていくことは、大病に罹患した人にとって重要なテーマである。 そんななか世間の耳目を集めているのが、生老病死を支える「コミュニティケア」だ。 長野県松本市にある神宮寺の高橋卓志住職は、生まれ故郷の温泉街にホスピスを作ろうと、奮闘する日々を送っている。 「もてなし...
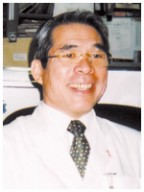
2007年3月
ふくだ かずのり 銀座東京クリニック院長。昭和28年福岡県生まれ。熊本大学医学部卒業。国立がん研究センター研究所で漢方薬を用いたがん予防の研究に取り組むなどし、西洋医学と東洋医学を統合した医療を目指し、実践。 乳がんの漢方治療の注意点 がんの漢方治療は、患者さんの体力や抵抗力や回復力を高め、不快な自覚症状を改善してQOL(生活の質)を良くすることを主な目標としています。 通常は、体力や食欲の状...
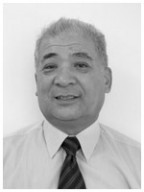
2007年2月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 73歳の男性。腹痛があり、近くの病院で腹部超音波を施行したところ、偶...

2007年2月
在宅では、スタッフや設備の充実した施設ホスピスほど手厚いケアは望めない。 しかし、それに優るケアがあれば我が家ほど居心地のいいところはない。 兵庫県尼崎市で開業している桜井隆さんは、「ふわっとフィットした距離感でのケア」をモットーに診療をしており、そこが患者サイドに受けている。 8割以上が病院死の異常な日本の中でがんばり抜く 以前、ある施設ホスピスに取材に行ったとき、看護師長にこう非難されたことが...
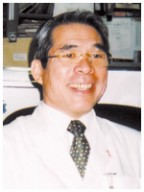
2007年2月
ふくだ かずのり 銀座東京クリニック院長。昭和28年福岡県生まれ。熊本大学医学部卒業。国立がん研究センター研究所で漢方薬を用いたがん予防の研究に取り組むなどし、西洋医学と東洋医学を統合した医療を目指し、実践。 抗がん剤とハーブ・漢方薬の相互作用 前回、抗がん剤治療中に適切な漢方治療を併用すると、症状の改善や副作用の軽減が期待できることを紹介しました。しかし米国では、手術前や抗がん剤治療中のハーブ類...
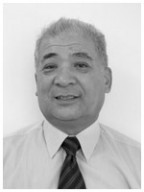
2007年1月
もりやま のりゆき 1947年生まれ。1973年、千葉大学医学部卒業。米国メイヨークリニック客員医師等を経て、89年、国立がん研究センター放射線診断部医長、98年、同中央病院放射線診断部部長で、現在に至る。ヘリカルスキャンX線CT装置の開発で通商産業大臣賞受賞、高松宮妃癌研究基金学術賞受賞。専門は腹部画像診断 患者プロフィール 52歳の男性。腹部の断続的な不定愁訴を感じ、受診をしたところ、胃がん...

2007年1月
母性的な愛に包まれた、家にかぎりなく近い「かあさんの家」で患者を癒す 我が家で過ごしたい、介護されたい、と思っても、1人暮らしだったり介護者が多忙だったり、いなかったりすると、それは実現できない。 宮崎の地でこの問題を解消しようと試行錯誤して編み出したのが、家にかぎりなく近いもうひとつの家「かあさんの家」だった。 残された家族に悔いを残さない医療の実現を目指したものでもあった。 「宮崎をホスピスに...
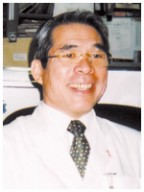
2007年1月
ふくだ かずのり 銀座東京クリニック院長。昭和28年福岡県生まれ。熊本大学医学部卒業。国立がん研究センター研究所で漢方薬を用いたがん予防の研究に取り組むなどし、西洋医学と東洋医学を統合した医療を目指し、実践。 抗がん剤で正常組織もダメージを受ける 抗がん剤はがん細胞だけでなく、骨髄細胞や免疫組織や消化管粘膜など細胞分裂の盛んな組織にもダメージを与えます。その結果免疫力の低下や、白血球や血小板の減少...

2007年1月
京都大学大学院 医学研究科助教授の 佐藤恵子さん 静岡がんセンターのCRCの 齋藤裕子さん エビデンスに基づいた臨床試験臨床試験というと、なかには「人体実験」という言葉を想起し、患者がモルモットのように扱われるイメージを持つ人もいるかもしれない。しかし現実の臨床試験はまったく違っている。とくに97年に厚生労働省で臨床試験実施要領(GCP)が政令として定められてからは、エビデンス(科学的...

2007年1月
癌研有明病院顧問の 中島聰總さん 臨床試験に参加するメリット がんを克服するためには、科学的な研究は欠かせません。その科学的な研究のひとつが人間を対象とした臨床試験です。実際、ここ50年のがん治療をはじめ、検査、がんの発生、進行のメカニズムなどにおける飛躍的な発展は、臨床試験なくしてはあり得ませんでした。この点は誰もが認めるところでしょう。 [臨床試験に参加するメリット・デメリット] メリ...